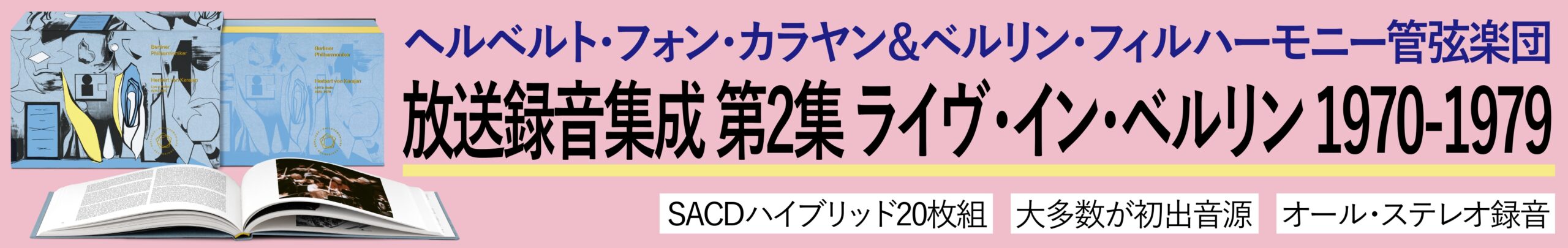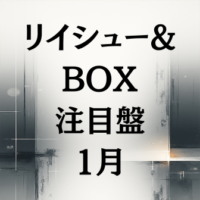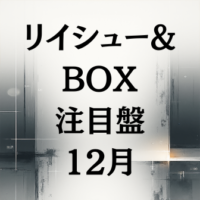シューベルト:交響曲第7番《未完成》,同第4番《悲劇的》
パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン(DKAM)
〈録音:2025年5月〉
[プロデューサー:フィリップ・トラウゴット
レコーディング・エンジニア:ジャン=マリー・ゲイセン
レコーディング&ポスト・プロダクション:ポリヒムニア・インターナショナル
[RCA Red Label(D)SICC10489]
※2025年12月24日発売予定
【商品Linkfireはこちら】
悲劇の音楽
思わず唸ってしまう。パーヴォ&ドイツ・カンマーフィルがシューベルトをまだ録音していなかったことに。そして、満を持した初録音が「7番&4番」のカップリングである事実に。
手前味噌で恐縮だが、シューベルト全交響曲の4夜にわたる演奏会を企画したさい、筆者はこの2つの短調作品を、まったく当然のように別々のプログラムに配した(山田和樹指揮、住友生命いずみホール、2022年)。あまりの破壊力ゆえだ。それをあえて並べることで、しょっぱなから悲劇の凝集的なパワーが炸裂する。これ以上ない説得力である。
いま悲劇といった。じっさい1800年代のドイツには悲劇の旋風が巻き起こっていたことをご存じだろうか? 英雄の不条理な死が世界に自由がもたらす、その反キリスト教的な世界観にシラーをはじめとする哲学者は魅せられ、火種はすぐウィーン市政の演劇界に燃え移る。音楽界では、ベートーヴェンが《コリオラン序曲》や第5交響曲の「ハ短調」でこの思想をつづると、19歳のシューベルトもそれに刺激され、同じハ短調による第4番の自筆譜に「悲劇的」と記したのだった(参考:拙著『わが友、シューベルト』(アルテスパブリッシング)終章)。
しかしその道は、先輩とあまりにちがっていた。「短調の暗から、長調の明へ」。この大きな軌道はベートーヴェンと変わらないのだが、明と暗が刹那に切り替わるような“陰影”こそ青年シューベルトの美学である。
耽溺しない美学、あるいはドイツの森?
この美学が、25歳で書かれた《未完成》だけでなく、19歳の第4番《悲劇的》にもそれがはっきり刻まれていることを、本ディスクはまざまざと教えてくれた。第2楽章アンダンテを聴こう。「ドルチェ」と記されている。数年前にN響で第4番を振った鈴木雅明さんがNHKのテレビ番組で言っていたように「知ってますか、レモンの花咲くあの国を(Kennst du das Land)?」がピッタリの旋律。まさに甘美な歌による逃避の世界……かと思いきや、パーヴォが描きだすのは霧に包まれた夜の世界だ。ppのテーマはほとんど啜り泣くように控えめであり、低弦の歩みは重く暗い。これにオーボエの対旋律がわびしく寄り添う。ゲルマンの森に彷徨うかのように。やがて第1楽章「ソラシド」のテーマが戻ってくる中間部は、悲劇の再来である。ヴァーグナーかと思うほどラディカルな不協和音が積み重なっていく箇所なのだが、むしろ嘆きの2音モティーフは意外なほどあっさりと、大きな旋律線のうちに包摂されてゆく。
このように過度な耽溺を避ける大局的な形式観を、簡素で端正なフレージングが支える。それに木管楽器のなんと鮮やかに聴こえてくることか。《未完成》第2楽章は楽器の細やかな組み合わせの妙が随所に光るのだが、随所でドキっとさせられる。冒頭まもない楽器のコンビネーション(Fl+Cl+Vc)は、こんなに美しい音がするものだったのか。
付属の解説もきわめて充実している。オケの広報は「ドイツ」カンマーフィルがついに「ウィーン」の音楽に乗り出したことを、大きく打ちだしているようだ。独墺の別はセンシティヴゆえあまり文字どおりに取ることでもないが、たしかに説得的な物語といえる。メロディに耽溺しない禁欲性、ホイリゲではなく暗き森のそよぎ——。つづくディスクを待ち遠しく思うとともに、このオケでパーヴォがベートーヴェンをどう響かせていたか、あらためて聴いてみたくなった。
堀朋平 (美学・音楽学)
協力:ソニーミュージック