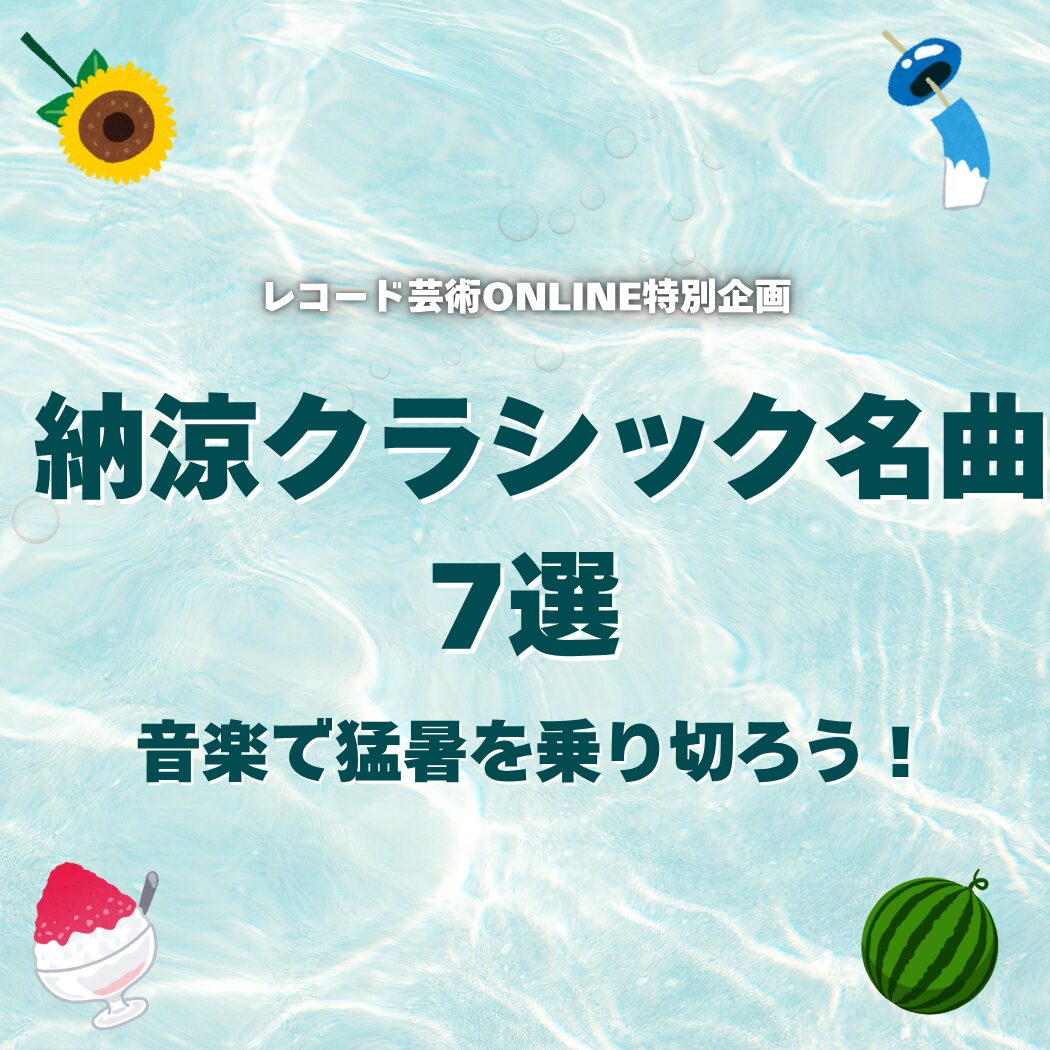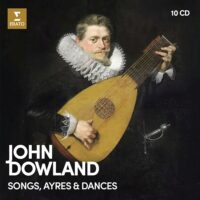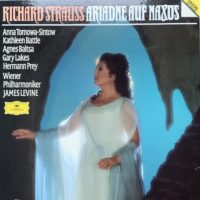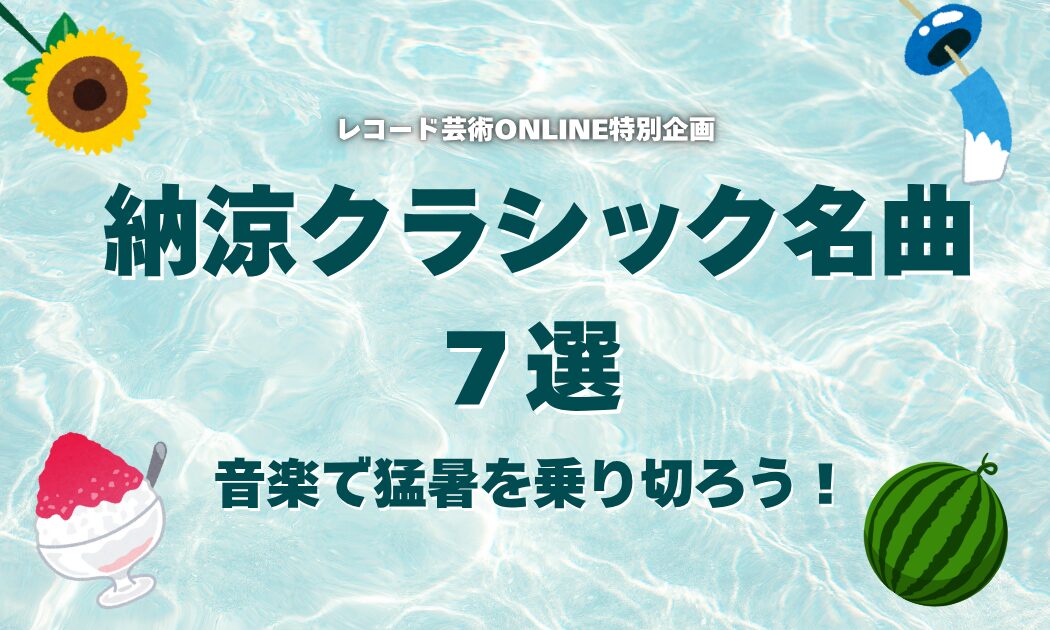
残暑お見舞い申し上げます。今年は全国的に猛暑が続いています。そんなとき、クラシックファンならどんな曲を聴いて涼をとるのでしょう? ここでは夏の風物詩などを描いたオススメの7曲をご紹介。音楽を聴いて、せめて気分だけでも涼んでみてはいかがでしょうか。
クロード・ドビュッシー(Claude Achille Debussy 1862~1918)
花火(前奏曲集第2集第12曲,1913)
まず夏の風物詩、花火から。ヘンデル《王宮の花火の音楽》は実際に花火の打ち上げとともに演奏された曲として有名です。一方シンプルに花火を描写して名高いのはストラヴィンスキーの幻想曲《花火》ですが、豪快なオケは暑苦しいので、ここではドビュッシーのピアノ曲をご紹介。7月14日の革命記念日の情景で、聴いているといろいろな花火が煌めき、最後には大きな花火が打ちあがります。新しい演奏もいいですが、ここではフランソワの名演で古き良きフランスを味わいたいものです。
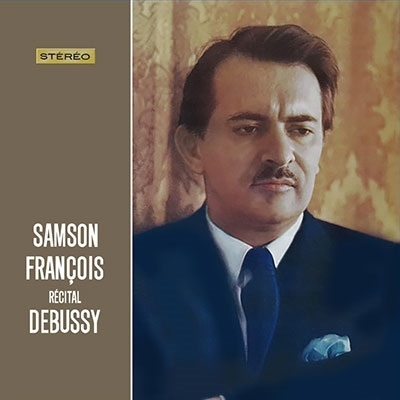
ドビュッシー/ピアノ作品集
サンソン・フランソワ(p)
〈録音:1961年7月~1970年10月〉
[TOWER RECORDS DEFINITION SERIES(S)TDSA292(4枚組)]SACDハイブリッド
※タワーレコード限定
カミーユ・サン=サーンス(Charles Camille Saint-Saëns 1835~1921)
水族館(組曲《動物の謝肉祭》第7曲,1886)
花火のあとは水族館で涼を取りましょう。サン=サーンス《動物の謝肉祭》に収められている〈水族館〉は魚が泳いでいる様子をフルートやチェレスタの静かなメロディと2台ピアノによるアルペジオで彩った小品です。私的な初演はオーストリアで行なわれたのですが、サン=サーンスが描いたのはどこの水族館だったのでしょうか? 小澤がナレーションも務めたボストン響盤で、その雰囲気を楽しんでください。
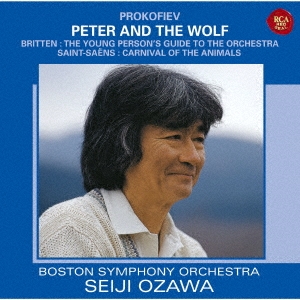
プロコフィエフ:交響的組曲《ピーターと狼》,サン=サーンス:組曲《動物の謝肉祭》,ブリテン:青少年のための管弦楽入門
小澤征爾(指揮&ナレーション)ボストン交響楽団,ジョン・ブラウニング&ギャリック・オールソン(p)
〈録音:1992年2月〉
[RCA(D)SICC40288]
【試聴・購入はこちら】
エリック・サティ(Eric Satie 1866~1925)
ウォーター・シュート(《スポーツと気晴らし》第15曲,1914)
次は水遊び。サティ(今年没後100年)がシャルル・マルタンの風俗画20枚に音楽を付けたピアノ小品集《スポーツと気晴らし》には、〈魚釣り〉〈ヨット〉〈海水浴〉など、夏の遊びがふんだんに盛り込まれています(〈花火〉まである!)。この〈ウォーター・シュート〉は舟を滑らせて水面に下りるもので、リアルな曲調がエスプリを感じさせます。ケフェレックの演奏は滑り落ちる感覚がすてきです。
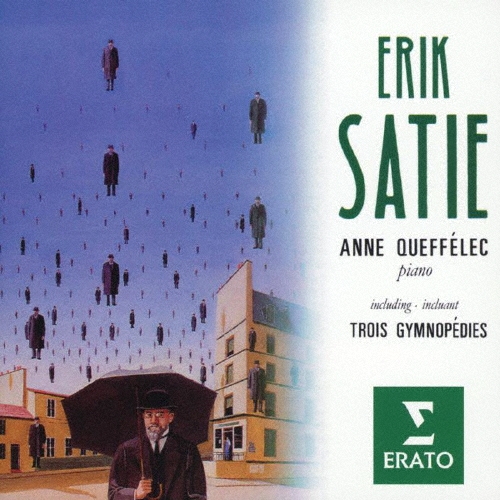
サティ:ピアノ作品集
アンヌ・ケフェレック(p)他
〈録音:1988年3月,1990年10月〉
[ワーナー(D)WPCS28502(2枚組)]SACDハイブリッド
【試聴・購入はこちら】
モーリス・ラヴェル(Maurice Ravel 1875~1937)
水の戯れ(1901)
水遊びの続きを。水を描いた音楽といえば、リスト《エステ荘の噴水》(1877)やドビュッシー《水の反映》(1904~05)も重要ですが、夏に聴きたいのは生誕150年を迎えたラヴェルのこの曲でしょう。冒頭からラヴェル独得の硬質な響きが水滴や水流を見事に描ききっていて、聴いていると涼味がたっぷりと感じとれます。アルゲリッチのデビュー盤の瑞々しさは、今でも一頭地を抜いています。
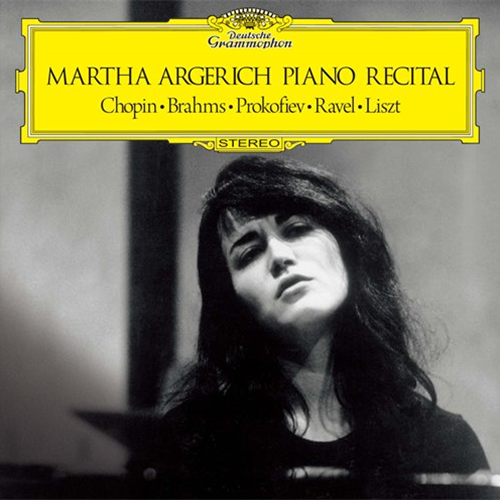
マルタ・アルゲリッチ/デビュー・リサイタル
〔ショパン:スケルツォ第3番,舟歌,ブラームス:2つのラプソディ,ラヴェル:水の戯れ 他〕
マルタ・アルゲリッチ(p)
〈録音:1960年7月〉
[DG(S)UCCG41052]
【メーカー販売サイトはこちら】
アルテュール・オネゲル(Arthur Honegger 1892~1955)
夏の牧歌(1920)
避暑地に出かけるのも夏の過ごし方です。この小品はオネゲル初期の小管弦楽のための交響詩で、彼の出世作となりました。暑さよりも爽やかさが勝って聴こえるのは、作曲したのが両親の故郷であるスイスの景勝地ヴェンゲンだったせいかもしれません。名匠プラッソンの指揮で爽やかな夏を楽しんでください。
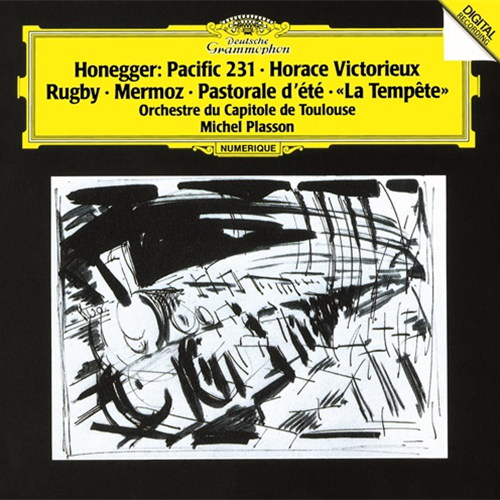
オネゲル:管弦楽作品集
〔《テンペスト》のための前奏曲,夏の牧歌,パシフィック231―交響的断章第1番 他〕
ミシェル・プラッソン指揮トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団
〈録音:1991年6月,11月〉
[DG(D)UCCS50383]
【メーカー販売サイトはこちら】
ジャン・シベリウス(Jean Sibelius 1865~1957)
鶴のいる情景(劇音楽《クオレマ》より,1906)
さらに避暑のため北欧に出かけます。フィンランドの風景を思い起こさせるシベリウスの作品は、日本人にとって「納涼気分」を味わえる曲ばかりです。1903年劇付随音楽として作曲され、後に独立した曲に編曲されたこの《鶴のいる情景》は、雪原で2羽の鶴が鳴き交わす様子を描いた音詩です。この曲以外にも《トゥオネラの白鳥》、交響曲第6番など、冷涼感たっぷりの曲がたくさんありますので、この時期はシベリウスで涼を取ってみてはいかが?
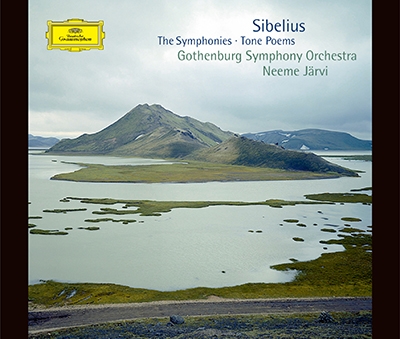
シベリウス/交響曲全集,管弦楽曲集
ネーメ・ヤルヴィ指揮エーテボリ交響楽団 他
〈録音:1992年~2005年(一部L)〉
[タワーレコード×ユニバーサル(D)PROC2050(6枚組)]
※タワーレコード限定
アントニオ・ヴィヴァルディ(Antonio Vivaldi 1678~1741)
協奏曲ト短調《夏》(ヴァイオリン協奏曲集《四季》第2番,1725出版)
最後は夏そのものを描いた名曲を。これは有名な協奏曲集《四季》の1曲です。第1楽章では夏の気怠さが見事に表現され(イタリアの夏もかなり暑いみたいです)、最終楽章では嵐が巻き起こります。実は《冬》の最終楽章で、《夏》の第1楽章のメロディが聴こえてきて「夏をなつかしむ」ところがあります。お気づきでしょうか? いろいろな演奏がありますが、ここではソネットの朗読がついたサバール盤で。
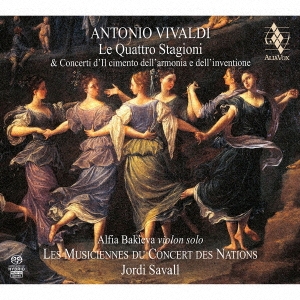
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》他
ジョルディ・サバール指揮レ・ミュジシャン・デュ・コンセール・デ・ナシオン,アルフィア・バキエヴァ(vn)オリヴィア・マネスカルキ(語り)
〈録音:2024年1月〉
[Alia Vox(D)AVSA9958(2枚組,海外盤)]SACDハイブリッド
Select & Text=北村洋介(音楽ライター)