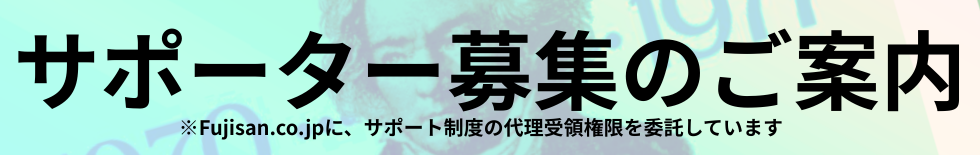音楽評論家・城所孝吉氏の連載第17回は、マーラーの交響曲第4番を取り上げます。ご承知の通り、マーラーの交響曲の中では最もシンプルで明朗、無邪気で牧歌的、しかしながらその裏には、孤独や絶望、死の影といった悲劇的な要素が横たわっている、ということもしばしば言われます。本稿では、その解釈に疑問符を付す一方、作品内容に別の角度からも迫っていきます。
交響曲第4番の二面性
マーラーの交響曲第4番(1900年完成)は、しばしば「皮肉的である」と評される。「牧歌的な曲想は、背後にあるものを隠す仮面であり、文字通りに理解してはならない」という主張だが、私も学生の頃、この解釈を頻繁に耳にした。例えばドイツ文学者の池内紀は、マーラーは童話的で無邪気な表面の下で、孤独や不安、死の影を表現しようとした、というようなことを言っている。これは日本だけではなく、欧米の文献でもよく見られるので、おそらくアドルノあたりが出どころだろう。それを昭和時代の評論家や文学者が輸入・踏襲したのだと考えられる。
私は同説を読むたびに「本当だろうか」と思ってきた。というのはそこに「悲劇的な含意がある方が深い」といった、一種のイデオロギーを感じたからである。交響曲第4番には、まちがいなくダークな側面がある。しかし全体が、孤独や絶望を描くために存在しているとは、私には思えない。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。