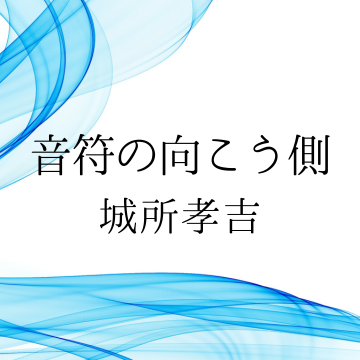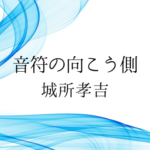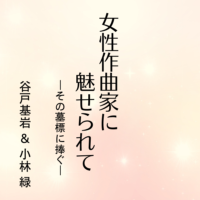音楽評論家・城所孝吉氏の連載は2年目に入り「第2シーズン」が始まります。「第1シーズン」(最初の12回)では「解釈とはどういうことか」という理論的な側面を扱ってきましたが、今回からは、氏自身が実際の作品をどう解釈するか、という趣旨で進めてゆきます。つまり「理論編」から「実践編」へシフト。毎回個々の楽曲を取り上げますが、そこでの解釈は必ずしも「正しく」ある必要はありません。「作品の真実は誰にもわからない」「解釈者には自分が信じる通りに読む自由がある」そして「推論に説得力があればいい」のですから。最初のテーマ曲は、シューベルトの交響曲第9番(本文中では城所氏の原稿通り第8番と表記)《ザ・グレイト》です。
シューベルトの音楽における「自然」
もし無人島へ持ってゆく交響曲を一つだけ選べ、と言われたら、読者諸賢はどの曲を選ぶだろうか。私はモーツァルト、ベートーヴェン、ブルックナー、マーラーのいくつかに想いを巡らせたあと、あまり迷わずに、直観的にシューベルトの《グレイト》と答えるだろう。それはこの作品が、他のどの曲よりも私の心の奥底にある何かに触れ、揺さぶってやまないからである。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。