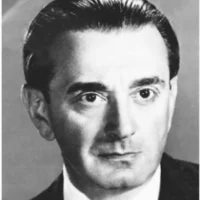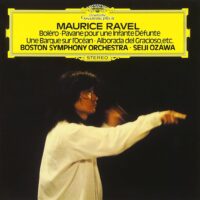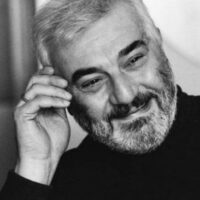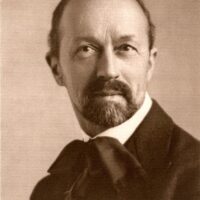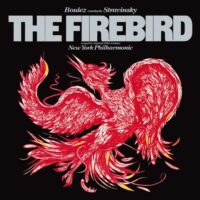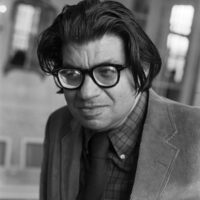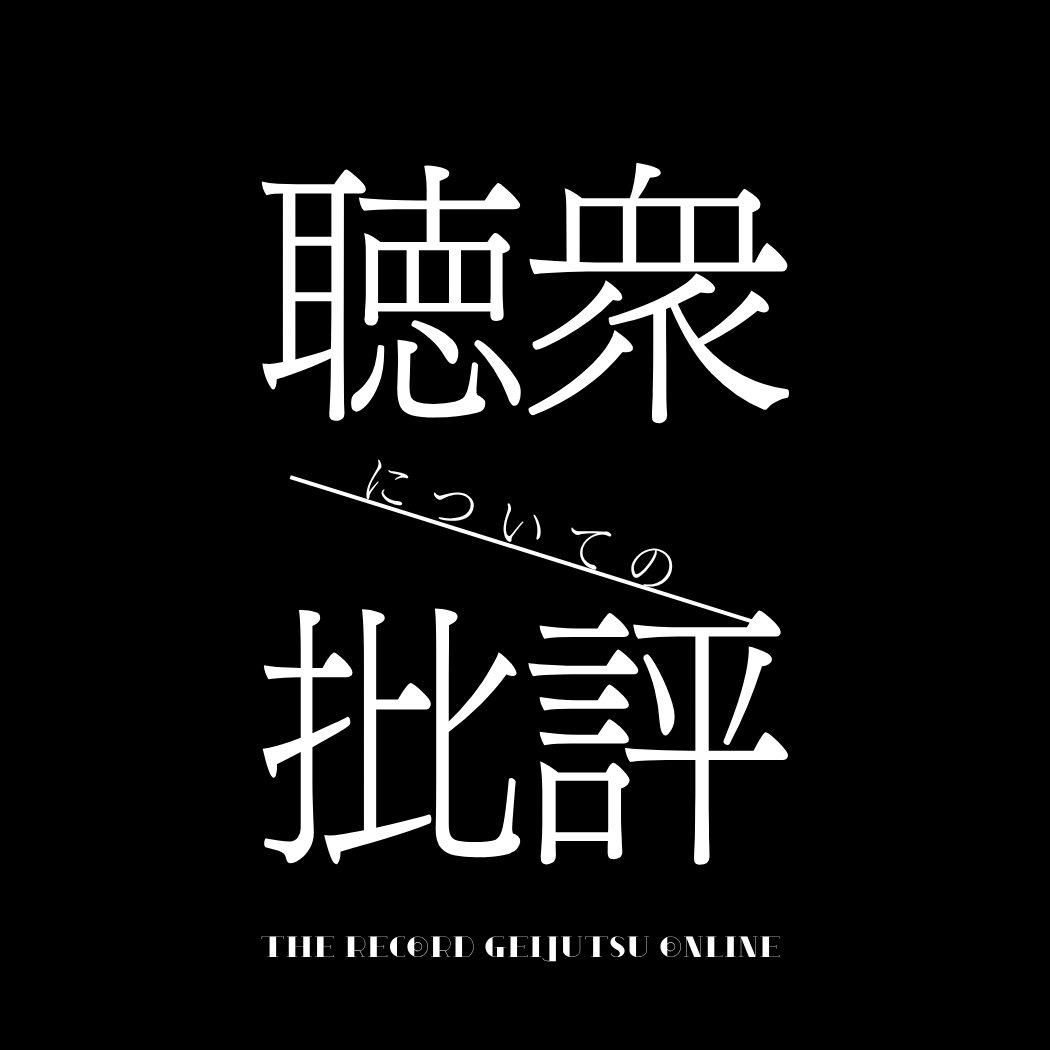
「レコ芸アーカイブ 編集部セレクション」は、編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとにキュレーションするコーナーです。
第3弾は「聴衆についての批評」。ここでいう聴衆は、決して読者にかぎりません。作曲する人、演奏する人、CD・レコードをつくる人、売る人、買う人、言葉を編む人……録音芸術に関わる人すべてが、それと対峙する点で「聴衆」といえます。
第3弾の1回目として、1994年9月号に掲載された諸井誠さんの論考「『不滅の名盤』の条件」を4回に分けて、連日お届けします。タイトルからは想像しにくいですが、その内容の大部分は聴衆論。掲載時からすでに30年を経過しているものの、その文明批評を含む厳しいまなざしは、幸か不幸か、2025年のいまも今日性を保っているように思われます。
※文中の表記・事実関係などはオリジナルのまま再録しています。
【構成】
・はじめに
・作品と演奏、そして聴き手
・演奏行為における時代性と時代精神(ここまで①※無料公開)
・グレン・グールドを考える
・演奏における地域性(ここまで②※有料公開)
・精神と技術
・「巨匠の時代」の終焉
・普遍的演奏とは(ここまで③※有料公開)
・聴き手の側の変化について
・演奏される作品の質・水準
・おわりに(ここまで④※有料公開)
こちらの記事は「『不滅の名盤』の条件」①の続きです。未読の方は、ぜひ①からお読みください。
広く深い知識を貯えながらも、今日的精神、今日的感覚で、
創造的想像力をもって作品にアプローチする姿勢が欲しい。
それを実現して見せたのが、フルトヴェングラーであり、
グールドであったのだと思う。
「グレン・グールドを考える」より
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。