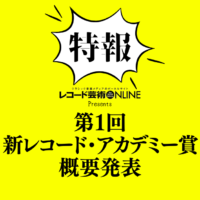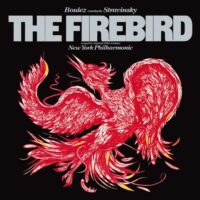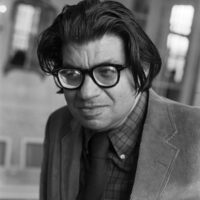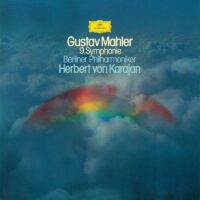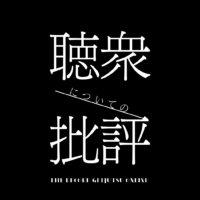≫特捜プロジェクト・アニバーサリー作曲家の他の記事はこちらから
1953年甲府市生まれ。1976年から18年半にわたり日本コロムビア、ワーナー・パイオニアにてクラシック音楽の日本盤編集・編成・宣伝作業に携わる。1995年から音楽評論家。30年で約7,000のコンサートに通うとともに多数の輸入盤CDを蒐集。2002年より「知られざる作品を広める会」を主宰。2003年~2024年尚美学園大学非常勤講師。第18、19回日本ハープ・コンクール審査委員長。共著に「古楽CD100ガイド」、「女性作曲家列伝」。
***

ほとんどの作品が
ピアノ曲と歌曲
今年(2007年)は女性作曲家のアニヴァーサリー・イヤーの当たり年と言えるのではないか? フランスの作曲家たち、セシル・シャミナード(1857~1944)の生誕150年(8月8日)、マリー・グランヴァル(1830~1907)の没後100年(1月15日)、そしてここにご紹介するアガーテ・バッケル=グレンダールは没後100年(6月4日)に当たる。アーロン・コーエンが編纂した「女性作曲家事典」(第2版)には19世紀に活耀した作曲家たちが1103名記されているので驚くには当たらないかもしれないが、これら3人は19世紀後半にそれぞれ看過できぬ足跡を残しているだけに重要だ。
女性作曲家には大きく分けて2つのタイプがあるように思われる。ひとつは男性中心社会である交響・管弦楽作品、オペラといった大規模作品に積極的に取り組んで行った人たち。こうしたタイプの女性としてはルイーズ・ファランク、ファニー・ヘンゼル、オギュスタ・オルメス、エセル・スマイス、マリー・グランヴァル、エイミー・ビーチといった名前を挙げることができる。これに対して、そうした大規模作品には興味がないかもしくは積極的には取り組まず、もっぱら歌曲およびピアノ曲という当時楽譜の需要が最も大きいジャンルをメインに才能を発揮して行った人たちがいる。こうしたタイプの作曲家で最も成功した例はシャミナードだが、グレンダールはその創作が徹頭徹尾ピアノ曲と歌曲にほほ限定されているという点でより一層こうした傾向が顕著な作曲家といえるだろう。しかも彼女は周囲からその才能を高く評価され、国際的な活躍の場を提案されてもそれを拒否してノルウェーに留まり続けたという点で、他の女性作曲家たちとは一味違ったユニークな人生を歩んだ。「地球規模で考え、地域的に行動する」というエコロジーの思想を実践するであろう21世紀的な作曲家の予言者と言えるかもしれない。ではその生涯とはどんなものだったのだろうか?
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。