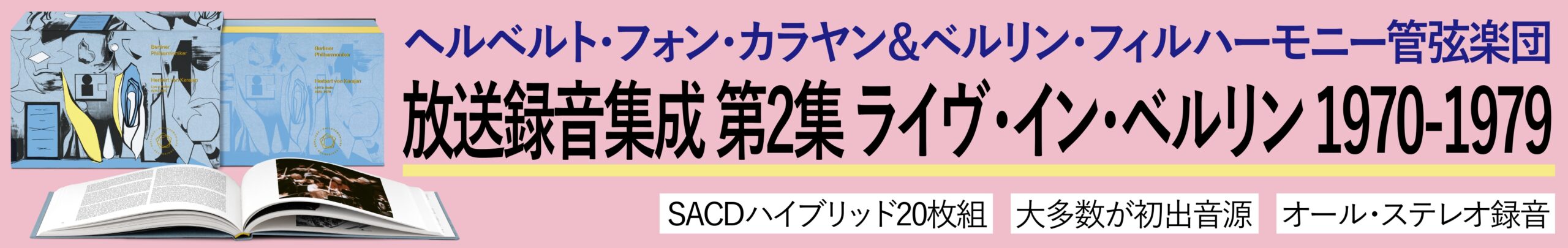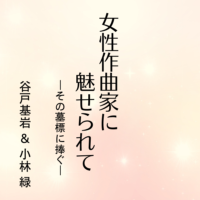あらゆる種類の発話がグルグル移動する
――俺たちは日本語でリズムを作ることを突き詰めようと思ったんだ。そんな時に手に取ったのが、この『日本語の歴史』(山口仲美、岩波新書)。
Mummy-D(RHYMESTER)
もうずいぶん前の話。発刊されたばかりの三宅幸夫『ブラームス』(新潮文庫)を読んだ時に、あのブラームスにもオペラを書く計画があったことを知って少々驚いた。この本によれば、しかし彼自身は台本全体に音楽を付けるのは不自然だと感じており、つまりは劇のしかるべき場所で音楽が入るような構成を考えていたという。まだ大学生だった当時のわたしはハタと膝を打ったものだ。というのも、オペラというのはどうにも仰々しく、不自然なものだと感じていたからである(たいして観てもいなかったのに!)。まさにブラームスが思い描いたようなオペラが観たい、そう思った。
しかし、今はまったく逆だ。偉そうで申し訳ないのだが、ブラームスは「分かってないな」と思う。
■
演劇+音楽という舞台の形態は、言うまでもなく古代ギリシアから存在していた。洋の東西を問わず、こうしたタイプの音楽劇は多くの国にあったはずだ。劇があれば音楽をつけたくなるに決まっているし、となれば、そのなかで登場人物が歌をうたうことだってあるだろう。
しかし、16世紀から17世紀へと移り変わるころにイタリアで誕生したのは、レチタティーヴォという特殊な技法を用いて、音楽を途切れさせずに続けてしまう、新しいタイプの音楽劇だった。この手法によって、頭から終わりまで音楽が鳴り続けるなかで、芝居が展開してゆくことが可能になったわけである。これこそがオペラだ。
「劇」も「歌」も、そして「劇+歌」も大昔から存在していた。しかし最初から最後まで音楽を途切れさせないというアイディアは、おそらくそれまでに類例がない、破天荒といってもよいものだったのではなかろうか。そんな前提にたつと、ブラームスが作ろうとしていたのが「オペラ」とは異なるものであったことが分かる。
つまり、オペラを単なる「音楽劇」だと考えるのは、大きなまちがいだと思うのだ。実際、オペラ史を紐解けば――現在にいたるまで――パリのオペラ座に代表される格式ある劇場ではセリフが入る(=音楽が途切れる)演目は若干の例外を除けば上演できないことが分かる。セリフの入る《カルメン》が、悲劇であってもオペラ・コミック座で初演されたのはご存じの通り。
音楽が途切れないことに加えて、古式ゆかしいオペラにはもうひとつ、きわめて重要な条件がある。それは台本が韻文で書かれていることだ。少なくとも19世紀終わりくらいまでは――モーツァルトやベルカントの作家たちはもちろん、ヴェルディだってプッチーニだって――オペラの台本は韻文で書かれていた。そんなこと別にどうでもいいじゃん、という人もいるかもしれない。しかし韻文とは、換言すれば「音楽化された言語」に他ならない。言語の論理にくびきをかけて、音楽の側へと強力に引き寄せること。言語の音楽的側面を強調し、音楽の鋳型に言葉を注入して鍛えあげること。この作業によって、はじめて言葉と音楽は溶け合い、一体化を遂げる。
もちろん現代のオペラの場合、レチタティーヴォも韻文も、そのまま用いるわけではないけれども、しかし、調性音楽を知らなければロクな無調音楽が書けないように(まあ、例外はあろうが)、こうした歴史や原理をまるで顧慮せずにオペラを書こうとするならば、ロクなオペラにならないであろうことは容易に想像がつく(まあ、例外はあろうが)。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。