
Interview & Text=山野 雄大(ライター/音楽・舞踊)
取材協力・写真提供=ナクソス・ジャパン
6月のベルリン・フィル定期演奏会への初客演も成功裡に終えた山田和樹。2026/27シーズンからはベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者兼芸術監督の任につくのを前にして、いよいよ多忙をきわめるマエストロだが、2016年から芸術監督兼音楽監督を務め、良好な関係を紡いできたモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団(2024年春の来日ツアーも大好評を博したばかり)とのレコーディングが続々と届いている。これがまた、フランス音楽に入門しようというリスナーにも愉しいアルバムから、相当以上のマニアまで驚かされる秘宝発掘まで、バラエティに富んだ優れた仕事揃いだ。
ビゼー、グノー、サン=サーンスの「はじめての交響曲」
まずユニークなのが、『はじめての交響曲』。有名なビゼーの交響曲ハ長調にグノーの交響曲第1番、サン=サーンスが少年時代に書いた(!)交響曲イ長調と、フランスの作曲家たちの「はじめての交響曲」を併せ聴くことで、フランス音楽の豊かな土壌を体感しようという2枚組のアルバムだ。
このうち、ビゼーの(少年時代の作ながら、その清々しさから広く愛されている)交響曲は再録音となる。録音デビュー期の横浜シンフォニエッタとの録音〈2009〉と聴き比べると、テンポ感もぐっと落ち着きをみせる今回の新録音について、「歳を取ったんですよ!」と山田は笑う。「モンテカルロ・フィルはオペラも演るオーケストラですから、ビゼーの交響曲でも第2楽章の歌い回しなど、そういう土壌が生きていますね。これらの作品は、フランスの作曲家たちがまだ交響曲を書いていた時代、なんですね。その後になくなっちゃうんですけど……。彼らが初めて交響曲を書こうとしたとき、その前にはベートーヴェンなど『交響曲というのはこういうものだ』という伝統的なイメージがある。ですから、フランスの作曲家でもこうなるんだなぁ、と今回の収録で思わされる(笑)」
モンテカルロ・フィルとも豊かな経験を重ねてきたマエストロだが、「任期もあと1年なので、そのあいだにできるものはできればと思っていて。次は『2番目の交響曲』かな、とか(笑)」
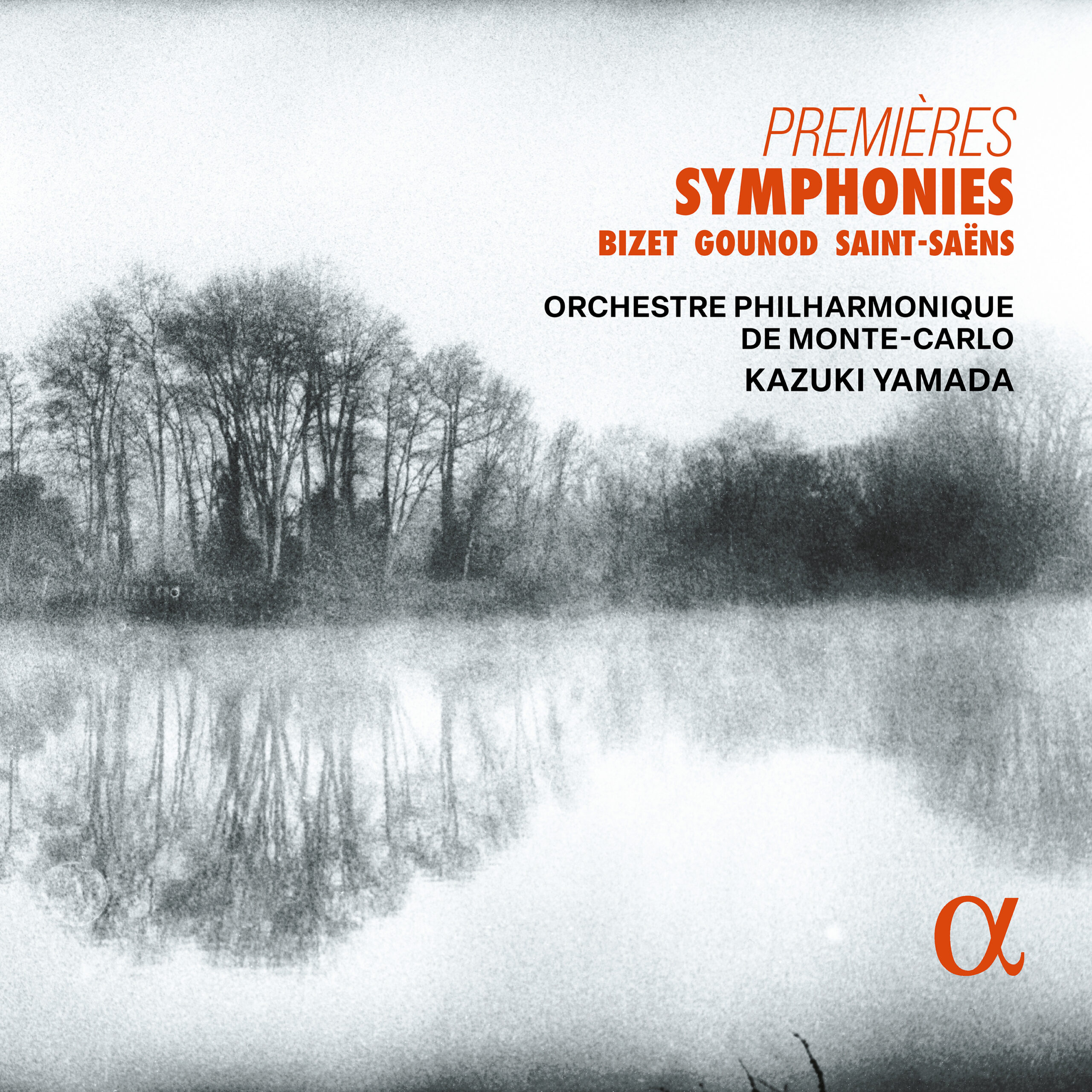
はじめての交響曲
〔ビゼー:交響曲ハ長調,グノー:交響曲第1番,サン=サーンス:交響曲イ長調〕
山田和樹指揮モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団
〈録音:2023年12月,2024年6月〉
[アルファ(D)NYCX10544(2枚組)]
【メーカー商品ページはこちら】
山田 和樹 Kazuki Yamada
1979年生まれ。東京藝術大学在学中にTOMATOフィルハーモニー管弦楽団(現横浜シンフォニエッタ)を結成して音楽監督を務めるなど、早くから積極的な指揮活動を展開する。2009年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝して以降はヨーロッパでも広く活動し、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団やバーミンガム市交響楽団で音楽監督を務める。2026年からはベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者兼芸術監督に就任することが決定している。
ネルソン・ゲルナーとのラヴェル/ピアノ協奏曲集
同じアルファ・レーベルからは、名手ネルソン・ゲルナーを独奏に迎えたラヴェルのピアノ協奏曲集が登場した。山田がスイス・ロマンド管弦楽団(2012年から18年まで首席客演指揮者を務めた)と、デニス・コジュヒン独奏で録音したラヴェル協奏曲集〈2017〉以来の再録音だ。「スイス・ロマンド管もフランス語圏のオーケストラですが、両手のほう(協奏曲ト長調)はよく演るんですよ。ところが、オーケストラにもヴィルトゥオーゾ的なものが散りばめられている『両手』に比べて、あまり演らない『左手』はオーケストレーションもぶ厚いし、細かく書き込まれているので大変なんです。今回の録音でも、細かいパッセージの動きなど、シビアなものが要求されました」というあたり、気心知れたモンテカルロ・フィルとの誠実な音楽づくりを、細部まで堪能したいところ。
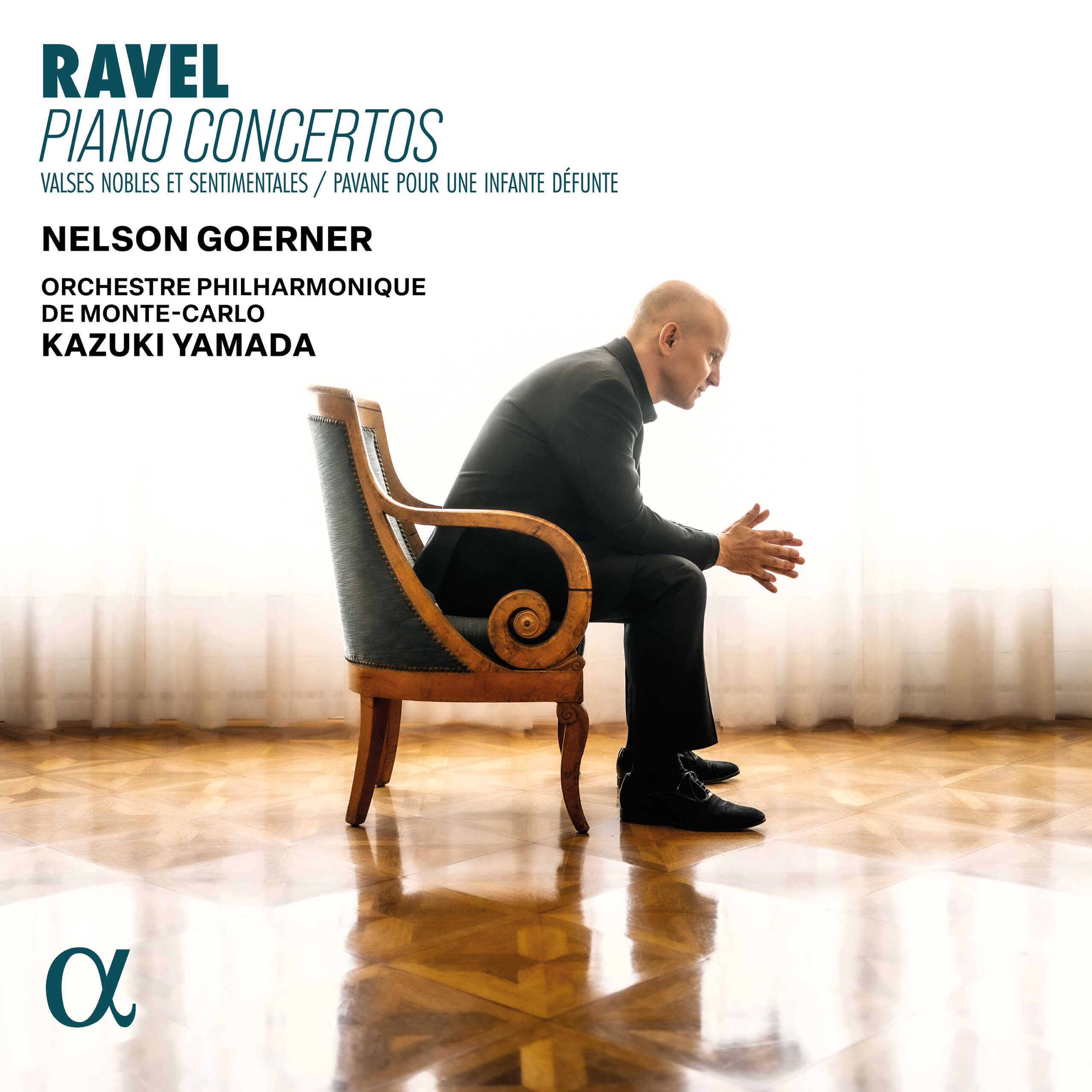
ラヴェル:ピアノ協奏曲集,高雅で感傷的なワルツ,パヴァーヌ
〔ピアノ協奏曲ト長調,高雅にして感傷的なワルツ(ピアノソロ),左手のためのピアノ協奏曲,亡き王女のためのパヴァーヌ(ピアノソロ)〕
ネルソン・ゲルナー(p)山田和樹指揮モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団
〈録音:2025年3月~4月〉
[アルファ(D)NYCX10548]
【メーカー商品ページはこちら】

ネルソン・ゲルナー Nelson Goerner
1969年生まれ。アルゼンチン出身で、1990年のジュネーヴ国際コンクールで優勝したことで一躍その名を世界に広めた。ヨーロッパや南米、さらには韓国・日本でも数多くの演奏会に出演して高い評価を受けてきた。NIFCレーベルでいくつかのアルバムを制作して後、現在はアルファ・レーベル専属として数多くのディスクを世に送り出している。そのレパートリーは広大で、ベートーヴェンからショパン、リスト、ブラームス、ドビュッシーからブゾーニやアルベニスにまで及ぶ。
サン=サーンスの埋もれたオペラ《祖先》を初録音!
山田&モンテカルロ・フィルの録音ではもうひとつ、サン=サーンスの埋もれていた大作オペラの発掘初録音が素晴らしい。これは、フランスのBru Zaneレーベル(フランス・ロマン派音楽センター)が制作したもの。同レーベルは、埋もれたグランド・オペラからオペラ・コミック、オペレッタなど40作以上を、資料的価値も非常に高い充実したブックレットとともに発売している。山田はこのレーベルにサン=サーンス最後のオペラ《デジャニール》を録音〈2022〉。1911年の世界初演がモナコだった縁もあって、モンテカルロ・フィルとのセッション録音が行なわれたが、壮麗かつ力感あふれる演奏が素晴らしかった。
それに続く第2弾としてサン=サーンスのオペラ《祖先》世界初録音が誕生したのは、いよいよ好奇心もマニア心もそそられるところだが、こちらも優れた演奏だ。「そもそも、今の時代にサン=サーンスの『世界初録音』が出来る機会なんて、そうそうないわけですよ(笑)。今回の《祖先》は、録音は無かったものの2000年以降にも演奏記録はあるんです。ところが、前に世界初録音をした《デジャニール》に関しては、本当に何にも記録が無かったから大変でした(笑)。まず3か月かけて自分のために台本の翻訳を作ったんですが、題材が神話の世界なので、音楽とテキスト、時代的な背景など夏休みを潰して勉強しないと分からなかった。それが非常に勉強になりましたね」
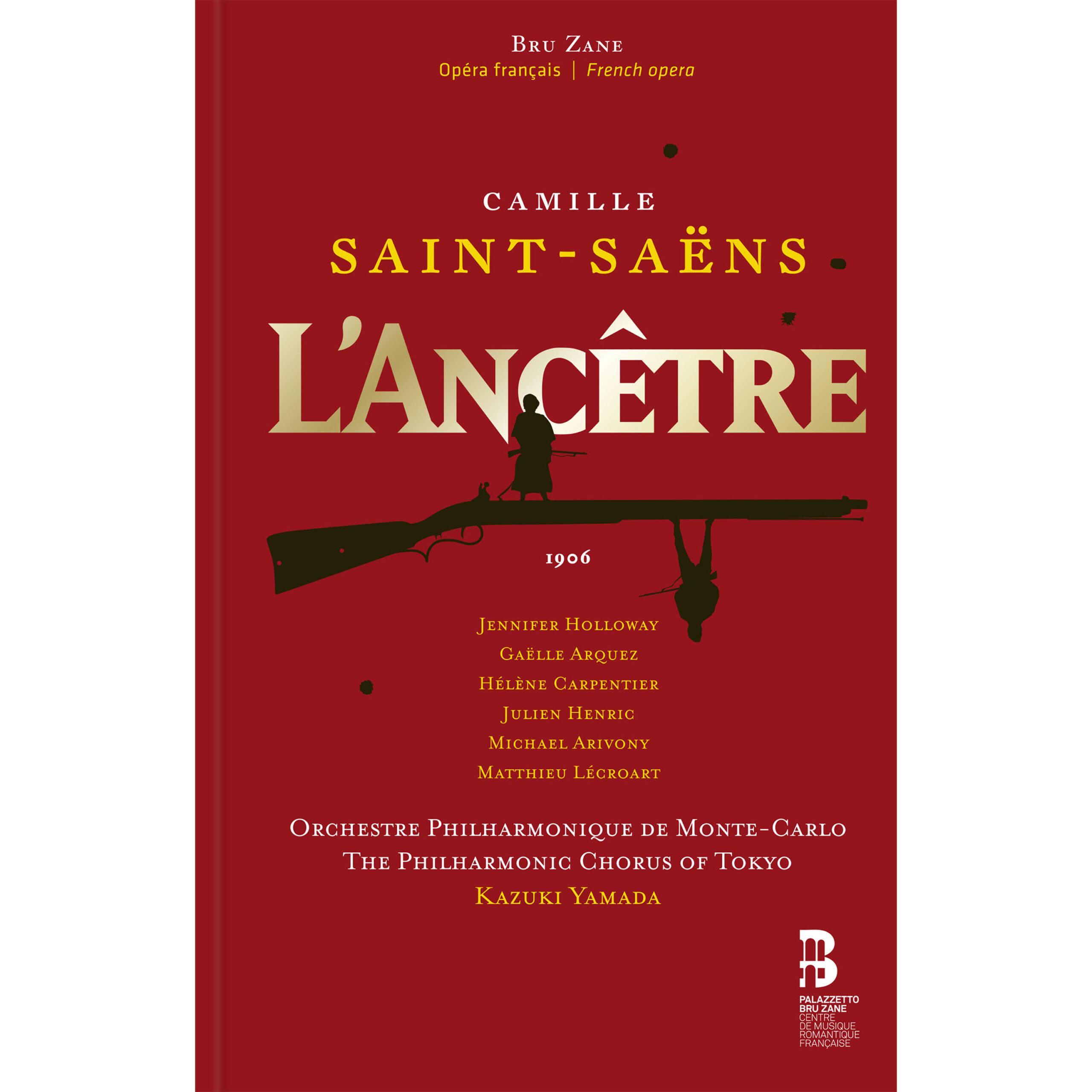
サン=サーンス:歌劇《祖先》全2幕
山田和樹指揮モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団,東京混声合唱団,ジェニファー・ホロウェイ(S)ガエル・アルケス(Ms)エレーヌ・カルパンティエ(S)ジュリアン・アンリック(T)ミシェル・アリヴォニ(Br)マチュー・レクロアル(B-Br)大沢結衣(S)
〈録音:2024年10月〉
[Bru Zane(D)BZ1061(2枚組)]
【メーカー商品ページはこちら】
今回の《祖先》も1906年に(作曲家のお気に入りでもあった)モンテカルロ歌劇場で世界初演され、それきり埋もれていたサン=サーンス晩年の大作オペラ。コルシカ島で物語が展開される本作は、作曲家が初めて現代を舞台にした作品であり、同時代のプッチーニやマスカーニとの対抗意識など、従来のサン=サーンス観を変えるようなインパクトも持っている。「サン=サーンスは、あの時代にあっても伝統的なやりかたでオペラや交響曲を書いていた人ですが、それでも後期にはけっこう挑戦的なこともしていて、今回も『これは譜面通りに演っていいのかな?』と疑問に思うところがたくさんありました」と山田も語るように、この蘇演録音はサン=サーンスの晩年、その音楽が同時代の潮流と大きく離れながらも独自の道を探っていた様子まで明らかにされる、貴重なものだ。
「僕は海外に行って衝撃を受けたのは、劇場のオーケストラ・ピットの音響の良さなんです。モナコもそうなんですが、パリのシャンゼリゼ劇場のピットに入った時、変な話ですが舞台上よりピットの方が音が良くてびっくりした(笑)。ゴージャスではないけど音がちゃんと溶けて響くから、作曲家はこれを想定して書いたのか、と納得しました」。モンテカルロ・フィルも、オペラ公演のピットにも入るオーケストラだ。「劇場ならではの音響」を良く知る楽団として、その持ち味を磨いてきたわけだが、「モンテカルロのオーケストラは、100%フランスというよりは、歌い回しがつやつやな感じとか、ちょっとイタリア的なところが入っている」というのも面白いところ。
《祖先》の録音に東京混声合唱団が参加!
今回の《祖先》の録音では、山田が音楽監督兼理事長を務めている、東京混声合唱団が参加しているのも、特筆すべき成果だ。「今回は、昨年秋に東混のヨーロッパ・ツアーを行なった[トゥールズ・キャピトル国立管やルクセンブルク・フィルとフォーレの《レクイエム》などを共演したほか、フランスなど各地で教会コンサートを開催]とき、モナコでも演奏できることになったので、《祖先》録音に参加したんです。東混のことをあまり知らない関係者ははじめ、フランス語の心配をしていたんですが、フランスに来て特訓も受けた結果、演奏は『フランス人以上に出来ている』とお褒めの言葉もいただくことができました。東混のみんなは〈お世辞だろう〉と本気にしてませんでしたが、お世辞を滅多に言わない人たちから褒められたんですから!(笑)」
※東京混声合唱団の参加レポートはこちら

自身は「もともとレコーディングはあまり得意なほうではないんです。いつも気が引き締まります」と語る山田だが、着々と録音を重ねることで「好き嫌いに関わらず、これだけの録音経験を重ねてこなかったら、ライヴが今のような演奏にはなっていなかったと思います」と言う。2023年から首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーに就任し、2024年からは音楽監督を務めるバーミンガム市響とは、「ウォルトンなどイギリスの作曲家を録音できないかと話しているところです。今度就任するベルリン・ドイツ響とも、まだ何も決まっていませんが録音の相談をしています」とのこと。山田和樹の止まらぬ飛躍、レコーディングにも着々と刻まれるその実りを、余さず追いかけていきたいと思う。









