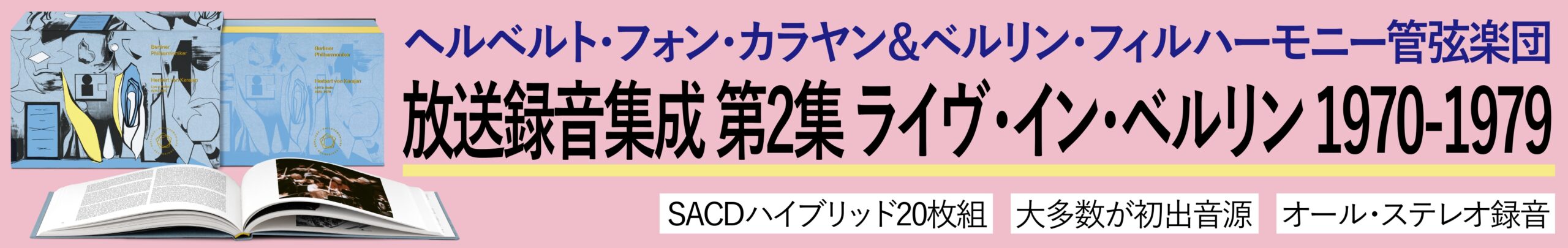Interview & Text=宮本 明(音楽ライター)
写真:各務あゆみ
取材協力:ファインアーツミュージック
ハーバード大学とジュリアード音楽院を卒業。著作家・起業家としても活躍し、メディア出演も多いこの人の演奏をもっとよく聴いてみたいと望んでいた人は、『レコード芸術ONLINE』の読者にも多いのでは。ヴァイオリニスト廣津留すみれがソロ・デビュー・アルバム『11 STORIES(イレブン・ストーリーズ)』をリリースした。
優しくソフトに語りかけてくるのがクライスラーの魅力
アルバム『11 STORIES』は、彼女が幼い頃から弾いてきた11の名曲をたどる物語。いわば名刺がわりの1枚だ。たとえば、幼い頃に愛聴していたクライスラーの《ウィーン小行進曲》や、小学校の文化祭で初めて弾いた、やはりクライスラーの《前奏曲とアレグロ》などなど。全11曲中の7曲を、クライスラーの作曲または編曲作品が占める。
「クライスラーは、最初は“弾く”より“聴く”のほうが多かったと思います。家には父のCDがたくさんあって、私は自分の好きなCDに、犬のぷっくりシールを貼ってたんですね。2歳からヴァイオリンを習っていたので、マーキングもやっぱりヴァイオリン曲が多く、なかでもクライスラーが好きでした。メロディラインがシンプルに美しいですし、絶対こう来ると思った進行のところに、ちょっと予想と違うおしゃれな和音が入っていたり。優しい感じで、ソフトに語りかけてくるのもクライスラーの魅力ですね」

11 STORIES
〔クライスラー:ウィーン小行進曲,前奏曲とアレグロ,アイルランド民謡(クライスラー編):ロンドンデリーの歌,バルトーク:ルーマニア民俗舞曲,クライスラー:美しきロスマリン,モーツァルト(クライスラー編):ハフナー・セレナーデより〈ロンド〉,クライスラー:シンコペーション,ドヴォルザーク(クライスラー編):我が母の教え給いし歌,イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番《バラード》,ラフマニノフ(クライスラー編):ピアノ協奏曲第2番第2楽章より〈祈り〉,サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン 全11曲〕
廣津留すみれ(vn)河野紘子(p)
〈録音:2025年4月〉
[HATCH MUSIC(D)HATCHM001]
辰巳明子氏に師事していた高校生のとき、全米ツアーに招かれ演奏。そこで弾いたのが、バルトークの《ルーマニア民俗舞曲》、イザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番《バラード》、そしてサラサーテの《ツィゴイネルワイゼン》だった。
「2週間ぐらいのツアーで、4州をまわって、最後はカーネギーホールでした。お客さんがすごく盛り上がってくれて。国境なんて全然関係なく、いいと感じるものは同じなんだなと実感しました」
その訪米中にキャンパスを見学したのがきっかけでハーバードに留学することになる。いうまでもなく、ハーバードに音楽の実技の授業はほとんどない。学業と音楽との両立は彼女が望んだものだったが、ボストン留学中はヴァイオリンのレッスンもあまり受けられなかったという。しかし、その環境が、ヨーヨー・マ率いるシルクロード・アンサンブルとの出会いという大きな転機につながった。
「大学に専門的にヴァイオリンを勉強した人はあまりいなかったので、ヴァイオリンが必要なイベントがあると、全部私が頼まれていました。あるレセプションでモンティの《チャールダーシュ》などを弾いた数日後、演奏を聴いたという女性からメールが届きました。『ヨーヨー・マと弾きませんか?』と。シルクロード・アンサンブルのディレクターだったのです」
自身もハーバードの出身者であるヨーヨー・マが世界の民族楽器の名手を集めて結成したシルクロード・アンサンブル。ヨーヨー・マとの共演は彼女の価値観に大きな改革をもたらした。
「それまでの私は、難しい曲を上手く弾くことが目標だったのですが、そうじゃないんだということを、ヨーヨー・マさんとの共演で学びました。誰もが知っているシンプルな曲でも、彼の演奏からは何かが伝わってきます。一音一音に込められたストーリーを伝えるのが本当に上手なんですね。どうやったらそれが自分にもできるのかをすごく考えるようになりました。弾き方が変わったなと思います」

廣津留すみれ(ひろつる・すみれ)
大分市出身のヴァイオリニスト。12歳で九州交響楽団と共演、高校在学中にニューヨーク・カーネギーホールにてソロデビュー。ハーバード大学(学士課程)卒業、ジュリアード音楽院(修士課程)修了後、ニューヨークで音楽コンサルティング会社を起業。現在は日本を拠点に、世界各地で演奏活動を行なう。国際教養大学特任准教授・成蹊大学客員准教授。中央教育審議会委員。大分市教育委員。『超・独学術』(KADOKAWA)、『イツァーク ヴァイオリンを愛した少年』(音楽之友社)など著書・訳書も多数。
公式サイトはこちら
シルクロード・アンサンブルやジュリアードの経験から
演奏に対する姿勢をしっかり考えられるように
シルクロード・アンサンブルというグループの空気そのものも新鮮だった。
「リハーサルがとても大切。ものすごく話をしながらのリハーサルでした。練習というのは、先生の言ったとおりに弾くものというイメージだったのですが、それとはまったく違って。『こうしたほうがいいんじゃないか』というサジェスチョンが、全員からどんどん出てくる。そのときヨーヨー・マはだいたい、ニコニコしながら黙って聞いてます(笑)」
つまり演奏の意図を言語化すること。ハーバード卒業後、音楽だけをやる環境に浸ってみたいと進んだジュリアード音楽院も、それと似た環境だったようだ。
「ジュリアードでは、音楽に没頭することができました。でもとにかく先生が質問攻めなんですよ。『ここはどうやって弾きたいの?』『なぜ、そう弾いているの?』『そこはアンサンブルで話し合ったの?』……。全部考えていたはずなのに、1か所でも考えていなかったところがあると、そこを見事に突っ込まれる。お見通しなんですね(笑)。
ただ、否定はしないんです。説明は求めても、好きなように弾きなさいというスタンスなので。おかげですごく真剣に考えるようになって、頭が相当鍛えられました。自分の演奏に対する姿勢もしっかり考えられるようになったと思います」
やや意外だったのだが、ジュリアードでは古楽と出会う機会も得たそう。古楽科に鈴木雅明が教えに来ていたのだ。
「鈴木雅明さんにはニューヨークで初めてお目にかかりました。『バロックもやっておいたほうがいいよ』と猛烈に説得されて(笑)、副科でバロック・ヴァイオリンを取ったのです。雅明さんが指揮していた“ジュリアード415”というアンサンブル(ジュリアード音楽院古楽オーケストラ)にも参加して、バッハ・コレギウム・ジャパンとのジョイント・ツアーや、ライプツィヒのバッハ・フェスティバルでメンデルスゾーン《エリア》を演奏しました。最初はバロック・ピッチ(A=415Hz)に慣れなくて、雅明さんにお伝えしたら、『それは慣れと時間の問題だから』と。たしかに時間が解決してくれましたが、何度かご一緒したBCJの《第九》はA=430Hzなので、いまだに混乱します(笑)。
今回のアルバムのピアニスト河野紘子さんも鈴木優人さんが紹介してくださいました。コロナ禍で帰国した当初、日本の音楽家の方々とはまだ交流が少ない状況でした。知っている日本の音楽家が雅明さんと優人さんしかいなかったので、大変ご親切にいろいろな方を紹介していただき、お二人には感謝しています」

音はライヴで消えていくものなので
何か形を残せるのはすごくうれしい
CDは、自身が立ち上げた「Hatch Music」からのリリース(「Hatch」は卵が孵化すること)。ニューヨークでは音楽コンサルタント会社も起業していた彼女。アメリカではフィジカルなCDはもはやかなり劣勢だが、日本ではまだ可能性があるのではないかと見ている。
「日本はサイン会という文化もありますしね。配信で聴くけれど、CDも手元に置いておきたいという人も多いのではないでしょうか。私も紙の本が好きで、なかなか電子書籍に移行できないタイプなんですけど(笑)。そういう良さって、たぶんあると思いますし、とくに音はライヴで消えていくものなので、何か形を残せるのはすごくうれしいなと、今回アルバムを作りながら考えていました」
幼い日のクライスラーから、シルクロード・アンサンブルでの経験、そしてジュリアードで培った確かな思索。胸に刻まれた旋律が成熟した響きとなって結晶した「11の物語」。ヴァイオリニスト廣津留すみれの足跡をたどるアルバムが、次の物語の始まりを予感させる。