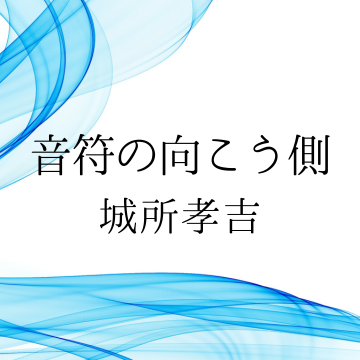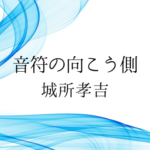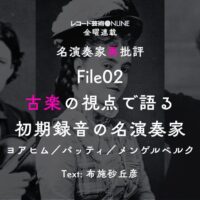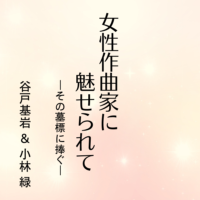音楽評論家・城所孝吉氏の連載、第5回は、ドイツ・リートに関する論考です。歌曲は器楽曲と違って常に歌詞が介在し、詩人の手による詩と、それに付曲した作曲家の音楽の「ダブル」解釈が必要となる。そこには、とてつもない深い世界が広がっています。
詩人と作曲家への「ダブル・アクセス」
これまで当連載では、基本的に器楽曲をどう解釈するかの話をしてきた。しかし声楽曲では「読み」をめぐる状況はやや違っている。なぜなら、それには歌詞があるからだ。作曲家は、歌曲やオペラ、合唱曲等を書く場合、まずテキストから発想し、それをどう音にするかを考える。器楽曲では、純粋に自分が考えたことを音楽にするが、声楽曲ではまず原詩を読み込まなければならない。演奏家が作品を解釈する前に、作曲家がテキストを解釈するという二重のレヴェルが存在するのである。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。