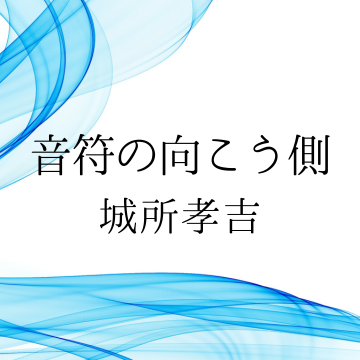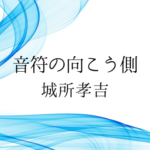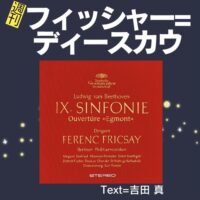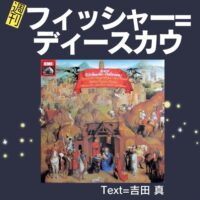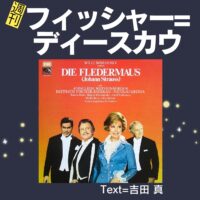音楽評論家・城所孝吉氏の連載、第11回は、演奏者と聴衆(観客)がコンサートで「同一の体験をすること」について考察します。ライヴで演奏を体験する時、それがどんなに複雑な感情を表現していても、ホール全体が同じ内容を共有した思いになることがあります。それは当たり前のようでいて、実は奇跡的なことなのかもしれません。
演奏家と観客が「同一の体験をする」ということ
連載第10回では、指揮者とオーケストラの間の意思疎通が、棒や言葉だけでなく、テレパシーのような(理性で説明できない)ものによっているのではないか、という話をした。しかしこのことは、振る人と弾く人の間のコミュニケーションにとどまらない。なぜなら、演奏を最終的に体験するのは、聴衆だからである。優れたコンサートを聴くと、聴き手は指揮者とオーケストラの音楽行為を、彼らとまったく同じように体験している、という実感を持つことがある。演奏者と観客が一体化し、「心がひとつになった」ことを確信する瞬間が、確かに存在するのである。
そんな体験で頭に思い浮かぶのは2000年、ベルリン国立歌劇場で観たA.スカルラッティ《グリゼルダ》の公演である(ルネ・ヤーコプス指揮)。このオペラは、シチリアの王グァルティエーロが、身分の低い妻グリゼルダの貞操と誠を試す、という筋書きで、ヒロインは数々の試練に立たされる。身分を剥奪され、宮廷を追われて森に置き去りにされた彼女は、運命を嘆く一方で、横恋慕する貴族オットーネを頑として受け付けない。冷たくされたオットーネは、彼女の赤ん坊を奪って逃げるが、ひとり残されたグリゼルダは、アリア〈運命よ、終わるのでしょうか〉を歌う(第2幕10場)。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。