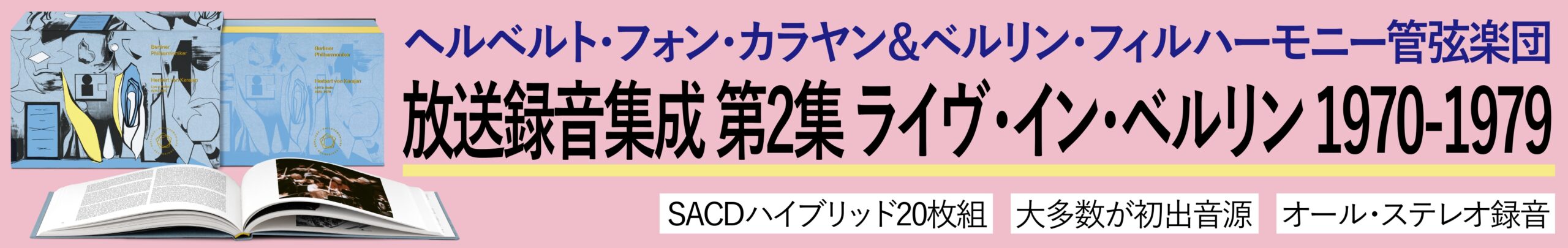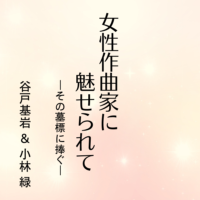なにごとかが映画館とホールのあいだを行き来する
―――昔、映画『砂の女』を作った時、前衛的な音楽を書いた。音楽も、とってもよかったって言われたのに『砂の女』をもとにして《地平線のドーリア》(1967)という作品を書いたら「難しい」って言われる(武満徹)
映画や美術展を見逃すことが実に多い。演奏会ならば簡単なのだ。まず日程を調べて、予定が空いていればすぐにチケットを手配する、空いてなければすっぱりサヨウナラ。ところが映画や美術展は、2週間とか2か月とか、ともかく一定期間やっている。よし、行ける時にぜひ……と思っていると、毎度のごとく、会期を逃すわけである。うっかり忘れてしまうのは、音楽ほどに興味がないせいなのかもしれないが、少なくとも自覚的には「どうしても見たい」映画や美術展なのだ。対策として考えられるのは、演奏会のように、最初からピンポイントでこの日、この時間に行く! と決めて手帖に書いてしまうことくらいだろうか。実際、最近はそうしているのだが、締め切り間際の原稿があったり、飲み会のお誘いがあったりすると、ついそちらを優先してしまう。やはり、頭の隅に「まだやってるから」「まだ行けるから」という気持ちがあるので、緊張感に欠けるのだろう。いったいどうしたらよいのだろうか。
■
映画と音楽の関係は、批評や研究における実に魅力的な主題だ。
ただし、以前は大変だった。映画音楽で実際に使われたスコアを見るのはまず無理だから、論文などに旋律を引用する際にも、がっつり「聴音」しなければいけない(映画音楽で修士論文を書くという学生にはこれをさんざんやらせたものだ)。そもそもそれ以前に、ヴィデオがない場合には、映画館で観たものを逐一覚えておかないといけないわけで、これはどうにも限界がある。おそらくはこんな単純な理由から、映画と音楽にかんする研究は思いのほか進んでいなかったのだと思う。
しかし状況はここ十年ほどで急速に変わりつつある。DVDなどのソフトが充実してきたのはもちろん、「アマプラ」や「ネトフリ」などをフル活用すれば、今やかなりシブい映画でも自宅で観られたりする。さらにはYouTubeで全篇を見られてしまう映画も、意外なほどにたくさんある。
つまりは映画音楽研究のインフラがどんどん整いつつあるわけで、多分、これから刺激的な研究や批評が次々に出てくることだろう。
きわめて怠惰な映画好きであるわたしも、2年ほど前、武満徹が音楽を担当した映画をできるだけたくさん観ようと試みたことがある。これは、先のような状況の変化にくわえて、武満の後期の音楽様式を「映画音楽化」というタームで切り取ることができるのではないかと考えているからだ。
一般に、武満作品の様式変遷は、メシアンあたりを手掛かりに自らの音楽を探る初期を経て、60年代に入ると同時代のヨーロッパ前衛と呼応した鋭い響きに到達、その後、邦楽器の使用を含めて前衛の延長線上でさまざまな語法を開拓するも、80年代に近づくと徐々に「保守化」がはじまり、晩年に向けて調性的な音楽へと回帰する中でこの世を去った……といった類の図式で語られることが多い。 この「保守化」を、1980年代の、いわゆる新ロマン主義の枠組みで考えてもいいのだろうが、武満の場合には映画音楽の語法へと自らの芸術音楽の様式を寄せていった、と表現する方が適切ではないかと思うのである。生涯に百本以上の映画音楽を担当した武満にとって、映画音楽と演奏会用音楽は音楽活動の両輪であり、これらは相互に、深く関係しているはずなのだ。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。