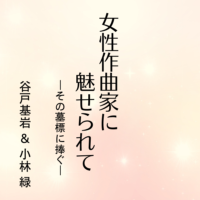真の作者が機械を操作する
「抜き打ち訓練は、通常の訓練の3、4倍のエネルギーがかかりますから」
(日本地震学会広報紙『なゐふる』より)
7月の頭は、灼熱の日本を脱出して、イギリスの北部、ハダースフィールドという小さな街の大学で行なわれた国際会議に出席していた。
会議2日目の午後。メキシコ人の学者が発表をしている途中、突然に警報ベルがけたたましく鳴り響いた。すわ一大事と、参加者全員がスマホだけ手にして、あたふたと建物の外へ。少したって明らかになったのは、これが避難訓練だったこと。ほう。
たまたま隣にいた、アリシアというファーストネームのイタリア人学者に「これで今日のスケジュールが押しちゃうね。そもそも日本では避難訓練って、ちゃんと事前に日時のアナウンスがあるものだけど」とぽろりと言ったら、「え? それじゃ意味ないじゃない」と笑われてしまった。
なるほど、言われてみれば、日本の一般的な「避難訓練」というのは、かなり妙な儀式かもしれない。ともかくこの社会では予定通り、時刻通り、段取りばっちり、混乱なく、というのが何よりも(場合によっては「突然の災害にすばやく対処する訓練」という本義よりも)大事なのだ。なんだかうんざりするような話ではあるのだが、無理やりポジティブに考えるならば、新幹線が東京から福岡まで1分の遅れもなく走ったりするのは、まちがいなく、こんな性向のおかげではあるだろう。そして多分、日本の誇る「技術力」というやつも、この延長線上に位置している。
■
電子音響音楽というジャンルに、一定の興味を持っている。ものすごく好きというのとはちょっと違う。音楽創作の過程を考えるうえで、きわめて面白いモデルだから、興味があるのだ。以下、少しばかり手前から説明してみたい。
どこかの国の作曲家が、百年も二百年も前に書いた楽譜を、演奏者があれこれ解釈して演奏する。これが「クラシック音楽」というジャンルの中核において、日々起こっている事態だ。もちろん百年前ではなく、千年前だったり、三日前だったりもするわけだが、まあ、事情はさして変わらない。
作曲者が生きている場合には、演奏解釈についてあれこれと指示を出すこともある。現代音楽、それもとりわけ不確定性音楽において、そうした指示が決定的に重要であることは、かつて自著のなかで論じた(「不確定性音楽をめぐるコミュニケーション」――『音楽学への招待(春秋社)』所収)。
ロックやヒップホップやジャズの場合、「楽譜を解釈する」というプロセスはほとんど存在しない(あるいは、あってもきわめて少ないスペースに留まっている)。多くの場合、こうした音楽は「自作自演」だし、他人の作品をカバーする場合においても、参照されるのはその音源であり、楽譜ではない場合がほとんどだ。
さて、クラシック音楽の制作過程を単純化すると、以下のような、見慣れた図式があらわれる。
①作曲家→②楽譜→③演奏者→④音響→⑤聴き手
作曲家、演奏者、聴き手という3種類の人間のあいだに、「楽譜」と「音響」というモノが挟まっているわけだが、このうち最初の「①作曲家→②楽譜」という段階で起こっていることは、以下のように細分化できるのではないか。
1a:作曲家が特定のイメージ、アイディアを抱く
1b:作曲家がそのイメージ・アイディアを楽譜の上に定着させる
もちろんこの2つは、必ずしも段階的・解離的に生じるわけではなく、場合によってはぐずぐずと一緒になっていたりもするだろう。それでも理念的にいえば、この二つは少々異なる作業である。
重要なのは、例えば音楽大学のような場所で行なわれる作曲の訓練というのが、基本的には1bの訓練であることだ。1aに属する、いわば神秘の秘訣――どうすればよいアイディアやインスピレーションがひらめくのか――を教えたり、教わったりすることは難しい。しかし、どのように一定のアイディアを正確に、過不足なく、効率的に楽譜上に定着させるのか、という技術ならば、段階的に習得することが可能だ。
一方で、初期の電子音響音楽の場合には、先の図式は以下のように変化する。
①作曲家→②テープ/音響→③聴き手
先には3種だった人間が、ここでは2種に減っている。しかし、先と同じように、この最初の部分を以下のように細分化してみると、もう1種、別の人間が隠れていることが明らかになる。
1a:作曲家が特定のイメージ・アイディアを抱く
1b:技師がそれをテクノロジー機器を用いて音響化する
ここでは1bは、主に技師という新しい種類の人間によって担われている。もちろん、時代が下ってくると、電子音響音楽の制作は小さなラップトップでも可能になるから、その場合には作曲家が技師を兼ねることもある。しかし、少なくとも初期はそれなりに大型の、特別な操作が必要な機器を操作しなければならなかったから、技師という存在は不可欠だった。
大事なのは、先に見たように、音楽大学のような場所で行なわれる作曲の教育が、この1bの範囲を扱うものであることだ。アイディアやイメージも大切だが、しかし実は、この部分は作曲という行為のかなり重要な本体(body)ともいえるのである。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。