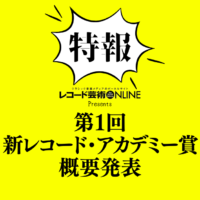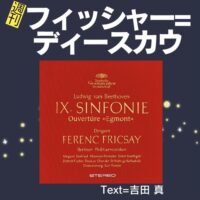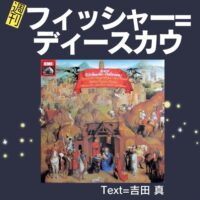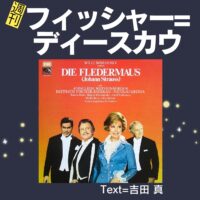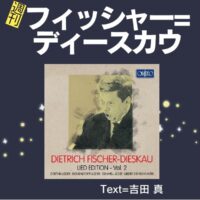深い赤がエロティックな質を帯びる
――WHOは、生活の質(Quality of Life)を、文化や価値観の文脈、また個人の目標、期待、基準、関心との関連の中で、個人が人生における自分の立場を認識することと定義しています。
(World Health Organization[WHO] サイトより)
今年の1月。ほとんど突発的に、イタリア製の、少々値の張るダウンジャケットを買ってしまった。
それ以来、寒い日にはたいていこれを着る。上質のダウンとフェザーを使っているだけあって大変に暖かいのはもちろんだが、何よりいいのは、その軽やかな質感である。ふわり、しっとりしていて、身につけるのが心地よい。触っているだけで不思議な「快」を感じるのだ。
恥ずかしながら、服の質感というものを意識するようになったのは、そんなに昔のことではない。あれは4、5年前、勤務先の音楽大学の式典だった。教員がずらりとひな壇に並んだ際に、わたしの前に位置していた、ひとりのピアノ科の教授のスーツに目が釘付けになったのである。遠くからはよく分からなかったが、至近距離で見ると生地に滑らかな光沢があり、なんともいえず質感が良い。自分が着ているわけでもないのに、思わずうっとりしてしまった(あのスーツは一体、いくらくらいするのだろう?)。
それまでのわたしは、服はデザインと機能さえよければ十分だと考えていた――もちろんユニクロにも無印良品にも、素敵なデザインや、丈夫で暖かい服はたくさんある。ところが、この時から「質感」というものが、どうにも気になりだしたのだった。たぶん今回の衝動買いは、その数年越しの帰結のひとつなのだろう。
■
デザイン(「カッコいい」)や機能(「丈夫で暖かい」)と比べた時、質感、というのは実にあやふやな言葉である。服の場合、きめ細かく柔らかい、といえばちょっとだけ似てはいるけれども、それだけでは良い「質感」の十分条件ではない。
服のデザインが、主に外に向けてカッコよさをアピールするものだとすれば、その機能は、ある程度、数値化が可能な指標のもとに成り立っている。これらに対して質感は、むしろ着ている人間の内部に働きかけるタイプの快といってよいだろう(もちろん、先の例のように、間近で見た時にその快さを共有することもある)。
昨今、よく目にするQOL(Quality of Life)という語は、単に他人と比べて何歳だか長生きすることが重要なのではなく、自分自身がこの世界のなかにきちんと居場所を確保し、「楽しく」「快く」生きることにこそもっとも大きな意味があるのだ、という考え方にかかわるものだが、まさにだからこそ、これは機能ではなく「質=Quality」の問題なのだ。
内側に向いているだけに、質は「自己満足」とも緊密にリンクしている(QOLは、ある意味では自己満足の度合ともいえるのではなかろうか)。ゆえに良い質感は思い込み、あるいはプラシーボ効果によっても醸成される。服の例でいえば、値段が高いから上質なはず、という思い込みが、着ている人をしていい気分にさせるわけだ。愚かなようでもあるが、しかし、本人がそれで上機嫌になるのであればけっして悪いことではないだろう。
実際、世の中には、ストラディヴァリウスはいい音がする、と単純に考えている人がたくさん存在する。しかし、おそらくストラドの良さは、機能、すなわち客観的な音の良さとは少々異なる部分にあるような気がする。その、歴史を孕んだ重層的な質感が人間に対して働きかけ、弾き手を心地よい自己暗示にかける点にこそ、この楽器の最大のマジックがあるのではなかろうか。ストラディヴァリウスの本質がプラシーボ効果にある、などというと怒り出す人がいるかもしれないけれども、しかしそのプラシーボ効果は時として数億円の代償を払わなければ得られない、きわめて特別なプラシーボなのだ。わたしのダウンジャケットとは訳がちがう。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。