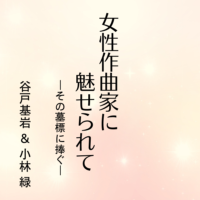イヌイットの喉歌を朝ドラのヒロインが学ぶ
それほど才能のない詩人たちは、偉大な先達を理想化する。その一方、有能な想像力を持つ者たちは、自力で先行者を押しのけて、自分の場所を確保する。
ハロルド・ブルーム『影響の不安』(新潮社)
自分の書いている文章や意見が、実はかつてどこかで読んだ、誰かのものであったら……。文章を書く人間であれば、誰もがそんな不安を常に抱えているのではなかろうか。他人とまったく異なる意見や文体を提出することなど、土台不可能ではあるのだが、しかし無意識のうちに他人とそっくりの文章を書いていたら。
ハロルド・ブルームは『影響の不安』(新潮社)の中で、作家や詩人は常に先人の影におびえざるを得ないことを論じたうえで、ゆえにすぐれた書き手は常に、積極的・詩的な「誤読」を図ることによって先人を自らの影響下においてしまうのだと述べる(なんとダイナミックな逆転だろう)。ブルームの議論は抜群に面白いのだが、わたしの書く文章は詩や文学とは異なるから、そんなに派手な誤読を仕掛けるわけにもいかない。
実は、ずっと気になっていることがある。拙著『音楽学への招待』(春秋社)のまえがきのなかに、「少なくともその役を買って出ようと考える程度には、筆者はこの学問に恩義を感じているのである」という文章があるのだが、さりげない一節ながらも、これは多分、どこかで読んだ表現なのだ。当時、思い当たるフシをかたっぱしから探してはみたもののどうにも見つからず、きっと気のせいだと半ば自分を騙しながら、えいやっと使ってしまった。
全く同じ表現が他の本にあったとして、例えばこれが吉田秀和の文章であれば、さして問題にならない気もする。ああ、ヌマノは秀和ファンだったのか、思わず真似してしまったのだろうな……という程度で終わるのではなかろうか。しかし、これが駆け出しの書き手の文章であった場合、かなり感じがワルい。「若い人の文章を無断でパクった、権力的な簒奪者」として糾弾される可能性は十分にあろう。
もっとも、やっていることは同じでも、吉田秀和と「若い人」で罪状が異なるのも、考えてみれば不思議な話ではある。
■
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。