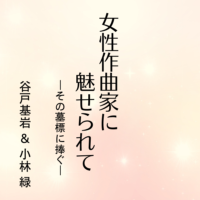打楽器奏者が鎌を研ぐ
先般の選挙では「日本人ファースト」なる不思議な文言が話題になった。シニカルな友人によれば、この語がこれだけ人口に膾炙したことは、英語における「名詞+形容詞」という表現を世に知らしめた点において、少なからぬ意義があったという。なるほど、たしかにこれを文法的に説明するのは決して簡単ではない(ちなみに、名詞+副詞と考えることも可能だ。たとえば元が「Put 日本人 first」という表現だと想定した場合)。きっと英語の時間にはよい教材になるだろう。
考えてみれば、この「日本人ファースト」の原型であろう「America First」を唱えたドナルド氏の、もうひとつのパンチライン「Make America Great Again!」も、英語の勉強に便利なフレーズだ。SVOCのSが省略された形。この第5文型は、最初の内はなかなか厄介だから、中学生のあなた――『レコ芸』読者に中学生はどのくらいいるのだろう?――は、この文章を丸ごと暗記しておくと、定期テストで高得点が狙えるかもしれない。メイク・アメリカ・グレート・アゲイン!
さて、これらから得られる教訓は、物事には必ず両面があるということだろう。たとえくだらない主張であったとしても、文法構造からはちゃんと学ぶべき事柄があったりもする。世の中はけっして捨てたものではない。
■
かつて「政治参加」といった名で呼ばれる作品群があった。
例えば手元にある松平頼暁『現代音楽のパッサージュ』(青土社)を開いてみると、第14章は「政治への発言」と題されており、アイスラーに関する記述にはじまり、ルイジ・ノーノ、フレデリク・ジェフスキー、コーネリアス・カーデューらの作品、さらにはクリスチャン・ウルフ、高橋悠治、アンドリーセン、ヘンツェなどの例が論じられている。
「意識的な参加、それも批判者側からの参加」に焦点を合わせた、と松平が述べるとおり、これらはいずれも広義の「左翼」に属する作曲家である。彼らは抑圧的な国家、あるいはその基盤となっている資本主義社会を音楽によって批判したわけだが、おそらく21世紀の現在、状況はより錯綜した状況にある。
実際、この連載のなかでも、何度か政治にかかわる作品を取りあげてきたが、その様態は先の作曲家たちのケースとは微妙に異なっている。たとえばフリードリヒ・ハースの《in vain》(2000) は、オーストリアにおいて、イェルク・ハイダー率いるオーストリア自由党が議会第2党へと躍進を遂げたことを反映した作品だった。ハースは「克服されたと思われたものが再び戻ってくる」、すなわちナチスの時代が再び到来することに対する警告として、途中から照明がどんどん暗くなるというこの楽曲を作曲した。あるいはアレキサンダー・シューベルトの《Black Out BRD》(2017)。これは当時台頭しつつあった(そして、現在はさらに伸張を遂げている)ドイツの極右勢力に対抗して、ドイツ国歌をすべてクラスターの中に埋め込み、消してしまうというコンセプチュアルな楽曲だった。
この2例はいずれも、現状に対する不満や反発というよりも、未来に対する不安あるいは警告が中核になっている。今のうちになんとかしないと! という焦り。その意味では、かつての「政治参加作品」より、さらに緊張度の高い作品と言えるかもしれない。
もちろん、オーストリアやドイツと同じく、フランスやオランダ、そしてハンガリーやポーランドをはじめとするヨーロッパ諸国では、いずれも右翼的な主張を持つ政党が大きく支持を伸ばしている。国によって、あるいは政党によって主張の詳細は異なるけれども、彼らに共通するのは、外国人や移民に対する一種の不寛容だといって、さして間違いにはならないだろう。大事なのは、その意味では、トランプ政権下のアメリカ合衆国、そしてこの日本も似たような状況にあることだ。
とすれば、これからの「政治参加」作品は、どちら側の立場であれ、この問題をめぐるものになる予感がするのだ。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。