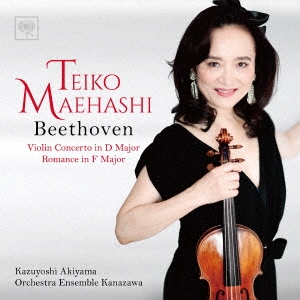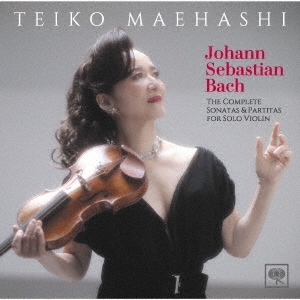インタビュー・文=芳岡正樹(音楽評論)
カメラ=堀田力丸
演奏活動60年を超えた希有なヴァイオリニスト、前橋汀子はここ数年、バッハとベートーヴェンに集中して取り組んでいる。前作のベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲が、彼女の師、シゲティを思わせる、細部を丹念に積み上げた意味深い名演奏だったことは記憶に新しいが、今回遂にベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集を完成した。これまた内容的にも技巧的にも素晴らしく、表現の深みにおいて比類を絶した驚くべき名演となった。また、シゲティ信奉者の筆者は、彼女の演奏に彼からの強い影響を感じずにはいられなかった。インタビューの場を与えられたので、この辺りも含めて伺ってみた。

ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ全集
〔第1番~第10番〕
前橋汀子(vn)ヴァハン・マルディロシアン(p)
〈録音:2023年6月,7月,2024年1月〉
[ソニークラシカル(D)SICC19081~4]SACDハイブリッド
ヴァイオリン・ソナタに至るまで
――まず、前橋さんとベートーヴェンとの出会いについてお聞かせいただけますか。
前橋 ベートーヴェンのソナタは、ヴァイオリンを学ぶ人は、あまり子供の時に弾かないと思います。ピアノがないと音楽として成り立たないし、ヴァイオリン・パートだけ弾いてもつまらない。私も10代の頃はソナタはほとんど弾きませんでした。むしろ協奏曲を含むテクニック的な曲が多かったと思います。私がソ連に留学していたとき(筆者注:17歳~20歳)もソナタはあまり弾かないというか、ほかの曲に時間を費やしていました。
――レコーディングは1986年に《春》と《クロイツェル》をなさっていて、その頃にはレパートリーに入っていたということですね。
前橋 1967年にシゲティの下で学ぶようになって、彼はベートーヴェンを得意としていたので、彼からベートーヴェンの奏法のエッセンスを盗もうなんて思っていましたが、そんな簡単なことではないことがよくわかりました。最初に彼から習ったのは第7番のソナタです。
――シゲティらしい劇的で剛毅な曲ですね。
前橋 でも、それは、たまたまコンクールの課題だったからなんです。すごく細かくいろいろなことを学んで。その後、第2番と第1番、ずいぶんいろいろレッスンしてもらいました。
――《クロイツェル》はシゲティとバルトークの演奏がすごく好きだと書かれていますよね。
前橋 そうですね。バルトークはすごいピアニストですけど、作曲家が見るベートーヴェンという気がするんですよね。テンポ感とか、何か特別な、独特な感じがしませんか。
前橋汀子(Teiko Maehashi)
日本を代表する国際的ヴァイオリニストとして、その優雅さと円熟味あふれる演奏で、多くの聴衆を魅了し続けている。これまでにベルリン・フィルを始めとする世界一流の多くのアーティストとの共演を重ねてきた。近年、小品を中心とした親しみやすいプログラムによるリサイタルを全国各地で展開。一方、バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティ―タ」、2014年からは弦楽四重奏の演奏会に取り組む。2004年日本芸術院賞。2011年春に紫綬褒章、2017年春に旭日小綬章を受章。使用楽器は1736年製作のデル・ジェス・グァルネリウス。オフィシャルサイト:https://teikomaehashi-violin.com/
デュオを組んだマルディロシアンのこと
――今回ピアニストは指揮もするマルディロシアンさんですね。
前橋 彼はアルメニア人なんです。最初に聴いたのはイヴリー・ギトリスのコンサートに行ったとき。ステージの雰囲気がとても良かったんですね。その後ひょんなことから一緒に弾く機会ができました。それ以来共演を重ねています。
――彼のピアノはタッチが美しいですし、落ち着いた雰囲気をもっていますね。
前橋 とても温かい人なんです。私もロシアのシステムで勉強して、彼はもちろん後の時代ですけれども、ロシア・ソヴィエトの伝統的な学校教育を受けている人なので、そうしたところにも通ずるものがあるんです。
――ロシアのピアノもネイガウスなどベートーヴェン演奏の素晴らしい伝統があって、リヒテルもベートーヴェンを得意としていました。
前橋 そうですね。私も色々な作曲家に出会って、色々な曲を弾いてきましたが、やはり行き着いたのはベートーヴェンとバッハ。とくにベートーヴェンはソナタに加えて弦楽四重奏もあるので、本当に特別な作曲家ですね。
弦楽四重奏に取り組んだことがベートーヴェンを見直すきっかけに
――前橋さんは弦楽四重奏を演奏されてから、ベートーヴェンのヴァイオリン作品に対する考え方が変わってきたと発言されていました。
前橋 ヴァイオリン・ソナタはベートーヴェンの比較的初期の作品なんですね。40歳過ぎくらいまでですから、体調も晩年のような苦しみはありませんし、絶望的な状況におかれていなかったときに書かれています。彼の晩年の生き様というか、心の叫びというのはヴァイオリンで弾ける曲としては弦楽四重奏の晩年の作品に凝縮されていると思います。ピアノ・ソナタはたくさんあって、生涯を辿れるような感じですが、ヴァイオリンに関しては、彼が晩年にヴァイオリン・ソナタを書いていたら、とは思うけれども、あんなに素晴らしい弦楽四重奏があるので、ベートーヴェンとしては弦楽器で自分の気持ちを表現したかったのかなと思います。ピアノとヴァイオリンでは全然違いますからね。
――弦楽四重奏曲第16番は、1曲だけ飛び地のように生まれていますね
前橋 ゆっくりした第3楽章は、齋藤秀雄先生が一番お好きだった曲なんですよ。あれを最後に聴きたい、ということをおっしゃっていたのを覚えています。でも当時10代の私は何の興味もなかったんですね。ところが、その後に実際に取り組んでみて、あのようなシンプルなメロディの中で、深い内容表現ができるということに、ベートーヴェンの偉大さというものを改めて実感しました。

深い音色の秘密とは。シゲティから学んだこと
――今回、録音を聴かせていただきヴァイオリン・ソナタ第1番の最終楽章ロンドの中間部を深い音色で弾かれているところに、私は人生を振り返るような趣きを感じました。深い音で楽想を表現すことを意識されていることはありますか。
前橋 何度も楽譜を読み返してみると、私なりに感じるというか、読めることがあるんです。第1番は何十年も前に弾きましたが、今回再び弾いて、あのような「音色」をベートーヴェンが要求しているように私には思える訳ですね。それと、シゲティの影響はすごくあるかも知れません。というのも、例えば同じ「ソ」の音をD線でも弾ける、G線でも弾ける、でも明らかにD線とG線では音のもっている趣きが違うんです。シゲティはそういうことをとても重視した先生なんです。ときに非常に演奏しづらい指使いをするのだけど、それは彼がどうしてもその音を欲しかったからす。それも単に演奏効果を狙ってということではなくて、ベートーヴェン自身がこの音を欲していたのだと、彼は確信をもっていたのです。シゲティのレッスンを何度も受けていると、そういうことが理解できていくのです。そういう影響はあるかも知れない。だからシゲティは他の曲でも、他人には変な指使いと思われるかも知れませんが、指使いではなくて「音」「音色」をとても大事にされたから、確信をもって絶対こっち、と選んでいた。そういうところはベートーヴェンのソナタのほかの所にもいっぱいありますね。
ベートーヴェンを突き詰めたいという思いから録音に挑む
――前橋さんがベートーヴェンのソナタをパッケージ、フィジカルにしたということは、自分の今の思いを形にして残したい、というのがあったのでしょうか。
前橋 残したい、ということよりも、私は勉強したいのね。私は残された時間も限られていますから、そうしたときに何に時間を使いたいかというと、やはりベートーヴェンのソナタをもう一回、あらためて突き詰めたい、取り組みたいという思いがすごく大きかったんです。それには、いろいろな方を巻き込んで、苦労して作らなくたって、とは思いますが、ここまでやって、いろいろなことが見えてくることがある。それが私にとってはとても大事なことなんです。

――最後に、ベートーヴェンの時代の楽器やピリオド奏法について、どう思われますか。
前橋 私もバッハの《無伴奏》全曲を録音したときに、ピリオド専門のヴァイオリン奏者にレッスンしてもらったり、当時の弓を試したりしました。でも、そう簡単にいかないし、全然違う方向で勉強しないといけない。どちらが正しい、ということはないけれども、弓の奏法や弦を試すことによって得られたヒントはあります。だから、奏法を元に戻したときに、そういうような音が出るんですね。ですから参考にする部分はもちろんありましたね。
――ありがとうございました。
取材協力=ソニーミュージック・レーベルズ、ヒラサ・オフィス

ヴァイオリン・ソナタ全集
〔第1番~第10番〕
前橋汀子(vn)ヴァハン・マルディロシアン(p)
〈録音:2023年6月,7月,2024年1月〉
[ソニークラシカル(D)SICC19081~4]SACDハイブリッド
ちょっとお昼にクラシック 前橋汀子&荘村清志(ギター)
[曲目・演奏]
エルガー:愛の挨拶,ドヴォルザーク:ユーモレスク,クライスラー:愛の悲しみ,J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番より ロンド風ガボット(ヴァイオリン・ソロ)他
[日程]
2025年3月8日(土) 開演13:30
[会場]
水戸芸術館コンサートホール ATM
[料金(税込)]
全席指定 1,500円(カップオン サザスペシャルブレンド1枚付き)
前橋汀子 珠玉のヴァイオリン名曲集〈春を彩る心に残る数々のメロディ〉
※2024年7月18日の延期公演です。
[曲目・演奏]
エルガー:愛の挨拶,クライスラー:愛の喜び,ウィーン奇想曲,プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ,ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2番,ハンガリー舞曲 第1番、第5番,他
[日程]
2025年3月14日(金) 開演14:00
[会場]
埼玉会館 大ホール
[料金(税込)]
全席自由 一般 3,000円 学生(高校生以下) 1,000円
※2024年7月18日のチケットはそのまま有効です。
前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
[曲目・演奏]
ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番《雨の歌》,同第3番, クライスラー:ウィーン奇想曲,愛の喜び,マスネ:タイスの瞑想曲,ファリャ:スペイン舞曲,他
[日程]
2025年4月27日(日) 開演14:00
[会場]
三鷹市芸術文化センター 風のホール
[料金(税込)]
全席指定 一般 S席:4,000円 A席:3,000円 O-70(70歳以上/A席限定) 2,700円 U-23(23歳以下/A席限定) 2,500円