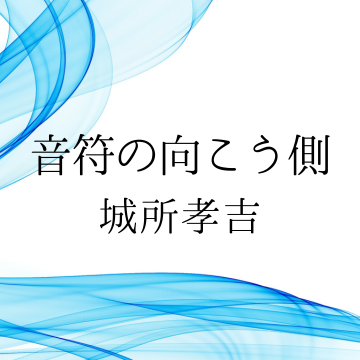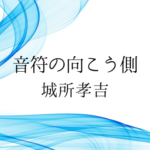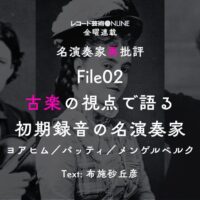音楽評論家・城所孝吉氏の連載、第3回は、シューベルトの弦楽四重奏曲第14番ニ短調D.810《死と乙女》。この作品に貫かれているテーマは「メメント・モリ」(=死を想え)。人間の死の淵が垣間見えるようなこの壮絶な音楽物語を、クリスマスあるいはお正月を迎えるこの時期に聴き直してみる、というのもなかなかに逆説的で意味深いことかも知れません。
シューベルト作品の「隠れた物語性」
「極論」としてお聞きいただきたいのだが、音楽作品には、曲自体の自律性が高く、演奏者が特別なことをしなくても成り立つものと、積極的に解釈しなければ形にならないものとの、二種類があると思う。
例えばベートーヴェンの《悲愴ソナタ》は、曲が流れの構築や曲想の意味付けを自分でやってくれるところがある。それほど内容が明確で、弾き手が道を踏み外しようがないのである。他にも《英雄ポロネーズ》やブラームスのヴァイオリン協奏曲、チャイコフスキーの交響曲第5番等は、楽譜にある通りに演奏しただけでも、(おおまかな次元において)それなりに音楽になると思われる。
いっぽう同じショパンでも、《幻想ポロネーズ》は単に音符を弾いただけではまったく形を成さない。ピアニストが「読み」を弾き込まないかぎり、13分間とりとめのない音楽が続くだけになってしまう。あるいは《悲愴交響曲》も、指揮者が作品の含意、作曲家の意図を想定していないと、行方がわからなくなる。音大生やプロの演奏家ならば、頷いてくれるのではないだろうか。そうした性格の作品は、実は少なくない。ベートーヴェンの後期作品の大部分がそうだし、マーラーの交響曲も想像以上に「解釈」を必要とする。
しかし「そのままではわからない曲」を書いた作曲家の代表格は、シューベルトだろう。限られた有名曲を除けば、多くのピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲等は、楽譜を弾いただけでは成立しない。演奏者が、なぜそのように書かれているのかを読み込んで、意味を掬い出す必要がある。例えばピアノ・ソナタ第15番《レリーク》は、途方もなく謎めいた作品だ(意図が測りかねるからだろう、バレンボイムはシューベルト・ソナタ録音選集でこの曲を取り上げていない)。ヴァイオリンとピアノのための幻想曲も、「なぜこう書いたか」についての回答がなければ、脈絡不明になってしまう。
誤解を避けるために言うが、これは作品が劣っているとか、内容や構成に欠陥がある、ということではない。作曲家が表現しようとしたものが、楽譜という記述法に収まり切れておらず、弾き手がその意味を推察し、演奏に織り込んでいかなければならない、ということなのだ。音符の表に出ているのは氷山の一角で、裏に意味や意図が隠れている。その際言えるのは、そうした「行間の内容」が、多くの場合プロットだということである。楽譜を読んでいると、形式や和声といった純粋に音楽的な要素を分析しても説明できないことがあるが、その解析不能な要素とは、往々にして「隠れた物語性」なのである。シューベルトの場合、それは思いのほか具体的になる。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。