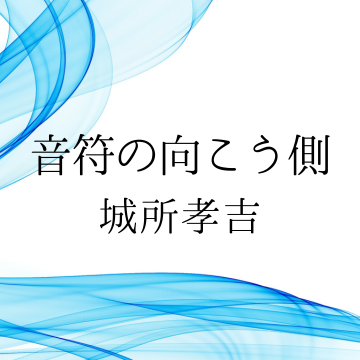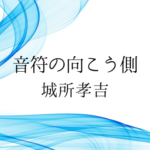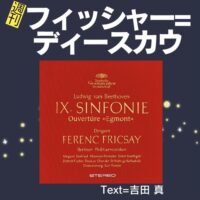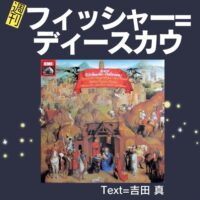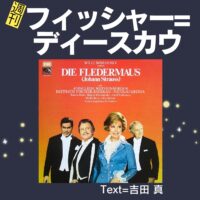音楽評論家・城所孝吉氏の連載は、いよいよ “シーズン1” の大詰めです。これまでは「演奏家が作品という真実にどう迫るか」をテーマとしてきましたが、それでは「聴き手にとっての真実」とは何なのでしょう。我々聴き手は、演奏家の思考や意図を完全に理解し、言い当てることができるのでしょうか。それとも演奏を、自分が感じるままに自由に聴いていいのでしょうか。第12回では、作品→演奏家→聴衆の「解釈の連鎖」の間に、大きなアーチが築かれます。
作品という真実は、我々には知り得ない
読者諸氏はご記憶だろうか。1年前に本連載をスタートした時の最初のテーマは、「作品と演奏家の間には断絶がある」ということだった。演奏家は、「作品という真実」に到達することはできない。どんなに努力しても、作曲家の想念は、それを解釈する人間には知り得ない……。
普段あまり意識しないことだが、この両者を介在する役割を果たす楽譜は、音楽ではない。音符とは、作曲家が考えたことの「痕跡」にすぎず、作品が血肉を得、「音」になるためには、必ず演奏する人間を必要とする。そして彼らが出す音は、作品(=作曲家が想起した曲の姿)そのものではない。楽譜を読む演奏家の主観というフィルターを必ず通るため、作品は原理上、客観的に再現され得ないのである。それはどの場合においても個々の現象として立ち現れるが、我々は極論すれば、曲の「真の姿」を知ることができない。しかし、である。それは決して忌まわしいことでも、悲しいことでもないだろう。作品そのものの再現が可能ならば、「正しい」解釈は必然的にひとつしか存在しなくなる。逆説的なことに、演奏家は真実そのものに到達し得ないからこそ、「自分の信ずる作品のあり方」を追求し、表現する自由を与えられているのである。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。