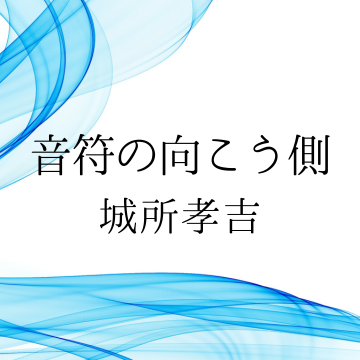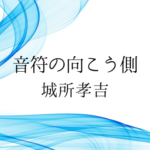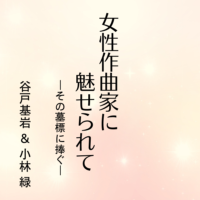音楽評論家・城所孝吉氏の連載、第7回のテーマは、ピアノ音楽あるいはピアニストについて。すべての楽器の中でピアノ(音楽)は、音づくりから解釈のディテールまで「徹頭徹尾ひとりの演奏家で完結しうる」唯一の独奏楽器と言えるかもしれません。すなわち我々がピアノ作品の音源を聴くこととは、まさしくピアニストその人と一対一で対面することにほかなりません。
ピアノ――最大のポテンシャルを持った楽器
これまで当連載では、音楽家が作品を解釈・演奏する時に、自分ですべてをコントロールできるかのような書き方をしてきた。しかし実際には、そうではない。演奏は、多くの場合、複数の人によって行なわれるからである。個々の奏者にはそれぞれの考えがあり、ひとつの統一された解釈があらかじめ存在するわけではない。奏者が自分の解釈を貫徹できるのは独奏曲だけである。そして独奏曲とは、端的にはピアノの音楽だと言える。
ピアノは、あらゆる楽器のなかでも特殊な存在である。それは単に、ひとりで演奏できるからだけではない。包括的な表現が可能で、作品から無限とも呼べるほどの複雑さを引き出し得るからである。もちろんバッハの無伴奏ヴァイオリン作品のように、他の楽器でも深く高度な内容を表現したケースはある。しかしそれはあくまで例外で、同等のレパートリーが数多く存在するわけではない。またチェンバロをはじめ、他の鍵盤楽器でも、同じことは論理的には可能だろう。しかしピアノには、独奏楽器としてのポテンシャルが、他のどの楽器にも増して備わっている。包括的な表現が可能だからこそ、複雑なソロ作品が書かれるようになったのである。
その意味でピアニストは、複雑な作品をひとりで解釈し、ひとりで演奏する音楽家と呼べる。そして、解釈することが「デフォルトで任されている」存在でもある。彼らは楽器を習い始めた当初から、作品全体を自分で解釈し、音にしなければならない。これは面白い現象と言える。例えばオーボエ奏者やフルート奏者が、総体的な読みを携えて演奏に望むことはあまりない。ソナタ等でリードを担うことが多いヴァイオリン奏者にしても、レパートリーの絶対数はピアノとは異なる。そこで主導権を握ったとしても、すべてを自分では音にできず、共演者に依存せざるを得ないのである。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。