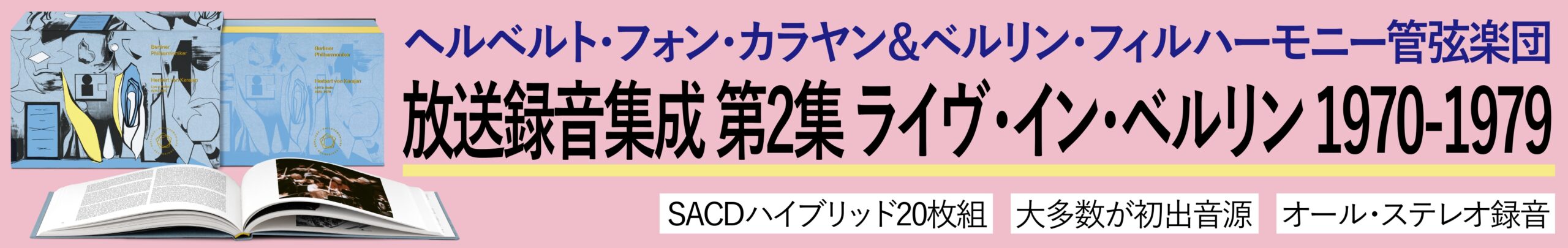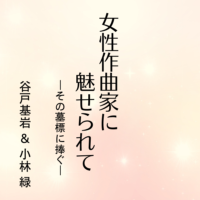一周まわった地点でふたりが出会う
たぶん生き乍ら鼠や蛇に噛まれ、食われ、じわじわと死んだのだろう。
それなのに――。
侍の顔は――。
伊右衛門様とお岩様です――と男は言った。
伊右衛門は。
嗤っていた。
余茂七は手を合わせ、意味もなく、ただはらはらと泣いた。
(京極夏彦『嗤う伊右衛門』)
はじめて人を好きになったのがいつかはよく覚えている。
小学校に入ってすぐ、同級生のひとりを良いなと思ったのだ。ある時、男子数人が彼女の家に呼ばれることになった。喜んだわれわれは、皆で近所の善福寺公園の花を摘んで持っていくことにした。小1にしてはなかなかジェントルマンな発想である。
他の男子は花をビニール袋に放りこんだだけだったが、わたしはランドセルを置きに家に帰った際、母に「結婚式の時みたいにして」と頼んだ(その情景とセリフをよく覚えている)。花束にしたかったのだ。これはもう、なかなかどころか「相当に」ジェントルマンな発想である――もしかすると祖先にイギリス人がいるのかもしれない。大の花好きの母は、適当な紙をうまく使って、すぐにブーケみたいなものを作ってくれた。
彼女の家に行く途中、この即席ブーケを見た友人たちはどうにも鼻白んだようで、もういいや、とビニール袋を道端に捨ててしまった。かくしてわたしだけが、得意げに彼女に花をプレゼントしたのだった。
いったい、彼女はどうしているだろう。名前も顔も忘れてしまったのだが、おぼろげなイメージだけは今も残っている。
■
恋愛、というのは多くのひとにとって、きわめて重要な問題であるらしい。
その証拠に、誰もが知る通り、歌詞のある歌のほとんどは恋愛にかかわるものだ。ポピュラーであろうがクラシックであろうが変わらない。人類はまったく飽きることなく、大昔から現代にいたるまで恋愛ばかりを歌にしてきた。宇宙人がこれを見たら、地球人というのは恋愛バカばかりなのかと呆れることだろう。
歌が集まり物語化されたオペラとなると、この傾向はさらに強くなる。とりわけ19世紀のオペラで恋愛要素がないものを探すのは、好きな子の家に花束を持っていく小1を探すより難しいはずだ。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。