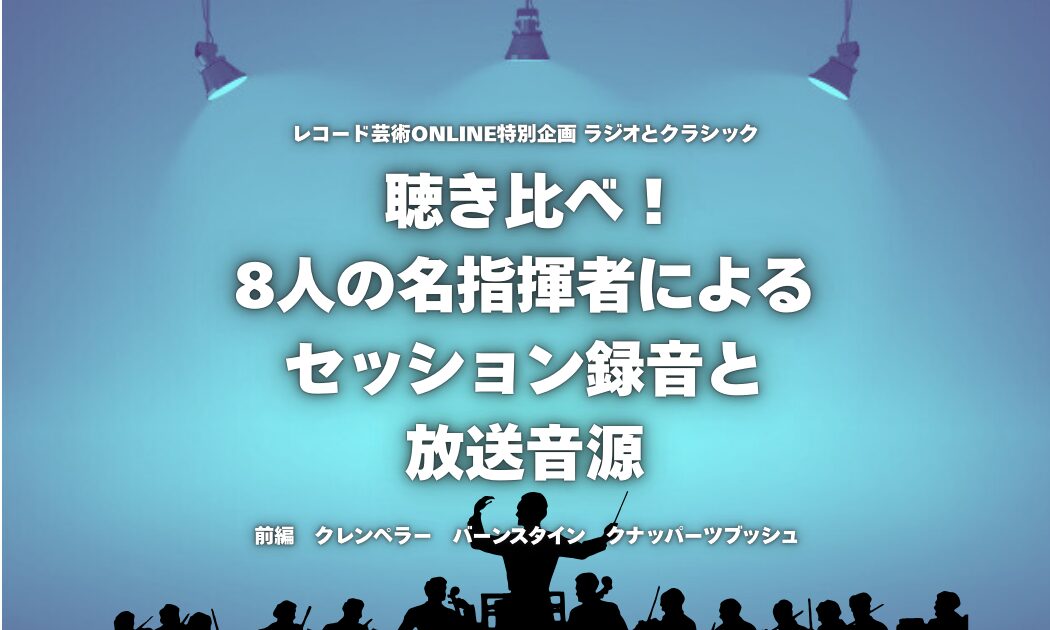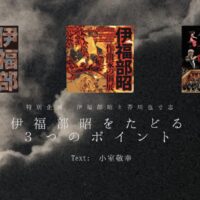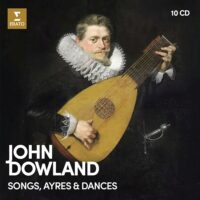2025年は、日本におけるラジオ放送開始から100年の節目! レコ芸ONLINEの特別企画シリーズ「ラジオとクラシック」の第2弾は、「セッション録音と放送音源」です。8人の名指揮者が遺したセッション録音の名盤とその前後にライヴで演奏した同じ曲の放送音源を聴き比べて、違いを味わいましょう。
ディスクの配列は収録年順で、前編は1950年代から60年代前半の録音を取り上げます。
前編(この記事):クレンペラー、バーンスタイン、クナッパーツブッシュ
後編はこちら:バルビローリ、クーベリック、ボールト、ハイティンク、ジュリーニ
選・文=相場ひろ(フランス文学)&増田良介(音楽評論)
聴き比べによって演奏家のこだわりが立体的に見えてくる
その昔、レコードというのは、客のいないスタジオで、何本ものマイクを吊ったり立てたりして行なうセッション録音が普通だった。うまくいかなかったところがあれば、その部分だけやり直し、テープをハサミで切って編集するのだ。放送局が演奏会を録音して放送で流すこともけっこう昔からあったが、レコードの収録はそれとは根本的に違っていた。
ところがある時期から、フルトヴェングラーなど、往年の巨匠たちのライヴ録音が、おもに放送局の音源をもとにして、レコードとして発売されるようになる。それらは、セッション録音に比べると音質も良くないし、演奏には傷もあったが、貴重なレパートリーがあったり、演奏会ならではの高揚感があったりして、ファンに珍重された。カラヤンが1989年、バーンスタインが1990年に世を去ると、その流れはいっそう顕著になり、アーカイヴから発掘された貴重な音源が次々と聞けるようになった。
そしてその中から、おもしろいケースが出てくる。長年聴かれてきたレコードの直前や直後に行なわれた演奏会のライヴ録音が出るようになったのだ。近い時期に同じ人たちが同じ曲をやったら似たような演奏になるかと思いきや、これが案外そうでもなくて、速かったり遅かったり、表情が違っていたりする。聴き比べると、単純にどちらが良い悪いではなく、演奏家の意図やこだわりが、より立体的に見えてくる。ここでは、そのようなちょっとマニアックな聴き方ができる、セッション録音とライヴ録音のペアをいくつか紹介しよう。(増田)
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。