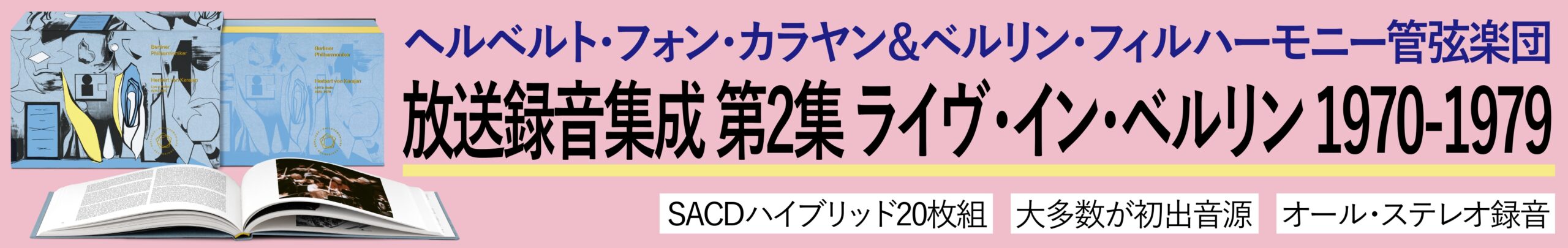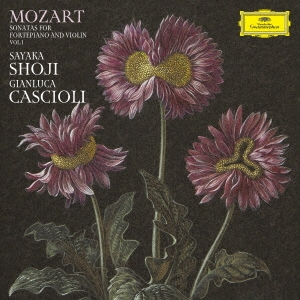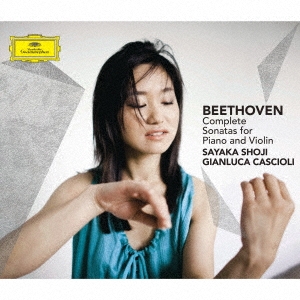インタビュー・文=山崎浩太郎(演奏史譚)
ヴァイオリンの庄司紗矢香とピアノのジャンルカ・カシオーリのデュオは、DGに録音したベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集の名演で知られている。また2022年には、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタ集を、庄司がクラシカル弓とガット弦、カシオーリがフォルテピアノで録音したことで、大きな話題となった。イタリアのArcanaレーベルからリリースされるこのソナタ集の第2集について、庄司に話を聞いた。

モーツァルト: ヴァイオリン・ソナタ 第25番K.301,第34番K.378,第40番K.454
庄司紗矢香(vn)ジャンルカ・カシオーリ(fp)
〈録音:2023年12月〉
[Arcana(D)NYCX10507]
音楽を自由にする、カシオーリという存在
――モーツァルトのヴァイオリン・ソナタとの出会いは、子供の頃でしょうか?
庄司 初めて学んだのはシエナのキジアーナ音楽院で、12、13歳ぐらいのときです。そのうちの一曲がK.301(第25番)でした。それ以来、何度かひいてきましたが、2009年のカシオーリとの出会いは、とても大きな転換点になりました。
小さい頃から教わった古典派の演奏様式は、いろいろな規則やタブーがあり、その枠の中で表現しないといけないものでした。今日でもそれが主流ではありますので、要求されればできますが、本能的な部分で、もっと自由に表現したいという気持がずっとあったんです。
コロナ禍のとき、学生時代から読み漁っていた18世紀のいろいろな教本を読み終えることができたのですが、そこには私が本能的に欲していた音楽作りの醍醐味が全部書いてあった。装飾とか音の長さの不均等さだけでなく、楽章内のテンポの変化とかルバートとか、教本に書いてある事は単に「規則」ではなく、当時の音楽家の感性が深い感情と繋がっていることが確認できたのです。
そんなふうにしていいんだと、古い教本から知ったときはとてもありがたく、嬉しかった。そしてそのように、オーガニックで、血の通った演奏を実際に叶えてくれたのがカシオーリでした。
かれも私と同じように、イタリア的な歌いまわしが常に根底にあり、歌に通じる音楽の作りかたをします。第二次世界大戦後に生まれた禁欲主義的な伝統を全部取り払って、共に当時の演奏についての研究をしながら自由に新しい音楽を作っていける相手という意味で、貴重な存在なんです。
――そういう演奏をする上で、ガット弦やクラシック弓のもつ意味は大きいのですか?
庄司 つじつまが合うということはあると思います。特にクラシック弓は、フォルテピアノと音量も合いますし、アーティキュレーションやダウンとアップの違いとか、教本に書かれていることがより自然に実現できますね。
――今回の3曲について、まずK.301(第25番)は、先ほどのお話では最初に習った曲ですね。
庄司 時間をおいて取り組むときには、全てを消してゼロから考えます。今回はいい機会で、ヨーロッパのリサイタルでこれをひいてほしいとプロモーターが言ってきたのと録音の時期がちょうど重なったので、選びました(笑)。
K.378(第34番)は、K.301よりも構成が洗練されて、とてもオペラティックな曲です。いろいろなピアニストと一緒にひいてきましたが、最初のところで右手はピアノ、左手はフォルテですぐにピアノになるんです。それがモダンのピアノではうまく響かすことができなくて、どうしようというのがいつもピアニストの悩みだったんです。だけど、フォルテピアノだとちゃんと聞こえる。その時代の楽器を使うと、楽譜に書いてあることとのつじつまが合って、とてもおもしろい体験でした。
K.454(第40番)の冒頭は、私の中では鐘が鳴って、響きあうようなイメージで演奏しています。そして付点音符のリズムが出てきます。長い部分はより長く、短いものはより短くひくというのは18世紀の教本に書いてあることなんですが、なかなかそのように演奏されることがないのです。
細かなことですが、そうしたほうが、表現がより生き生きとするのではないかと思います。2010年にバッハの無伴奏を録音したときにも、例えばパルティータ第2番〈シャコンヌ〉での付点のリズムは同じ教本の教えに従っています。またクーラントの3連音符の付点のリズムについても教本から教わったものです。今までそうした小さなことを積み重ねてきているのです。
――ありがとうございます。つぎに録音会場ですが、前回はモンドウィの教会でしたが、今回のトリノのペチェット・トリネーゼは、どんな会場ですか?
庄司 スタジオなんです。前回の教会はとてもいい響きでしたが、残響が長い。それに鐘が鳴るので30分おきに中断されたり、鳥の鳴き声なども入る場所だったんです。
――たしかに鳥が聴こえますね。
庄司 わざと入れたんです(笑)。それに、録音したのは2022年の5月でしたが、すごく寒かったんです。私達はセーターを着ればいいのですが、ガット弦やフォルテピアノに影響が出るんです。寒くて乾燥しているのがいちばん鳴らないんです。今回は12月でしたが暖房が効いて、加湿器も置いて、フォルテピアノに最適な環境にしました。

――ところで、前回はDGからの発売でしたが、今回はArcanaレーベル。どうして変わったのですか?
庄司 カシオーリがArcanaでCDを出していて、そこでヴァイオリン・ソナタも全集にしたいがどうだろうか、という話になったんです。途中で移るのはどうだろうとは思いましたが、双方のレーベルと話しあって、自然な流れで円満に決まりました。Arcanaは特にバロックやHIP(歴史的知識に基づく演奏)に力を入れているレーベルなので、そこからモーツァルトのソナタ全集を出せるのは嬉しく、とても光栄なことです。
ただ全集の録音については、特にタイムリミットはつくらず、録音できるときに録音して、ゆっくりとマイペースでいけたらいいなと思っています。
――そのほかの録音の予定など、お話できる範囲でお願いします。
庄司 カシオーリは作曲もしていて、私に献呈してくれたソナタを録音する予定があります。ホルンのアレッシオ・アレグリーニを加えた、ブラームスとリゲティのホルン・トリオも一緒に。ほかにいろいろアイディアはあるんですが、トランシルヴァニアの作曲家にいくつか面白い曲がありますね。それから、まだ先になるかもしれませんが、シューベルトやシューマンのソナタも録音してみたいです。
――ありがとうございます。楽しみにしています。
庄司紗矢香 Sayaka Shoji
1999年パガニーニ国際ヴァイオリン・コンクールで史上最年少&日本人として初優勝。1998年以降、ヨーロッパに活動拠点を移し、世界の名指揮者、名オーケストラとの共演を重ねている。室内楽活動にも力を注いでおり、イタマール・ゴラン、スティーヴン・イッサーリスらと共演するほか、2010年からは水戸芸術館の専属楽団「新ダヴィッド同盟」の中心メンバーとしても活動を行なっている。録音ではカシオーリとデュオでベートーヴェンのソナタ全集が 2015年春に完結、コロナ禍の期間を挟んで、2022年に、同じくカシオーリとモーツァルトのソナタ録音のプロジェクトをスタートさせた。使用楽器は1729年製ストラディヴァリウス「レカミエ」。
庄司紗矢香 公演情報
ラハフ・シャニ指揮 ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 来日公演2025
(曲目 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲)
6/22(日)15:00 愛知県芸術劇場コンサートホール
6/27(金)19:00 サントリーホール
6/28(土)14:00 横浜みなとみらいホール
https://www.japanarts.co.jp/concert/p2124/
取材協力=ナクソス・ジャパン、ジャパン・アーツ