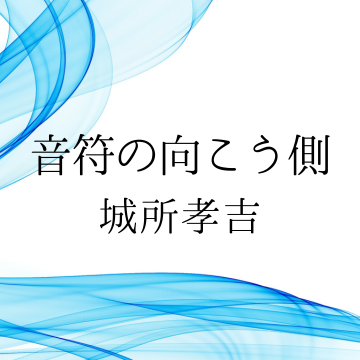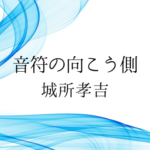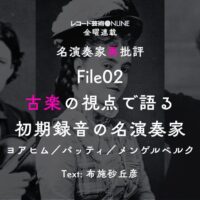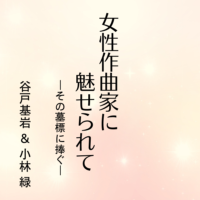音楽評論家・城所孝吉氏の連載、第6回は、モーツァルトの大ミサ曲ハ短調K.427を例に、いわゆるH.I.P.(Historically Informed Performance 歴史的知識に基づく演奏)について考察します。けっして難解な話などではなく、そこには普段我々が聴いている様々な時代の様々な音楽の「聴き方」にも関わってくる興味深いテーマが横たわっています。
十字架は「ジグザグ」、ため息は「下降」
哲学では、近代以前の人間は、現代の我々とは違うあり方で世界を認識していた、と考えられている。当時の人々にとって、物事は固定し独立した概念と結びついており、認識は概念の中で行われた。それが中世後期から変化し始め、近代に入って「主観」が誕生する。主観は、17世紀のデカルトを経て、18世紀末のフランス革命までには完成したが、我々がそこで獲得したのは、「世界を自分に見える通りに見る」というパースペクティヴであった。
この変化は、絵画の歴史を見るとわかりやすい。中世の聖母子のイコンでは、イエスとマリアは中央に巨大に、それ以外の人物は周囲に小さく描かれている。これは、ふたりが他との比較において重要だからで、彼らの「目に見える姿」ではなく、神と聖母の「概念」が描かれている。逆に言うと、中世において人間は、目に見える通りに絵を描くことができなかった。それが可能になったのは、ルネサンスに遠近法が発見されてからである。1427年にマザッチョが『三位一体』を描いた時、フィレンツェ市民はその「リアルな」表現(会衆が十字架上のキリストを見上げる遠近法で描かれている)に驚愕したというが、リアリズムは、対象を見る人間の視点=主観があるから可能となったのである。
なぜこんな話で始めたかというと、同様のことが音楽にも当てはまるからだ。バロック音楽の特徴のひとつは修辞法だが、当時音楽は「概念」のもとに成り立っていた。バッハやモーツァルトの声楽曲の楽譜では、「十字架」という言葉にジグザグ音型、「ためいき」という言葉にスラーの付いた下降音型が書かれている。これはよく「描写的表現」と呼ばれるが、正しい言い方ではない。というのは、彼らは特定の状況を描写しているのではなく、あらかじめ存在する十字架=ジグザグ音型、ためいき=下降音型という「記号」を、作品でパズルのように組み立てているからである。感情(アフェクト)や状況は、そうした定型によって表現され、修辞法は、音が言葉のように用いられることを指す。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。