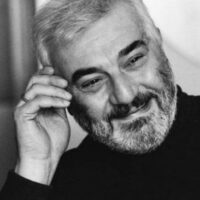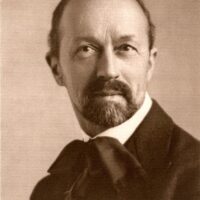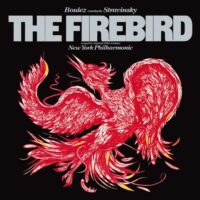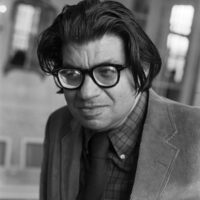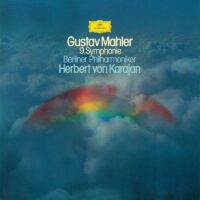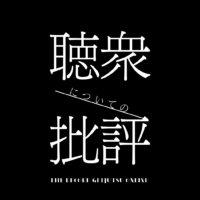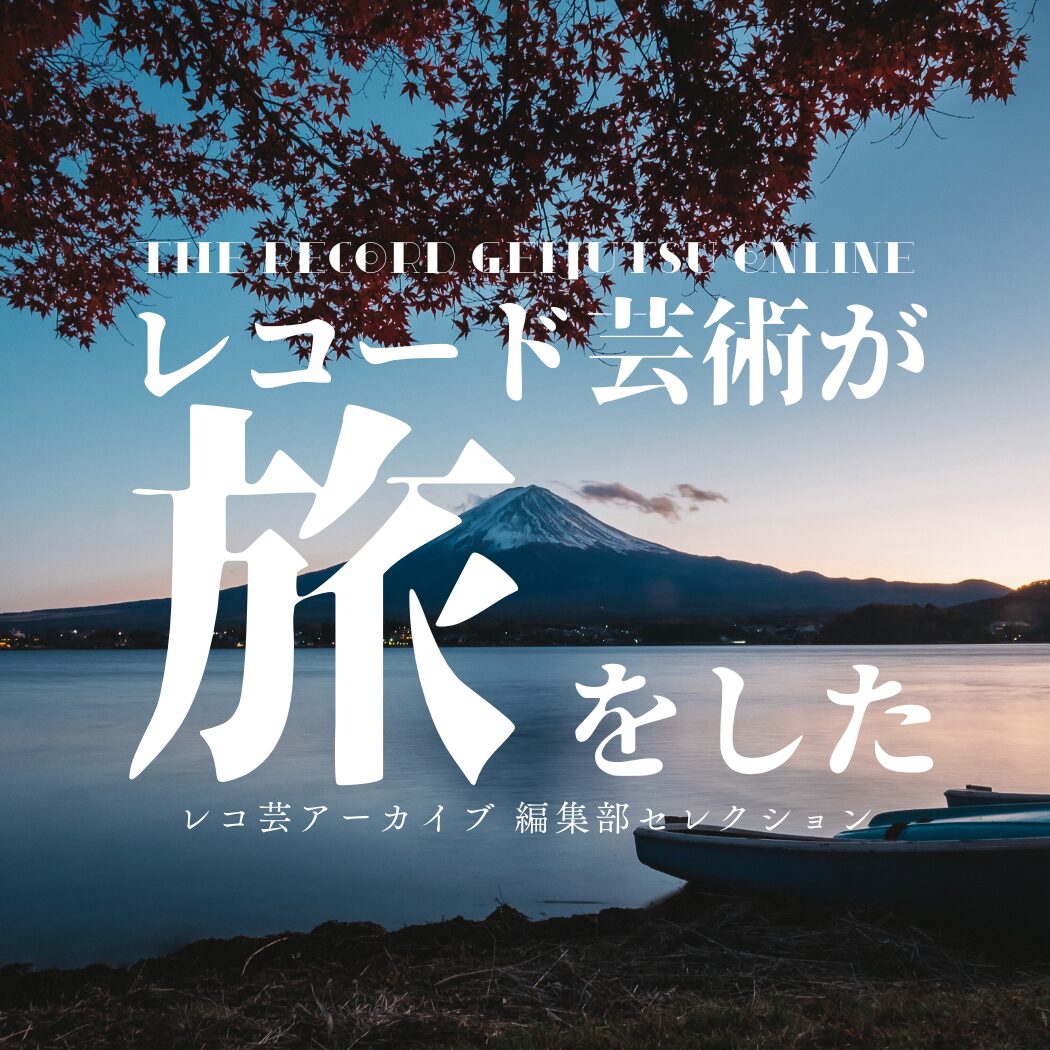
このコーナーでは編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとに集めて、ご紹介していきます。
新テーマは「レコード芸術が旅をした」。東京をねじろとする『レコード芸術』ですが、誌面で展開されたまなざしは、東京近辺に完結するものでは決してありませんでした。
第2弾として、1963年8月号に掲載された、志鳥栄八郎さんの『山陽・瀬戸内コンサートかけある記』をお届けします。志鳥さんは、レコード会社と協力して、全国をまわり、録音芸術を解説する「コンサート」を繰り返し行っていました。
食道楽の評論家による、歯に衣着せぬ旅日記と、豊富な写真のなかに、当時のひとびとの様子や、クラシック音楽受容の一端を垣間見れます。
・志鳥栄八郎『北海道コンサートかけある記』(1963年1月号初出)
・志鳥栄八郎『九州地区コンサートかけある記』(1964年5月号初出)
※文中の表記・事実関係などはオリジナルのまま再録しています。(今日では不適切と思われる表現も含まれますが、原典を尊重してそのまま掲載いたします)
※登場するレコード店、飲食店等は、現在閉業している場合がございます。ご了承ください。
※記事中の写真は、当時随行した『レコード芸術』編集長、辻修氏の撮影によるものです。

広島の原爆資料館から慰霊碑、原爆ドームを望む、その右に広島市民球場の照明塔が見える
第2回ビクター・レコード・コンサート・キャラバン(フィリップス関係)は、山陽道の宇部・徳山・広島・福山・岡山の五都市をまわった。あいかわらず、ぎっしりとつまったスケジュールで、辻君もわたしも、ともに1キロ半もやせるつらい旅だったが、収穫は大きかった。例によって、粗末な旅日記をご披露しょう。
1963年6月25日(火) 宇部
特急「はやぶさ」が、小郡[レコ芸ONLINE編注:現在の新山口]のホームにすべりこんだのは、朝の9時24分だった。
小郡の駅も、駅前の広場も、2年前とはがらりと変っていた。日本の町は、1年たつと、どこもかしこも姿が一変する。その変りようは、おそろしいほどだ。
南国特有の強烈な太陽が、睡眠不足の目にしみる。ほんの1週間前に旅した青森の太陽とは、その明るさがまるでちがう。吹けば飛ぶようなこの小さな日本だが、東北と山陽とでは、気候風土から、家並みから、ひとの性格まで、驚くほどちがっている。
わたしたちを迎えてくれたビクターの野村課長と河野君といっしょに、バスで宇部にはいる。この夏から秋にかけて、第18回の国体が開かれるので、宇部は町の浄化にいそがしい。旅装をといた堀辺旅館も、国体までにまにあわせようと増築におおわらわなので、昼寝もできず、さっそく取材にとびだす。
まず、新天町の名曲堂と大新に寄る。2軒とも大きなレコード店で、大新のほうではバーゲン・セールを盛大にやっていた。
名曲堂の加藤氏に、宇部の景気はどうですかとたずねたら、
「宇部は宇部興産の景気で左右されます。興産の景気がよければ、したがってレコードの売り上げもグッと……」
そこで、大新の若社長の案内で常盤湖と宇部興産の周囲を見物することにした。常盤湖なんて、どうせ水溜りぐらいなものだろうと思っていたら、どうしてどうして、周囲12キロもあるすばらしい湖であった。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。