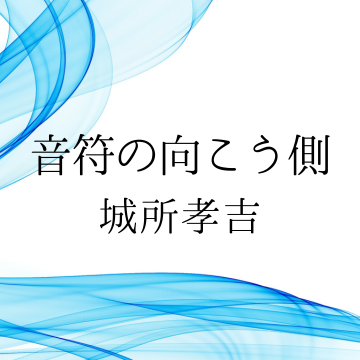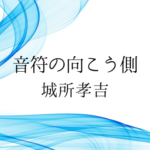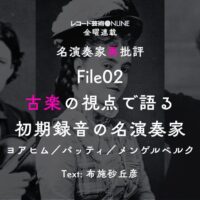音楽評論家・城所孝吉氏の連載、第4回は、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35。あまりに有名なこの曲の成立背景(バイオグラフィ)は、意外に知られていないかもしれません。その経緯を詳細に紐解きながら、作曲家のバイオグラフィと楽曲を関連付けることの是非を考察していきます。
バイオグラフィからの作品解釈は是か非か
前回(第3回)は、作品にはプロット=物語性を持ったものが存在する、という話をした。それをシューベルト《死と乙女》の例で考えたが、最後に浮かび上がったのは「作曲家はなぜそうした作品を書いたのか」という問いである。これに対するひとつの説明は、「彼は作品で、自身との死との対峙をテーマにした」ということだった。
このような推論を行なう場合、必ず俎上に上がるのが「作品を作曲家のバイオグラフィから解釈することは正しいか」という議論である。一般に1960年代以降の文学解釈では、作品は自立した構築物であり、その内的な構造を分析することが正しいとされる。音楽演奏でも、形式、和声、モティーフを解析し、楽曲の論理的な組み立てを明らかにすることが、正統的なアプローチと考えられる。これは言うまでもなく正しく、あらゆる解釈の前提だろう。
一方、バイオグラフィから作品を説明するアプローチは、恣意的になりがちである。個人的状況と作品の間の関連を跡付けること(証明すること)が難しいだけでなく、画一的な解釈に陥りやすいからだ。例えば、スターリン政権下で書かれたショスタコーヴィチの交響曲には、作曲家の苦悩が表れていると言われる。あるいはショパンの作品には、故郷ポーランドへの憧憬が映し出されているとされる。その見方は、基本的には間違いないだろう。しかし、それだけではあまりに一般論に過ぎて、個々の作品の解釈の助けにはならないのである。
それゆえ演奏の現場では、「バイオグラフィからのアプローチ」を嫌う傾向がある。例えば音楽大学では、掴みどころのない作品の背景を問題にする前に、構造そのものを分析して、内部で何が起こっているかを考えることが奨励される。学生の場合は「音楽の文法」を学び、作品を紐解けるようになることが課題なので、当然だろう。
しかし、プロの演奏家が曲の理解を深める方法としては、それだけでは足りないことも明らかなのである。というのは作品には、構造分析だけでは説明できない要素があり、それはしばしば、作曲家の個人的な状況と結びついているからだ。あるいは、こう言えるかもしれない。音楽的な分析によって演奏が成り立つ作品もあるが、それ以上の内容を持った作品もある。そこにバイオグラフィから得られる要素を加味してアプローチすると、解釈により広がりが生まれるのである。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。