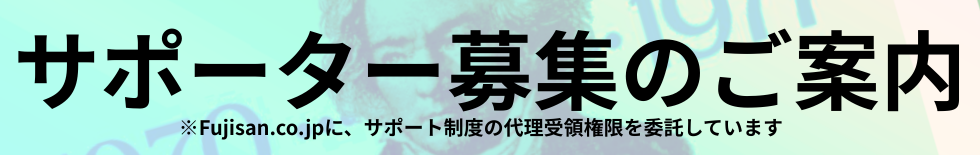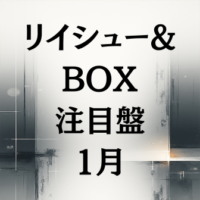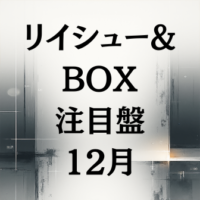ハイドン後期交響曲第4集〔交響曲第102番,第103番《太鼓連打》,第104番《ロンドン》〕
アダム・フィッシャー指揮デンマーク室内管弦楽団
〈録音:2023年10月〉
[ナクソス(D)NYCX10491]
繊細さと多彩さ、そして遊び心
初演当時の洗練性を現代に“翻案”
これこそ、現代における理想のハイドン像のひとつだろう。ハンガリー出身の名匠、アダム・フィッシャーが、デンマーク室内管弦楽団(DCO)の首席指揮者就任25年を記念して開始したハイドンの後期交響曲シリーズ、「ロンドン・セット」の完結編となる第4集(第102~104番)。この時代に特有の“作法”を踏まえつつも、決してピリオド奏法に寄せるのではなく、むしろ弦楽器などはモダン楽器の剛性を活かし、しなやかで洗練された快演を聴かせている。
NAXOSからリリースされた交響曲全集だけに焦点を当ててみても、全体的に端正ながら各曲の色彩の違いが繊細に表現されたモーツァルトに始まり、息をもつかせぬスリリングさで圧倒するベートーヴェン、超個性的で賛否両論を巻き起こしたブラームスと、発表の度に違ったアプローチで臨んできたフィッシャー&DCO。フィッシャー自身の取り組みも、伝統的なハイドン演奏の延長線上にあった、オーストリア・ハンガリー・ハイドン管との交響曲全集(1987~2001年)の録音時からは、全く異なっている。
ディスク冒頭、いきなり耳を奪うのは、第102番の序奏部の透明感と繊細さ。アレグロに入っても、そのニュアンスは保たれる。こうした楽曲の隅々に行き渡る心遣いと繊細さは、全篇に共通。さらに、楽員たちの自主性に裏打ちされた、自然な音楽の伸縮には作為の欠片すら感じさせない。「太鼓連打」こと第103番で、第1楽章の序奏部以外でもソリストのように浮き彫りとなるティンパニや、第104番の終楽章でのボウイング表現の多彩さ……ハイドンの音楽が湛える独特の遊び心も、独特の感覚で掬い取られてゆく。
これらの交響曲が、初演時にロンドンの聴衆へ与えた衝撃とは、きっと、このようなものだったに違いない。そして、フィッシャー&DCOは、円熟期の真っただ中にあったハイドンが、満を持して書いた、まさに交響曲の“集大成”(実際に、第104番を最後に、彼はオラトリオやミサなどの作曲に専念し、このジャンルに二度と目を向けなかった)が孕む、時代の最先端を走る、洗練性の極みとも言うべき音楽性を、現代の聴き手の感性へアピールできる形で“翻案”して伝えたいのでは。聴き進めるうち、こんな思いすら抱いてしまう。
寺西 肇 (音楽ジャーナリスト)
協力:ナクソス・ジャパン