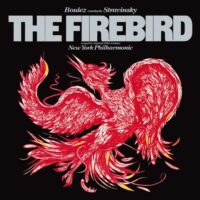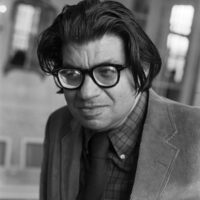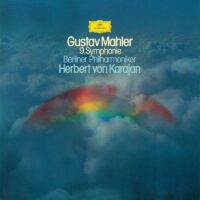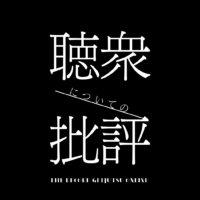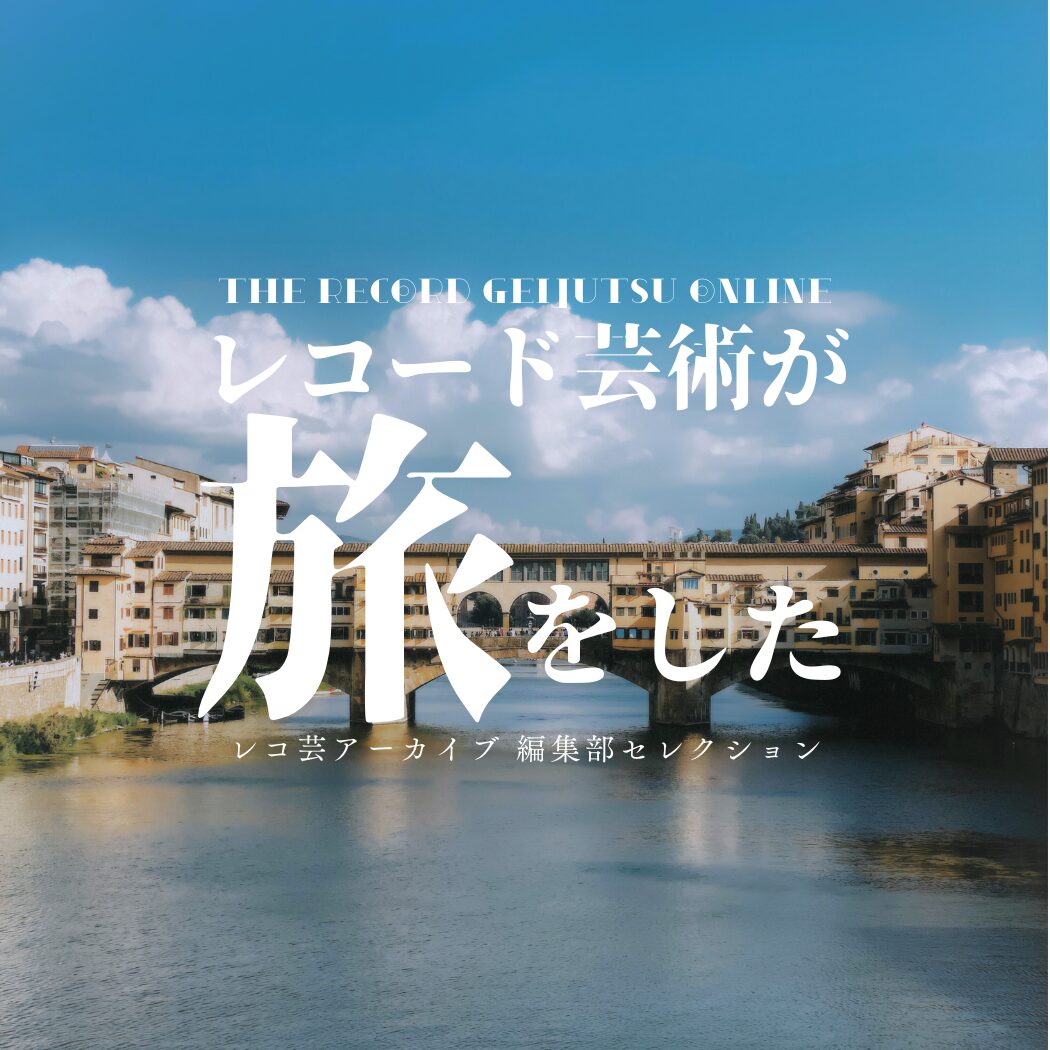
このコーナーでは編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとに集めて、ご紹介していきます。
テーマは「レコード芸術が旅をした」。東京をねじろとする『レコード芸術』ですが、誌面で展開されたまなざしは、東京近辺に完結するものでは決してありませんでした。
1967年に、4回にわたって掲載された、若林駿介さんの『欧米の音と生活』の第4弾(最終回)「アメリカのバイタリティ」(1967年12月号)をお届けします。本邦を代表する録音エンジニアとして活躍し、オーディオ評論家の顔も持っていた若林さんは、海外通でもあり、欧米諸国を繰り返し訪れ、そのレポートを『レコード芸術』に寄せることもありました。
タイトル通り、生活面にも着目した若林さんの文章・写真からは、その土地に生きる人々の「音・音楽」観が浮かび上がります。
※記事中の写真は、若林駿介氏の撮影によるものです。
ヨーロッパから大西洋を渡り、アメリカ大陸の土を踏むと、音も生活もがらりと変る。街角のノイズもコンサートの音も、レコード会社の方針も、すべての点で対称的といえば対称的である。
さほど長い歴史をもたず、伝統という言葉にさえ弱いアメリカ、一方広大なスペースとふんだんな資源によって生まれる、そのマスとスケール、じっくり見つめると、大げさな表現であるかも知れないが、同じ地球上で、こうも違うものかと感心させられた。
音楽、ハイ・ファイ、レコードという三つの上では、むしろ日本に似ている点が多い。いや、これはむしろ日本が如何にアメリカナイズされたかを物語っているのかも知れない。ただ日本の規模を、とてつもなく大きくしたものと考えればよいであろう。それほど、東京とニューヨークなど似通っている点が多いのだ。

①新装成ったメトロポリタン・オペラ・ハウス
たいへん近代的な構えに変ってしまった。正面のテラスには、テーブルも並べられていて、軽食もすませられるようになっている。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。