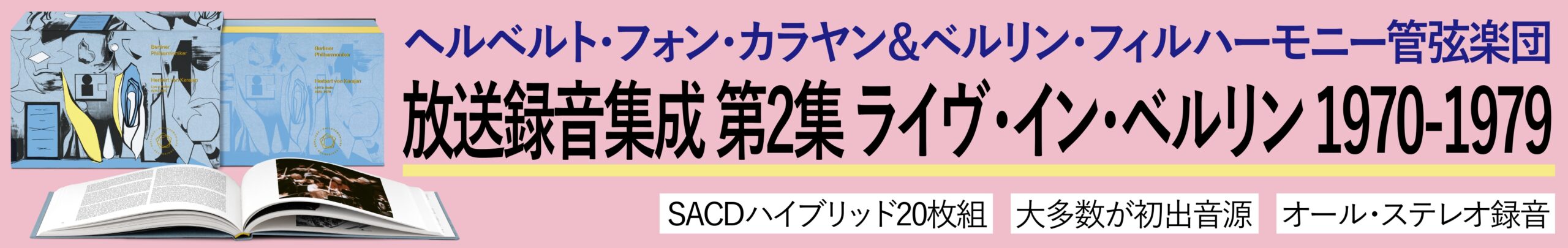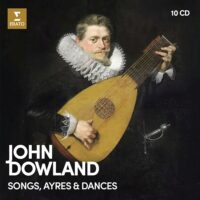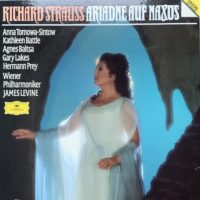2024年をもって指揮活動から引退した井上道義にインタヴューする機会を得たのは、2025年8月1日のこと。「お元気そうでなにより」といった雰囲気ではなく、彼が纏っている独特なオーラは健在であり、2時間以上にわたって、大いに語っていただいた。今回は、その中から、ショスタコーヴィチの音楽との出会いについての話をピックアップして、お届けすることにしたい。なお、一人称については、ライヴ感を優先して、敢えて統一せずに、“僕”と“俺”が混在していることを最初に記しておきたい。
①ショスタコーヴィチの音楽との出会いについて(無料記事)
②2度目の「ショスタコーヴィチ/交響曲全集」について(有料記事)
③江崎友淑プロデューサーは語る(有料記事)
Interview & Text=満津岡信育(音楽評論)
Photo=編集部
僕とショスタコーヴィチの出会いは、幸運だった
井上 俺は、本当に運がいいと自分で思っています。人間は、どこで生まれるかを選べないからね。自分がどこでどうやって死ぬかっていうのは、選べるけれども。生まれる場所が、ウィーンなのか、ノボシビルスクなのか、ガザなのかで、人生って決まってしまうじゃないですか。あとは、生まれてくる時代もそうです。僕は、時代的にも運が良かったっていう思いがとっても強い。もっと言えば僕の場合は、父親と母親の問題がいろいろあって、それは、皆さんご存知だから繰り返さないけれども、捨てられてたかもしれないし、ひょっとしたらアメリカに連れて帰られた可能性もあったわけです。それは運が良かったとしか言えないでしょ。父親と母親が助け合って、僕は成城学園というところで育ったんだけれども、すぐ近くに映画監督はいる、ピアノの先生はいる、友達は全く僕のことを差別しないという環境だった。

井上道義 Michiyoshi Inoue
1946年東京都生まれ。桐朋学園大学で齋藤秀雄氏に師事。1971年にミラノ・スカラ座が主催するグイド・カンテッリ指揮者コンクールで優勝して以来、一躍内外の注目を集め、世界的な活躍を開始、NZSO、新日本フィル、京響、アンサンブル金沢、大阪フィルなど国内外のポストも歴任し、斬新な企画と豊かな音楽性でそれぞれの時代を切り拓く。2024年12月30日に指揮活動を引退した。またオクタヴィア・レコードで制作・発売された「ショスタコーヴィチ/交響曲全集」(1回目)をはじめ、多くの録音芸術をリリースし、現在マーラーの交響曲全集へ向けてリリースを続けている。
公式サイト
そして、井上少年は音楽に親しみ、バレエを踊り、やがて、指揮者への道を歩むことになる。ショスタコーヴィチの音楽に開眼したのは、音楽監督を務めた京都市交響楽団(以下、京響と略)でショスタコーヴィチの交響曲第7番《レニングラード》を指揮した時のことであったという。
井上 第7番をやった時に、当時は、現在と違って、京響は今ひとつのオケでしたが、突然、ヴィオラが素晴らしい旋律を弾き出しました。その感激が、一体何でこの人たちは、この部分に共感した音が出せるのかなと思い、ショスタコーヴィチは、俺がこれまで考えていた作曲家じゃないのかもしれないと感じました。京響の本拠地は、当時は多目的ホール(京都会館)で、音響は、はっきり言って酷かった。そのホールでいろいろ試みたけれども、無駄な努力だった。そうやってもがいている時に、ショスタコーヴィチの第7番を演奏したら、彼の音楽がホールにビンビンに響いて、この人の音楽は、何故、こういうところで生き生きと鳴り響くんだろう。なんでお客さんがこんなに共感しちゃうんだろうと思い、それから僕は、ショスタコーヴィチにのめり込み始めたんだ。
その経験がのめりこむきっかけとはいえ、井上の場合、ショスタコーヴィチが存命中の1970年代前半には、ヨーロッパで活動を始めており、旧ソヴィエト連邦を肌で知っている。これも、彼が最初に語った運の良さでもあり、巡りあわせでもあるのだろう。
井上 僕は、1970年の桐朋学園弦楽オーケストラのヨーロッパ・ツアーで31都市をまわったが、まずモスクワとレニングラードに行きました。ショスタコーヴィチが聴きに来たという話は聞いていませんが、彼と同時代を生きた瞬間があるのは確かです。その時の僕は、21歳でしたから、記憶が鮮やかです。食べ物もそうですし、街の色彩、そして、飛行場を撮るな、夜行列車のカーテンを開けるな、とか言われたことを覚えています。
井上は、その後、東ヨーロッパでも指揮をし、旧ソヴィエト連邦解体後にロシアでもいくつものオーケストラを指揮している。
普遍的な人間的な音楽
井上 時代は下って、2006年にロシアの数々のオーケストラを、地方の楽団も含めて指揮をするというツアーを無理やり組んでもらいました。僕は、飛行機代は出さなかったけれど、収入はゼロという形でした。僕は、ソヴィエトに生まれた人間ではないし、ヨーロッパで生まれた人間でもない。あと時代的にも遅れて生まれてきた。その旅の時、ロシアの楽団員の中には、ショスタコーヴィチは、ソヴィエト時代の音楽で、我々と違う時代の人だと言った人さえもいた。へえっ、て思ったね。ロシアの地方ではショスタコーヴィチもその程度なのだ。
確かに、ショスタコーヴィチの演奏回数にかけては、今や、日本こそがショスタコーヴィチ大国であることは間違いない。また、ロンドンでも演奏回数は多そうだ。
井上 ロシアの中では、意外と取り上げられていない。第2番や第3番なんかは、絶対にやらない。演奏機会があるのは、第5番と第7番、あと第8番や第9番くらいかな。何故かっていうと、なんかいろいろと面倒くさいんだろうね。後期の作品はユダヤ人問題が出てきたり、戦争に勝ったのか負けたのか、どっち側だみたいな問題が出てきちゃうから、それこそ触れたくないんだろうね。でもそんな事を超えて、普遍的な人間的な音楽なんだけど。

今回のインタビューは編集作業の現場である、EXTON Studio TOKYOで行われた
この後、井上はショスタコーヴィチの音楽について、次のように語ってくれた。
井上 ショスタコーヴィチという人は、10代から注目すべき作品を、思いっきり作曲した。それこそ、全てのクラシックの決まりを取り払いつつ、20代でオペラを書き、ピアノは、ショパン国際ピアノ・コンクールに出場するほどの名手でした。交響曲第1番は、世界的な名指揮者たちが取り上げた。その勢いで音楽的にやりたい放題して書いたら、大変なことになってしまった。オペラ《ムツェンスク郡のマクベス夫人》は、セックスそのものを舞台でやっちゃえみたいな書き方をしたわけでしょ。あれを舞台であからさまにやるのは、僕は下品だと思う。そうしたい欲望は、人間誰しも持っているんだけれど、それをやっちゃうと、やっぱり舞台は成り立たないところがある。結局、その時代の中心的な人々から“作曲家のやりたいことだけではなく、民衆や社会にとってもプラスになるものを書きなさい”と言われた。ショスタコーヴィチは、“わかりました。書きます”というふりをして、実際には自分の好きな女性の名前(リーリャ)を織り込んで、「リャ」(ロシア語のラ)の音が繰り返されて終わる交響曲を、聴く人にはどうとでもとれるように書いた。うん! それが第5番。
交響曲第5番は、かつては“苦悩から”勝利へ“の交響曲として、西側でも盛んに演奏され、日本では、《革命》という愛称が付されていた。作曲者の没後に刊行された『ショスタコーヴィチの証言』以降は、旧ソヴィエト連邦の体制に関連付けて語られることが多かったが、最近ではエレーナ・コンスタンチノフスカヤ(愛称はリーリャ)との恋愛にまつわる深い感情が込められている作品だという解釈も提示されている。
井上 でも、そんなことはずっと伏せられていた。言っちゃいけないことには、口に蓋をしていた社会がずっと続いたわけでしょ。それがペレストロイカで潰れて、さまざまな事実が明るみに出てきた。音楽の場合、調性を用いて書いたからといって、良い曲が書けるわけではないし、無調だろうが何だろうが、良い曲と悪い曲はあるわけだ。ただ、その判断基準は30年もたったら、僕たちが今、ああだこうだって言ってるように、全部否定される可能性もある。ショスタコーヴィチは一生かけて、何が求めるに値することか、自分が書きたいものこそ人間全てが望むことであるという確信を持っていたように思える。
そういう意味でも、ショスタコーヴィチの音楽は、これからも、聴き手に何かを強く訴えながら、生き残り続けるのだと思う。
②2度目の「ショスタコーヴィチ/交響曲全集」についてに続く。
音楽評論家。1959年東京都杉並区生まれ。1999年から現在の筆名を用い、音楽誌やCDのライナーノートの執筆を中心に活動中。旧『レコード芸術』誌の月評では、「再発売」を振り出しに、「ビデオ・ディスク」、「管弦楽曲」、「交響曲」の新譜月評を担当し、内外の音楽家たちのインタヴュー取材も数多く手がけた。2016年4月からNHK-FMの『名演奏ライブラリー』で案内役を務めている。