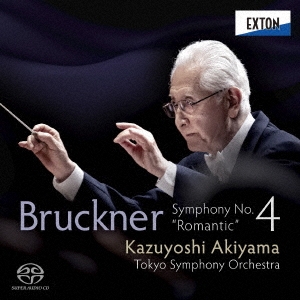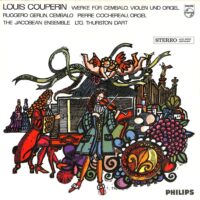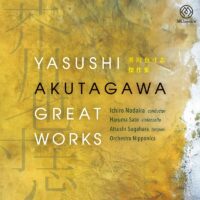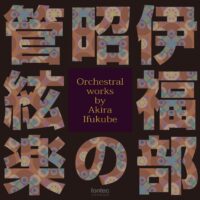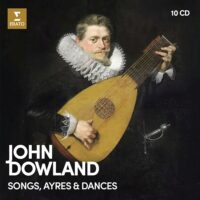文・写真提供:山野雄大(ライター/音楽・舞踊)
信じがたいマエストロとの突然の別れ

ほんの数年前のことだ。「いま、その音楽の凄さが極まる人にも関わらず、録音が(その実力に比して、著しく不当と言っていいほど)少ないマエストロは、秋山和慶だと思う」と記したことがある(『レコード芸術』2021年11月号)。
「80歳を迎えてなお現役、端正明快にして豊かな情報量をもつその指揮が引き出す、温かい生命力もいつしか内側からたぎり燃えてゆくような演奏……。温厚な人柄ながら妥協なく厳しい、〈我〉を超えた〈献身〉を昇華したその音楽を、録音芸術として味わえる機会がもっとあるべきだと強く感じる」
「高度なバランス感覚のなか、荒ぶる魂がめらっと炎をみせる瞬間が絶妙なマエストロ──円熟の先へ、重い扉をすっと開けるような凄みを〈いつのまにか〉感じさせるその音楽は、あらためて敬愛を捧げたい〈いぶし銀〉の芸術だ」
数年を経て、ありがたいことにマエストロ秋山の録音芸術はその数を増した。しかし、秋山先生が不意に去られてしまったこと、その音楽に新しく触れることがもうない、という事実が信じがたく、深く寂しい。
2024年12月31日の「MUZAジルベスターコンサート2024」までお元気に指揮をされていたのに、年の明けた元日に自宅で怪我をされ、治療に専念するため1月23日に引退を表明、しかし1月26日に入院先の病院で逝去。享年84。──なんと突然のお別れだろうか。
オーケストラと共に理想に
近づこうとする「妥協なき不屈」
マエストロ秋山和慶の振るコンサートを聴いて、身体中の血がざわめき止まないような昂奮を覚えた記憶が、いくつも蘇る。けれども、指揮台の上で秋山先生が我を忘れたような昂奮を見せている姿というのは、ついぞ記憶に無いのだ。獅子吼のような迫力を見せたとて、そこに立つのは品格に満ちた紳士の姿であり、そこから溢れ出す途方もない情熱をオーケストラにしっかりと注ぎ満たす、飾らずに的確無比な指揮の理想像だった。
スクリャービンの交響曲第4番《法悦の詩》の実演を聴いたとき(2023年7月、東京シティ・フィル定期)、その巨大なスケール感に満ちわたる豪奢絢爛をも突き抜けてゆくような美しいエネルギーの柱に、それこそ椅子に座っていられないような感銘に震えたことを思い出す。長い拍手喝采が終わるのももどかしく、舞台袖へ駆けつけて「先生、途方もない演奏でした……」と率直にお話すると、僅かに息のあがったような先生は、しかし穏やかな笑顔で開口一番、「いやぁ、オーケストラがとても良く演ってくれました」と仰った。
私が知る舞台袖の先生は、たいがいそうだった。長い歳月をかけて見事に育てられた広島交響楽団で、メシアンの難曲《7つの俳諧》を振られたとき(2017年3月「秋山和慶のディスカバリー・シリーズ」)も、真っ先に「リハーサル初日から全員ちゃんと吹けてたんですよ。凄いでしょう?」とご機嫌な表情で仰ったものだ(実際、凄かった)。まずは、オーケストラ。もちろん、多くのマエストロも最初に楽団の素晴らしさを讃えるものではあるけれど、秋山先生の場合、確固たる高い理想的な音楽へ共に近づき得た安堵、のようなものを感じるのだった。
とはいえ、褒めてばかりではない。「マエストロ、とても気持ちいい演奏でした」に「いやぁ、これでは小学生のようなものでね」と温厚な笑顔のまま返されたことは幾度もある(笑顔は笑顔なのだ)。楽屋や居酒屋でのとまらぬ音楽談義でも、厳しく率直な評をたくさん伺ったものだが、リハーサルでももちろん忖度なく、音楽家の皆さんにずばりと鋭く深い釘を刺しておられるのを幾度も見た。それは怒りではなく、雑なことを許さない、という凜とした姿勢だったから、厳しい愛と分かって受けとめる人たちを傷つけることはなかっただろうし、だからこそ先生の「オーケストラがとても良く演ってくれました」や「凄いでしょう?」には、揺るぎない自信を感じて、あらためてこちらの背筋も伸びるのだった。
そこに一貫していたのは、芸術への〈愛〉と〈不屈〉だった。──などと書くと、先生は苦笑いされそうな気もするけれど、もちろん、簡単に言葉にしてはいけないなにか、なのだ。それを分かったうえで書くならば、秋山先生の「ときにしなやかにたわみつつ、芯は決して曲げずに貫く」姿勢は、日本各地のオーケストラを育て耕し続けられた「妥協なき不屈」の歳月に体現された、深い愛ではなかったか。


このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。