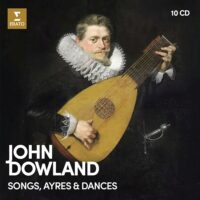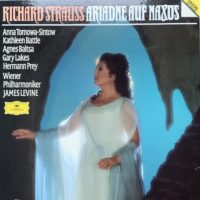2027年に没後200年を迎える、作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)。さまざまな録音プロジェクトが進行中と思われるいま、レコード芸術ONLINEでは、過去の「アニヴァーサリー・イヤー」に何が起こっていたのかを振り返ります。生誕200年(1970年)と没後150年(1977年)を迎えた1970年代は、ブレンデル、グルダ、エッシェンバッハ、ポリーニ、ワイセンベルク、アシュケナージなどのピアニストが盛んに録音を行い、多くの重要盤が生まれた時代でもありました。今回の記事では那須田務さんのナヴィゲートで、ピアノ曲(ソロ曲、協奏曲)の注目作が10点登場します。
Select & Text=那須田務(音楽評論)
遅れてやってきた、ベートーヴェン演奏の一大転換期
20世紀初頭に新即物主義が台頭するも、ベートーヴェンにおいては重厚かつ堅牢、即興的な趣があって時にはルバートもかけるというような演奏が「ドイツ伝統のベートーヴェン」として長らく生命を持ち続けた。ピアノでいえばバックハウスやケンプだ。しかし、1960年代に入って彼ら往年の巨匠たちが鬼籍に入るか引退したことで、レコード会社が新たな時代のベートーヴェン弾きを求めるようになった。作曲家生誕200年の記念年に始まる1970年代は、まさにそのような時代として特色づけることができる。その筆頭がブレンデル、グルダ、エッシェンバッハ。非ドイツ語圏のポリーニ、ワイセンベルク、アシュケナージ。彼らの演奏を一言でいえば、可能な限りの技術的な正確さを追求し、過大な響きや感情表現を退けた脱ロマン主義的なものとなろうか。もちろん天才グールドもその一人だが、彼はすでに50年代中頃から従来のベートーヴェン演奏の破壊を目論み、70年代には大方録音を終えているのでここでは取り上げない。こうした流れの先にあるのが古楽器演奏。フォルテピアノによるベートーヴェンの録音が本格化するのは1980年代になってから。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。