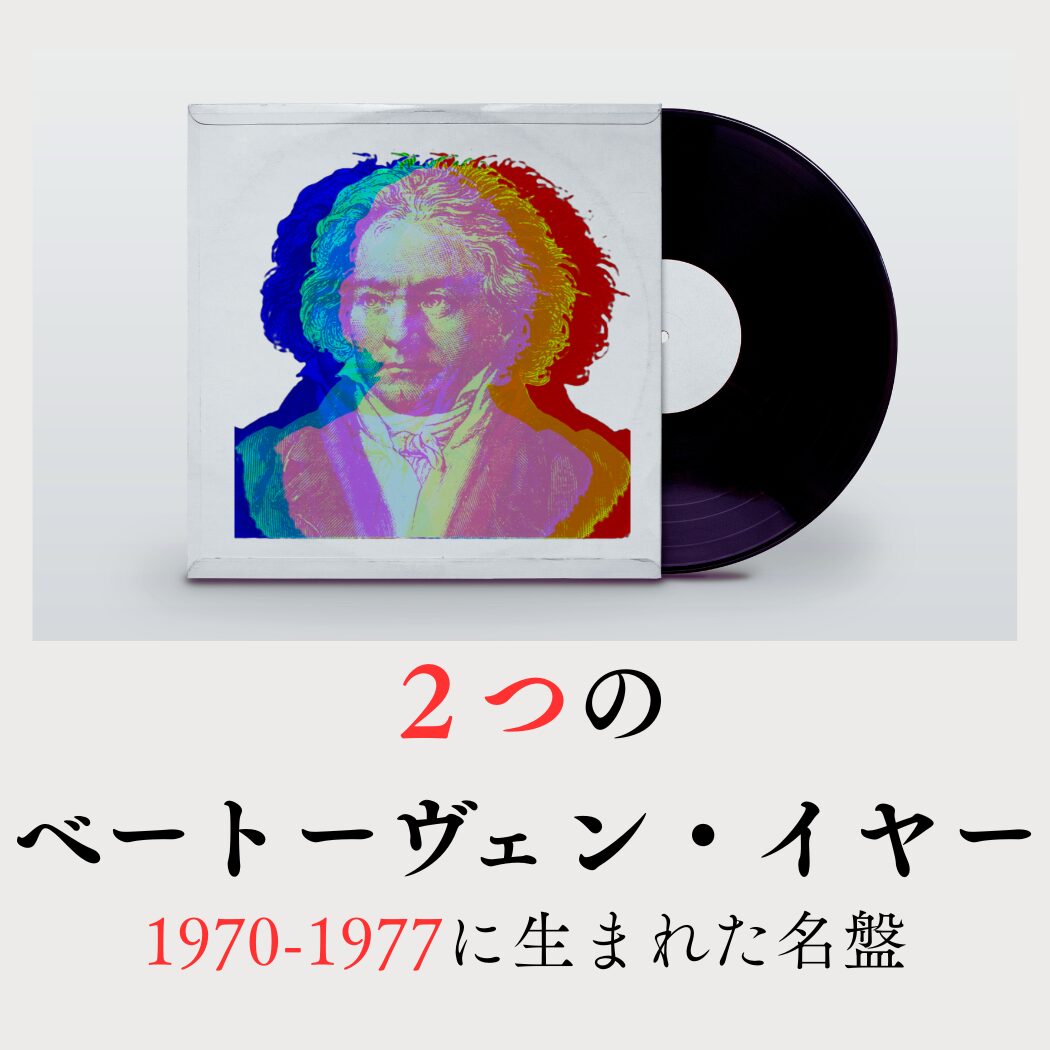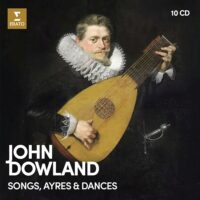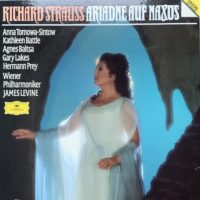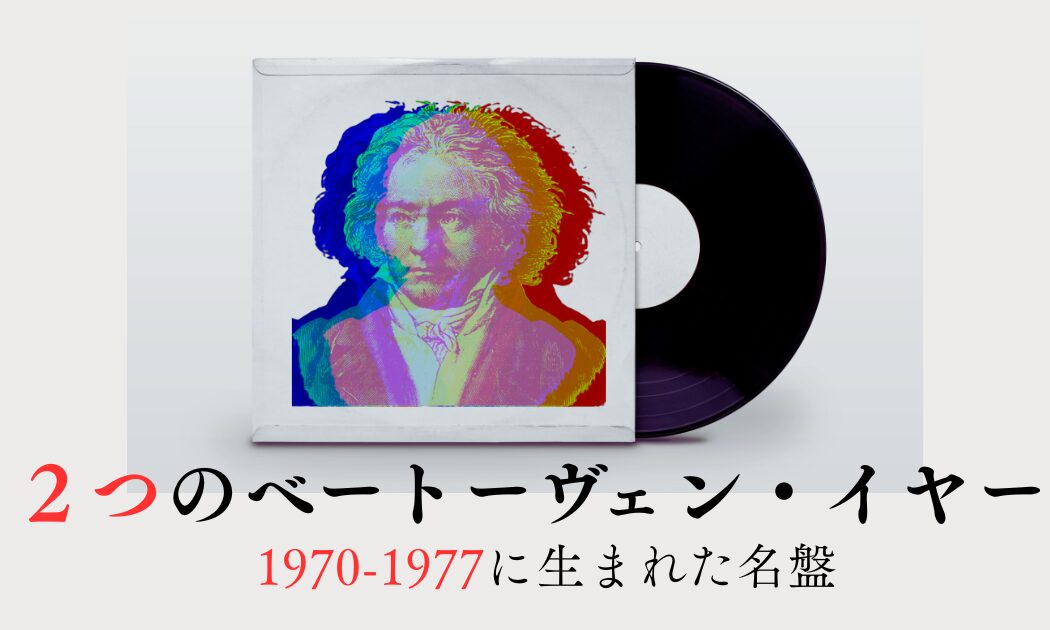
2027年に没後200年を迎える、作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)。さまざまな録音プロジェクトが進行中と思われるいま、レコード芸術ONLINEでは、過去の「アニヴァーサリー・イヤー」に何が起こっていたのかを振り返ります。生誕200年(1970年)と没後150年(1977年)を迎えた1970年代は、奇しくもアナログ録音の絶頂期と重なり、レコード産業始まって以来のベートーヴェン・ブームが巻き起こりました。芳岡正樹さんが「2つのベートーヴェン・イヤー」とその時代を振り返ります。
※本稿は旧『レコード芸術』2018年6月号特集「アナログ絶頂期「1970年代」に生まれた名盤たち」掲載記事を大幅に改稿の上、掲載しております
Select & Text=芳岡正樹(音楽評論)
ベートーヴェンとレコード、その不思議な因縁
ベートーヴェン(1770~1827)が2027年に没後200年を迎える。これはクラシック音楽界にとって、コンサートにおいても、レコード録音においても、またとないチャンスである。申すまでもなく、ベートーヴェンはクラシック音楽界が生んだスーパースターであり、その象徴でもあるからだ。ベートーヴェンが演奏され、録音されるということは、クラシック音楽の普及にもつながる。演奏家も、マネジメントも、レコード会社も、音楽出版社も、このチャンスを生かさぬ手はない。
加えて、2027年がレコード発明150年にあたる。ベートーヴェン自身は、録音技術の恩恵を受けることなく亡くなったが、没後50年の1877年にエジソンがレコードを発明したことで、没年の記念年がレコード発明のそれに重なることになったのは実に運命的だ。実際、没後100年の1927年にはSPレコードでクライスラーやバックハウス、ワインガルトナーなどによりベートーヴェンの名作群が次々に録音された。マイクロフォンによる電気録音が、その直前の1925年に始まったことを含め、なんという天の配剤だろう! 2027年、レコード会社とわれらが『レコード芸術ONLINE』は、ベートーヴェンとレコード発明のダブルアニヴァーサリーを迎える訳で、これを機に、過去100年にわたってベートーヴェンが録音され続けた意義を検証し、現代の新録音とともに大いに発売、宣伝し、クラシック音楽の振興に資するべきだと思う。
来たるべき2027年に向けて、過去のアニバーサリーを振り返る
ここで参考となるのが、1970年と1977年である。1970年はベートーヴェン生誕200年と、日本万国博覧会の開催が重なった。万博開催は一見、ベートーヴェンと関係ないようだが、『レコ芸』が目撃した名演奏家たち――1964~1974【第6回】1970年:大阪万博に世界の名門オケが大集結でご紹介した通り、クラシック音楽界も盛り上がり、カラヤン&ベルリン・フィルによる大阪フェスティバルホールでの5夜のベートーヴェン・ツィクルスは1万7千人もの聴衆を集めた。また、1958年に発売開始されたステレオLPレコードも1970年にはすっかり一般家庭に定着していた。海外企画で最も壮大だったのはドイツ・グラモフォンによる全12巻LPレコード79枚からなる「ベートーヴェン大全集」で、大小含めて約230曲もの作品を収録していた。英デッカによるシュミット=イッセルシュテットとウィーン・フィルによる交響曲全集、バックハウスによるピアノ・ソナタ全集も1970年を目指した企画だった。高度経済成長と大阪万博で盛り上がっていた日本では、東芝がEMI各国の音源を用い、足りない楽曲は若杉弘、深沢亮子、内田光子、巌本真理、岩崎洸、原田茂生などを起用して国内録音して補完。全24巻LPレコード89枚を1969年10月から1970年2月にかけて発売。約300曲もの作品を収録した、当時世界に類を見ない全集を完成させた。1枚物ではソ連の3人の巨匠を起用したカラヤンによる豪壮華麗な《トリプル・コンチェルト》が記念年に花を添えた。
1977年は世界的な不況期にあったが、ベートーヴェン没後150年とレコード発明100年が重なり、とくに交響曲全集の発売合戦が華やかだった。その中心はカラヤン&ベルリン・フィルの2度目の全集である(ドイツ・グラモフォン)。周到な準備のもと3年がかりで録音された全集で、本誌でも西村弘治氏による録音現場のルポを掲載するなど大きな話題を呼んだ。同年にはハイティンク&ロンドン・フィル(フィリップス→デッカ)とショルティ&シカゴ交響楽団(デッカ)の新録音が競合。ワインガルトナー(EMI→ワーナー)とメンゲルベルク(フィリップス→デッカ)の歴史的名盤も復刻され、ベートーヴェンとレコード録音史の深い結びつきを印象づけられた。
今回の特集が、2年後の2027年ベートーヴェン&レコード発明のダブルアニヴァーサリーを盛り上げるうえの一助となれば幸いである。
ベームの《フィデリオ》〈1969〉
西ドイツのDGと東ドイツのエテルナの共同制作。DGの「ベートーヴェン大全集」の第10巻として初発売された。エテルナも当時「大全集」に取り組んでおり、双方にメリットがあった。ちなみにカラヤンもEMIへ1970年に同オペラを録音したが、発売は翌年となった。東芝の「大全集」には1962年録音のクレンペラー盤が収録された。
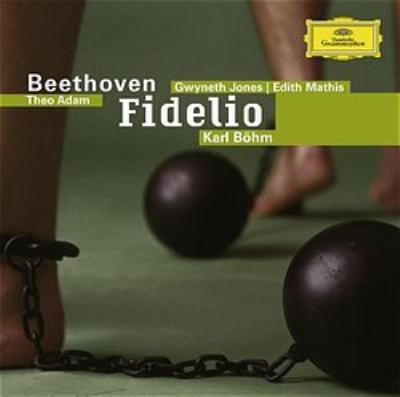
ベートーヴェン:歌劇《フィデリオ》全曲
カール・ベーム指揮ドレスデン国立o,ライプツィヒ放送cho,マルッティ・タルヴェラ,テオ・アダム(Bs)ジェイムズ・キング(T)ギネス・ジョーンズ(S)他
〈録音:1969年3月〉
[DG (S) 4775584(2枚組,海外盤)] 廃盤
シュミット=イッセルシュテットの交響曲全集〈1965~69〉
1965年の第9に始まり、1969年の第7で完結したこの名全集もベートーヴェン生誕200年を目指して制作されたもの。また、バックハウスのステレオによるピアノ・ソナタ全集も同様の企画だったが、1969年7月の巨匠の急逝により第29番のみ未録音に終わり、モノーラル録音を疑似ステレオ化して全集としたのは有名である。
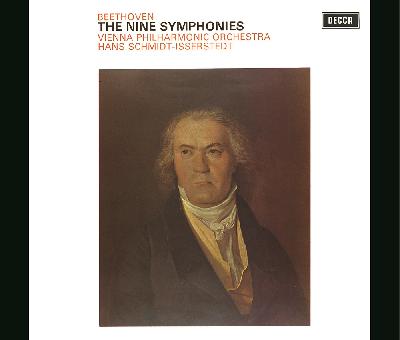
ベートーヴェン/交響曲全集
ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮ウィーンpo,ウィーン国立歌劇場cho,ジョーン・サザーランド(S)マリリン・ホーン(Ms)ジェイムズ・キング(T)マルッティ・タルヴェラ(Bs)〈録音:1965年11月22日~1969年6月9日〉
[デッカ(タワー) (S)PROC2072~6]SACDハイブリッド
カラヤン&ソヴィエト三大巨匠のトリプル・コンチェルト〈1969〉
1969年にEMIによって録音され、海外では1970年に発売されたが、日本では翌年2月にソ連メロディアの窓口であった新世界レコードより発売された。ソリスト3人がソ連のアーティストであったことが関係しているが、1987年以降は日本でもEMIレーベルより発売されるようになった。1971年度のレコード・アカデミー賞受賞盤。

ベートーヴェン:ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲(2011年リマスター)
スヴャトスラフ・リヒテル(p),ダヴィッド・オイストラフ(vn),ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc),ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンpo.
〈録音:1969年9月〉
[ワーナー・クラシックス(S)WPCS23035]
【メーカーページはこちら】
ワインガルトナーの交響曲全集〈1927~38〉
世界初の1人の指揮者による「全集」で、第8と第9以外は、1977年の発売が日本初復刻だった。しかも、これらの録音はパブリックドメインとなっていたためアルティスコ・レーベルからもほぼ同時にLP化され、同じ音源が2種類のSP復刻で競合。現在ではよくあることだが、当時は珍しいケースだった。
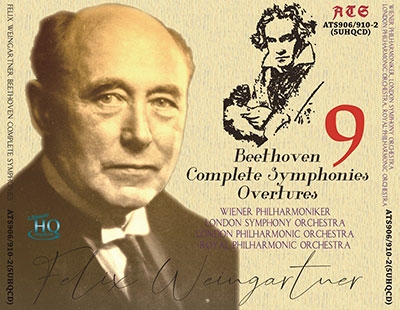
ベートーヴェン/交響曲全集
フェリックス・ヴァインガルトナー指揮ウィーンpo,ロンドンso,ロンドンpo,ロイヤルpo,ウィーン国立歌劇場cho,ルイゼ・ヘレツグルーバー(S)ロゼッテ・アンダイ(A)ゲオルク・マイクル(T)リヒャルト・マイア(Br)
〈録音:1927年~1938年〉
[ATS(M) ATS9062(5枚組)]
芳岡正樹(よしおか・まさき)
音楽評論家。1965年生まれ。広島大学法学部卒。9歳の頃からクラシックのLPに親しみ、学生時代より中古レコード店で働く。1997年7月発売のロジンスキー指揮「プロコフィエフ/古典交響曲」(ウエストミンスター-MVCW18012)のライナーノーツで執筆活動開始。以後CD解説、音楽専門誌、MOOKなどに執筆、旧『レコード芸術』誌には1997年12月号より2023年7月号の休刊まで約25年にわたり執筆した。