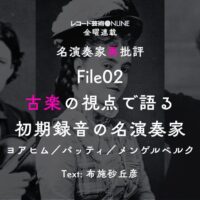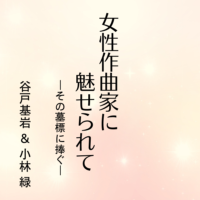アーティストは変態か?
Don’t be fooled by the title—“in vain”じゃない。
全然むなしくない、むしろ最高!
――クリス・ペプラー(人工知能による生成)
日曜日。多くのひとにとっては休日だが、わたしの場合はたいてい、日曜であっても大学の研究室でパソコンに向かっている。仕事がまるで終わらないのだから仕方がない。どうしてこんな人生になってしまったのかよく分からないのだが、きっと前世で何かやらかしたのだろう。
文献を読んだり、文章を書いたりするときに音楽は邪魔だが、事務的な仕事やデータを取るような作業の時にはCDをかけたりもする。もっとも日曜午後ならばラジオだ。J-WAVEの「TOKIO HOT 100」。これをかけっぱなしにするために、日曜日の13時~17時はなるべく事務的/データ的な仕事を入れるようにしている。
クラシックの仕事をしているとポップス方面には疎くなってしまいがちで、しかし一応「現代音楽」を看板に掲げているからには、同時代のポピュラー音楽にも少しは通じていたい。洋楽・邦楽問わず一通りの流行曲をかけてくれるこの番組は、その意味で貴重な情報源なのである(ちなみにこれを書いている4月13日は、HAIMの《Relationships》が先週に続いて1位。レコ芸読者の皆さんはHAIMをご存じだろうか?)。
翻ってクラシック音楽の「ヒット曲」を考えてみると、多くは百年単位でのヒットでもあるから、毎週ランキング番組を放送するのは困難だろう。しかし「現代音楽」であれば、少しは可能なのではないか。「TOKIO HOT 100」と同じようにクリス・ペプラーのナビゲートで現代音楽番組でも作ったら、この業界ももう少し活気づくように思うのだが。

SAISON CARD
TOKIO HOT 100
J-WAVE 毎週日曜日13:00~16:54
1988年にJ-Wave が開局して以来の看板番組。現在までクリス・ペプラーがナビゲータを務めている。
■
……そういえば、かつて現代音楽作品のランキングを試みた雑誌があった。
2017年、イタリアの音楽雑誌『クラシック・ヴォイス』が、2000年以降でもっともすぐれた現代音楽作品は何か、という問いを113人の審査員(音楽家、批評家など)に投げかけ、その結果を公表したのである。
作曲家別の集計結果でいえば、ゲオルク・フリードリヒ・ハースの作品群が49票を集めて第1位、以下、シモン・ステン=アナーセン(35票)、レベッカ・サンダース(30票)、ヘルムート・ラッヘンマン(26票)、サルヴァトーレ・シャリーノ(24票)、エンノ・ポッペ(21票)、カイヤ・サーリアホ(21票)、ベルンハルト・ラング(19票)、フランチェスコ・フィリデイ(19票)、そして10位のベアト・フラー(18票)と続く。さらに下位まで記せば、順にジェルヴァゾーニ、アペルギス、ロミテッリ、アンドレ、クライドラー、リーム、アプリンガー、ファン・デル・アー、プリンス、そしてミュライユ、となる。ここまでで20位。細かい順位はともかく、まあ、なるほど、というラインナップだろうか。
一方、作品単体ではどうかといえば、ハースの《in vain》(2000) が24票を集めてトップ。次にステン=アナーセン《ピアノ協奏曲》(2014)、サーリアホ《遥かなる愛》(2000)、プリンス《Generation Kill》がいずれも13票、続いてハースの《limited approximations》(2010)が12票、そしてステン=アナーセンの《Black Box Music》(2012)、ジョージ・ベンジャミンの《リトゥン・オン・スキン》(2012)が11票、といった具合。やはりハースが強い。
もちろん、このランキングは、一種のお遊び程度に考えた方がよいだろう。
「イタリア」の「一雑誌」によるという前提はもちろんだが、そもそも対象となる作曲家や作品が膨大だから、審査員のほうも「この前聴いたばかりだから」とか「うちの国の人もぜひ入れたい」とか「まあ、いいやつだし」というくらいの軽い気持ちで投票した可能性が十分にある(ちなみに審査員一覧を眺めていたら、ポール・グリフィスやピエール・アンドレ・ヴァラドに並んでYoichi Sugiyamaという名を発見。なるほど、イタリアの雑誌だからあり得る話だ。彼は誰に入れたのだろう?)。
しかしそうは言っても、結果は結果。
ともかくこのときには、113名の審査員のうち、49人がハースの作品を挙げ、そのうち24人が《in vain》を選んだのだ。ほとんどダブルスコアでの、圧倒的1位。クリス・ペプラーならば、きっとこんなふうに紹介してくれるはずだ。
“Hey hey hey, good afternoon, everybody! クリス・ペプラーです。
さあ、お待たせしました――ついに発表する、現代音楽のナンバーワン!
And taking that top spot… oh yeah, you better believe it…
オーストリアが誇る音の錬金術師―That’s right—Georg Friedrich Haas!!!
And the piece? It’s called ‘in vain’.
微分音を大胆に使って、照明まで味方につけちゃうという…もう、コンテンポラリー・ミュージックの革命児。音の渦に巻き込まれるその感覚、クセになります。
Don’t be fooled by the title—“in vain”じゃない。
全然むなしくない、むしろ最高 !
So get ready—volume up, lights down…
ここからは耳だけじゃない、全身で感じる時間です。
Here we go—‘in vain’ by Georg Friedrich Haas. Let’s dive in !
※これは筆者が作った文章をChat GPTに入れて「クリス・ペプラー風に」とお願いしたもの。さすがAI、まさにペプラー兄貴の声が聞こえてくるようではないか。
ゲオルク・フリードリヒ・ハース(1953-)
微分音、倍音の徹底的な使用で知られる人気作曲家。とはいえ、いわゆるIRCAM系のスペクトル楽派とはだいぶ作品の肌触りが異なる。現在はアメリカのコロンビア大学教授。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。