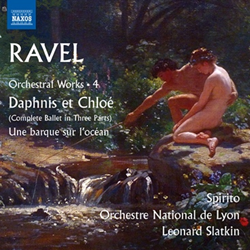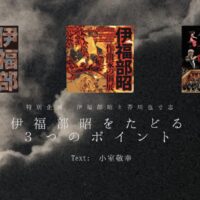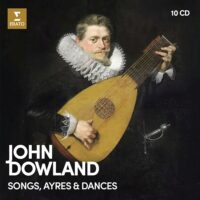生誕150年、モーリス・ラヴェル(1875~1937)! このことを祝して、レコード芸術ONLINEでは「ラヴェルと○○」という特別企画シリーズを始めています。
今回の記事は「ラヴェルと編曲」です。音楽ライターの小室敬幸さんによる執筆で、《海原の小舟》や《スペイン狂詩曲》といった自身のピアノ曲の管弦楽編曲を通して、ラヴェルのテクニックが成熟してゆく過程を明らかにしていきます。
「ラヴェルと編曲」後編はこちらから。
文・小室敬幸(音楽ライター)
「管弦楽の魔術」の秘密を理解するために
モーリス・ラヴェル(1875〜1937)はいかにして、日本では「管弦楽の魔術師」、フランスでは「un maître de l’orchestration(管弦楽法のマスター)」と称されるまでになったのか? ピアノ版と管弦楽版の比較を軸にして、その秘密を探るのがこの記事の目的なのだが、正しい理解のために前提を共有しておきたい。
まず管弦楽法の技術が「①個々の楽器への理解を深める」「②楽器の組み合わせ方を学ぶ」という2つの段階に大きく分けられるということだ。これはどの管弦楽法の教科書を開いても同じで、意外かもしれないが基本的には①に多くの頁数が割かれている。オーケストラという集団を巧みに扱うためには、各楽器が音域ごとにどう音色が変わり、演奏の難易度や精度はどの程度なのか、どんな音の並びなら無理なく演奏できるのか……等といった情報をくまなく理解しなくてはならないのだ。実際、ラヴェルは演奏家に楽器の可能性について、かなり執拗に質問を繰り返していたというエピソードが残っている。
一方、②については既存作品のスコアを参照しながら学ぶのが一般的で、教科書でも優れた実例となるスコアの抜粋が多数例示されているケースがほとんどだ(著者が管弦楽法の名手であるため、著者自身の作品が挙げられることも多い)。ラヴェルがよく参照していたのはベルリオーズ、リムスキー=コルサコフ、そしてシャルル=マリー・ヴィドールの著した管弦楽法であったという。
ベルリオーズとロシアの影響――《シェエラザード》序曲
ベルリオーズとリムスキー=コルサコフがラヴェルにとって管弦楽法の導入になったことは、ラヴェル最初の管弦楽曲《シェエラザード》序曲(1898)にあらわれている。編成はいわゆる2管編成が基調なのだが、ファゴットとトランペットが4本に拡張されているのは比較的珍しい。これはベルリオーズが《幻想交響曲》などで採用している編成を踏襲していると思われる(C管トランペット2+B♭管トランペット2と指定しているのは、ベルリオーズによるC管トランペット2+B♭管コルネット2を踏まえているからなのだろう)。またラヴェル自身はロシア音楽にかなり強く影響を受けたと語っている通り、ミュート付きトランペットの使い方などを筆頭に、実際に響くサウンドが《火の鳥》に至るまでの初期ストラヴィンスキーに近しいのは、晩年のリムスキー=コルサコフを参考にしているからだ。ロシアからの影響は1903年に作曲された管弦楽伴奏による歌曲集《シェエラザード》にも当てはまる。
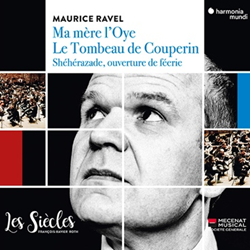
ラヴェル:バレエ音楽《マ・メール・ロワ》,《シェエラザード》序曲,クープランの墓
フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮レ・シエクル
〈録音:2016年~2017年〉
[Harmonia Mundi(D)HMM905281(海外盤)]
駄作が極端に少ないラヴェルだが、《シェエラザード》序曲は習作扱いでなかなか顧みられない。作品の主たる弱点はテンポや要素が細やかに変化する展開部以降にある。違和感なく、冗長じゃないように聴かせ、なるべくラヴェルらしさも出すことに成功しているのがロト=シエクル盤だ。それでも決して出来の良い作品とはいえないが、この作曲家の出発点として知っておいて損はない。
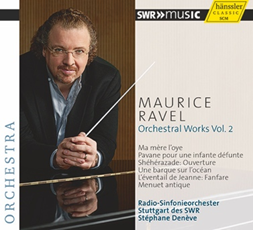
ラヴェル/管弦楽曲集第2集
ステファヌ・ドゥネーヴ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団
〈録音:2013年9月~2014年7月〉
[Haenssler Classic(D)93325(海外盤)]
ラヴェルらしさを大事にしたロト=シエクル盤に対し、展開部以降の処理が巧みであることに加え、スコアから滲み出る後期ロマン派の香りを隠さず表出させたのがドゥヌーヴ=シュトゥットガルト放送響盤である。最高潮に達したトゥッティ(総奏)から醸し出される表現主義にも近しいほどのロマンティシズムは、若きラヴェルがすぐに捨て去ってしまう要素のひとつだ。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。