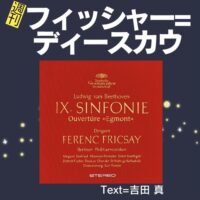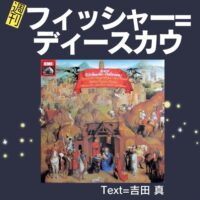彼女はジャンルを愛し、そして憎む
―――「音楽をジャンル分けするなんて意味がない。いい音楽があるだけだ」
マイルス・デイヴィス
今年の夏、文科省は理系学部に対する私学助成金を引き上げるという決定を行なった。めでたいことである……と思いきや、その分、文系学部の助成金を削るという。大学業界では「文系の学部を、ちょっとカタカナにして理系っぽく改組する」と文科省の覚えが良くなる、というのはもはや共通認識となっているが、つい昨日の新聞を見たら、天下の東京大学も「ディープテック学部」と「コンピューティング学部」を新設する予定だと報じていた。嗚呼。もちろんこれは文系学部の改組ではない。でも、「ディープテック」「コンピューティング」とは――音大教員の分際で思い切っていってしまうが――あまりにも頭悪そうなネーミングではなかろうか。
そういえば、ちょっと前に話題になった『文系と理系はなぜ分かれたのか』(隠岐さや香、星海社新書)は、一見すると頭悪そうなタイトルの本だが、しかし中身はいたって真っ当だ。ここでは文系と理系を別世界として捉える古くさい考え方と、もはや21世紀には文系理系の壁などない、という楽観的な考え方はともに「マッタ」をかけられて、歴史的にこのふたつのものの見方が成立してきた経緯や必然がじっくりと描かれてゆく。もちろん若い人が学問の世界に飛び込む際に、文理の壁などない方がよいとは思うのだが、しかし単に「世界に平和を」と唱えてもあまり効果がないのと同じように、壁をなくせと言うだけでは足りないことが、この本を読んでよく分かったのだった。
■
「ジャンルにとらわれず活動したい」といった発言をするクラシック奏者を時々見かける。もちろんレコ芸読者ならばよくご存じのとおり、若干の例外はあれ、これは大抵の場合、「ちょっとばかりポピュラー音楽っぽい曲や、ジャズっぽいこともやってみたいんです♡」という程度のステイトメントに過ぎない。で、そういう人に限って、ポピュラーやジャズをろくに知らなかったりするのも読者諸賢の知る通り。
世のポピュラー音楽家やジャズ奏者はおしなべてクラシック音楽に一定のリスペクトを払っているように見えるのだが、先のようなタイプのクラシック奏者はポピュラーやジャズに足を踏み入れるのは簡単だと思っている節がある。ちょっと下品な言葉をつかうと「ナメている」わけで、なんだか腹立たしいではないか(NHKの朝ドラ『あんぱん』が9月末に終了し、もはや毎朝「のぶちゃん」に会えなくなってしまったこともあって、このところのわたしはどうも機嫌が悪い……)。
「ジャンルにとらわれたくない」といった空疎な宣言などしなくても、理想的な知の中に文系理系がまったり溶け込んでいるように、優れた音楽であればごく自然にジャンルなど無効化してしまう。たとえばヴィンコ・グロボカールの音楽を(ニューフォニック・アート・アンサンブル時代も含めて)何らかのジャンルに当てはめることは難しいだろう。
あるいはフォルマント兄弟(三輪眞弘+左近田展康)の《フレディの墓》はどうか。この曲はポピュラー音楽と現代音楽の越境どころか、そもそも音楽なのか美術(アート)なのか、テクノロジーの展示なのか思想の開陳なのか、根本からして訳のわからない存在なのだ。そして当然ながら、その訳の分からなさが、そのままこの曲の豊かさにつながっている。
グロボカールやフォルマント兄弟まではいかないとしても、音楽家は常にジャンルの壁の向こう側を慎重に観察し、隙あらば参照し、謙虚に学び、場合によっては簒奪し、時には乗っ取ってしまうくらいの気概が必要だと思う――とりわけ「現代音楽」といわれる範疇の音楽に携わっているのであれば。
フレディ・マーキュリーが、「兄弟式」合成発音装置によって蘇り、同じくすでに「亡くなった」共産主義のテーマソング《インターナショナル》を日本語で歌うという曲。さらには作者による論文『デジタル・ミュージックにおける6つのパースペクティヴ』では、ベルナール・スティグレールに依拠しながら、このメディア的な事件について考察が加えられている。何度体験しても驚くべき巧緻な作品。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。