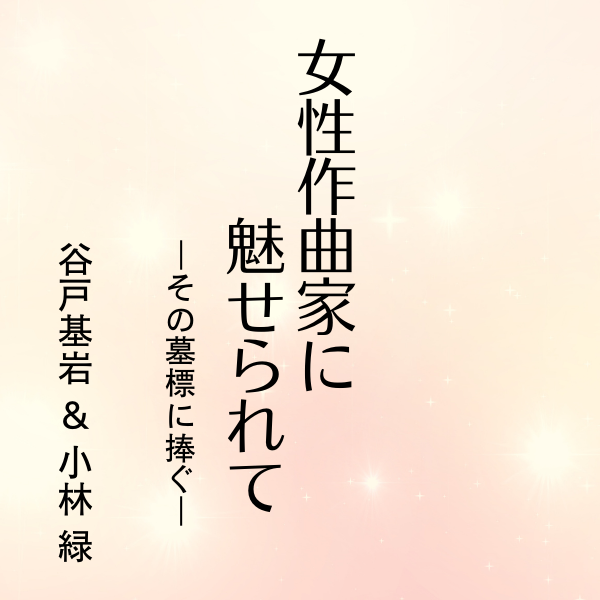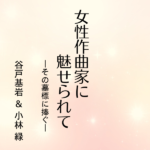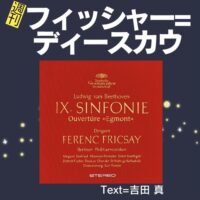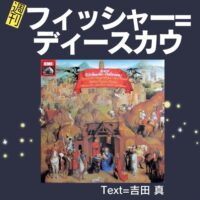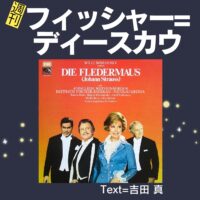ポリーヌとの出会い。バルトリの圧倒的に歌唱に接し開眼
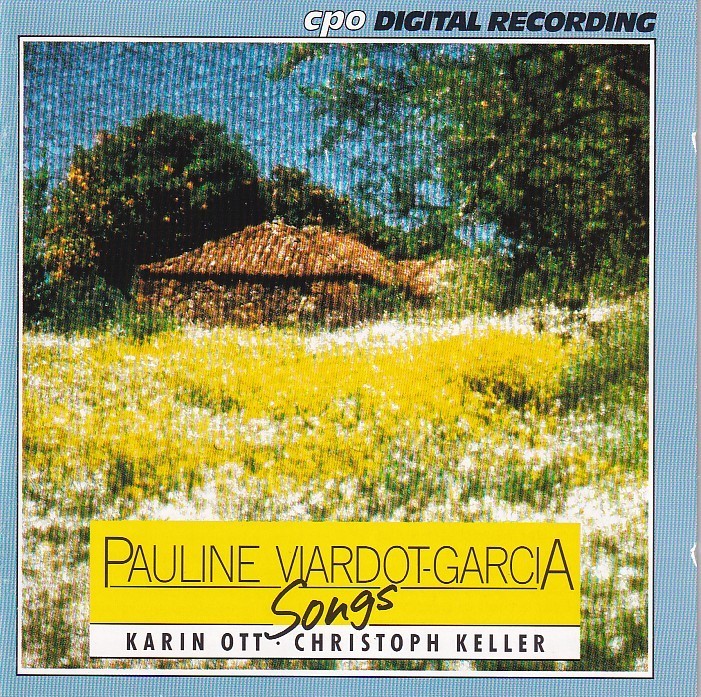
①Pauline Viardot-Garcia: Songs / Karin Ott (S), Christoph Keller(p)[cpo 999 044-2]
恐らく私が最初にポリーヌ・ガルシア=ヴィアルド(1821-1910)〔以下、ポリーヌと略す〕の作品に触れたのはスイスのソプラノ歌手カリン・オットのCPO盤のCD『ポリーヌ・ガルシア=ヴィアルド/歌曲集』(①)だったのではないか。改めて聴いてみると声の質がポリーヌにはややそぐわないものの、選曲のセンスが素晴らしく、好奇心をそそられた。また同じ頃にDA CAPO PressのWOMEN COMPOSERS SERIESの第22巻として出版された4人の女性作曲家の作品を収めた『Anthology of Songs』(1988年刊)も入手したが、その当時、私の関心はもっぱらルイーズ・ファランクの室内楽に向かっていた。レコード会社での編集業務の大変さから声楽を忌み嫌っていた谷戸基岩(そのくせ『カミーユ・モラーヌ/エラート録音集大成』は熱心に担当していたが……)のCD蒐集の偏りのせいもあったかもしれない。1993年には「女性と音楽研究フォーラム」という研究会を立ち上げ、横浜で女性作曲家の作品に特化したコンサートを企画した。そうした活動に旧知の間柄で、当時「東京の夏音楽祭1996」の企画委員だった船山信子が注目し、私に女性作曲家のコンサートを企画するよう依頼。それに応え4人の女性作曲家のフランス語(ソプラノ:秋山理恵)とドイツ語(メゾソプラノ:永井和子)の歌曲を取り上げた。フランス語の歌曲はオギュスタ・オルメスとポリーヌ、ドイツ語はジョセフィーヌ・ラングとアンナ・クラーマーによるものだった。正直に言えば、これら4人のうち当時の私はむしろ赤貧のうちに死んだオランダの悲運の作曲家クラーマー(谷戸が毎日新聞に紹介して一部で評判になっていた)、そして話題性にあふれたフランスの作曲家オルメスを重視していた。

②チェチーリア・バルトーリ/ライヴ・イン・イタリー(DVD)[DECCA UCBD1020]
ところがチェチーリア・バルトリのCDとLD(②)に接して事態は一変。わずか3曲〈アイ・リュリ〉、〈ハバネラ〉、〈カディスの娘〉(この曲はCDのみ)だったが、その音楽の豊かさと圧倒的な歌唱に接し、私はポリーヌにすっかり魅了されてしまったのである。とはいえ当時の日本で入手できたCDは限られており、アマリッリ・ニッツァによる全曲としては世界初録音となる『ショパン(ヴィアルド編曲):12のマズルカ、他』[伊AGORA]位しか聴けなかった。
ポリーヌ・ガルシア=ヴィアルド Pauline García-Viardot 1821-1910
オペラの名門ガルシア一族の生まれ。少女時代はリストに憧れピアニスト志望であったが、「女にとって成功の道は歌だけ」という母の意向で断念。人気の絶頂にあった姉の歌手マリア・マリブランの突然の死をきっかけに歌手デビュー。持ち前の幅広い声域と歌唱力、表現力により名声を上げ、マイアベーアの《預言者》では年老いた母親という異例の役回りで大成功を収め、オペラ・スターとしての地位を不動のものに。その至芸に魅了された音楽家・文化人は内外におびただしく、中でも重要なのがジョルジュ・サンド。彼女のお膳立てにより21歳年長のイタリア座支配人ルイ・ヴィアルドと結婚、4子を得た。ヴィアルド家の「木曜日」が当代随一のサロンと評された因はショパン、ミュッセ、ヴァーグナー等を含む華麗な人脈にあろう。1843年のロシア巡演に接したツルゲーネフは生涯熱烈な信奉者にして恋人。狩猟の趣味が共通である夫とも親交を結び、家族同然の間柄に。1848年のカンタータ《新しい共和国》は親しい友と共有した社会平等への志の賜物であった。1859年にグルック《オルフェオ》の大成功を最後に舞台から退いて後は作曲、歌の個人指導、サロン運営に注力。引退後もその威光は衰えず、サン=サーンスは歌劇《サムソンとデリラ》、ブラームスは「アルト・ラプソディ」をそれぞれ献呈。世紀末のジャポニズムに反応したパントマイム作品「日本にてAu Japon」も実に興味深い。〔詳しくは拙著「ポリーヌに魅せられて」(梨の木舎、2023)を参照されたい〕
パリで、バーデン=バーデンで、研究に没頭
そんな中、国立音楽大学の長期国外研究制度に応募し、在外研究者として1999年度の一年間フランスに滞在できることに。その研究のテーマとして「ポリーヌ・ヴィアルド」を掲げたのである。パリ16区の賃貸アパートに住み、フランス国立図書館(BNF)の音楽部門に足繁く通い、各種コンサートに出かけ、パンの笛、アリオーゾといった店で音楽書や楽譜を、フナックやヴァージン・メガ・ストアでCDを買い求めた。ただ私の滞在中に3度来仏した谷戸によるとCDに関してはフランスのマイナー・レーベル以外では日本の方が遥かに充実しているとのことだった。
このコンテンツの続きは、有料会員限定です。
※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。
【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。