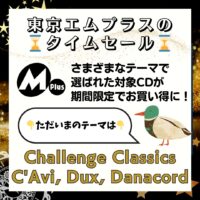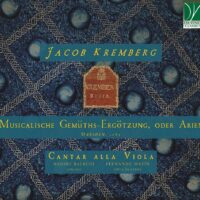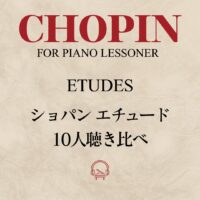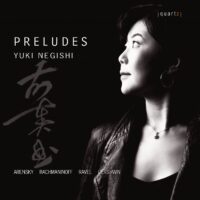国際室内楽コンクール3冠、ウィーンを拠点とする新星デュオ「Aka Duo(アカデュオ)」がポーランド室内楽の知られざる名作を紹介するアルバムを発表。ポーランド音楽国際コンクール(2023)優勝を果たした際、その演奏・解釈に感銘を受けたNIMiT(ポーランド国立音楽舞踏研究所)が提案して実現した当アルバムは、レコード芸術ONLINEのCD評でも推薦盤となりました。このアルバムについて、ヴァイオリンの松岡井菜さんからの寄稿を掲載します。

ポーランドの音楽
〔ユゼフ・エルスネル:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ニ長調 Op. 10 No. 2(1798頃),アルトゥール・マラフスキ:ブルレスケ(1940),アレクサンデル・タンスマン:ソナタ 第2番 ニ長調(1919),ミウォシュ・マギン:アンダンテ(1963),イグナツィ・ヤン・パデレフスキ:ソナタ イ短調 Op. 13(1885)〕
【演奏】
Aka Duo(アカデュオ)
松岡 井菜(ヴァイオリン)&木口 雄人(ピアノ)
[ACD-340(輸入盤・日本語解説付)]
試聴・購入はこちら
私たちがデュオとして活動し始めたのは2018年の夏、留学先であるウィーン国立音楽大学の室内楽クラスコンサートを聴きに行った私(松岡)が、たまたま出演していた木口さんの演奏を聴いたことがきっかけでした。そのとき彼はヴァイオリニストとラヴェルのソナタを弾いていたのですが、ヴァイオリンと共に呼吸し、共に歌う彼のピアノに惹かれた私は、終演後にすぐ声をかけに行きました。
「まずは一度でいいから一緒に弾いてください!気に入らなければいつでもやめていいから!」
そのときは、こんなに長くデュオ活動を続けられるとは思ってもみませんでした。

そこから早7年経ち、デュオとして2023年のポーランド音楽国際コンクールで第1位をいただいたことをきっかけに、Aka Duoとして初めてのCDをリリースすることとなりました。当初、コンクールから頂いた副賞の中にCD制作の副賞はありませんでしたが、嬉しいことに主催者の方々が後から私たちのために特別に用意してくださったのです! 私たちとCDを作りませんか?と事務局から連絡をいただいた時のことは今でも鮮明に覚えていて、本当に飛び上がるほどのサプライズで、私たちにとって大きなプレゼントとなりました。

収録は2024年7月、コンクールの受賞者コンサートでも演奏したワルシャワ・フィルハーモニーホールの小ホールで行われ、朝から夕方までの録音セッションが3日間続きました。

初めてのCD収録、やはり難しいことがいくつかあって、まず体力配分、そして曲ごとの気分の切り替え。夜型人間の私にとっては朝10時に体も頭も万全の状態に整えておくというのは、なかなか頑張らないといけない課題でした。また、特にコンサートと違って難しいなと感じた事のひとつに「空腹具合の調整」がありました。録音セッションは都度都度に休憩はあるものの、朝から夜までずっと本番さながらの緊張感と集中力を必要とします。そのため、しっかりご飯を食べてしまうと眠くなるし、かといって空腹では集中を保つのが難しく、食べることが大好きな私たちにとっては大きな試練でした。この3日間は、2人ともお気に入りの小さなおやつを大量に持ち込み常に調整することで乗りきりました。私のお供はグミ、ハリボーのトロピカルグミに大変お世話になりました。

収録初日は、まずホールに合わせて私の立ち位置やピアノの位置の確認、それを踏まえてのマイクの位置など様々な調整を30分以上かけてするところから始まり、お次はピアノの選定!ホール内にすでに用意してあったピアノが少し重めの音色だったので、ダメもとで尋ねてみるとピアノの変更も可能とのこと。お言葉に甘えすべてのピアノを見せていただき、どのピアノが適切かじっくり選ばせていただきました。ホールの裏で試奏を重ねた結果、最初のものより少し軽めで、デュオとして今回の収録曲が最も生き生きとする、深さがありながらも粒立ちの美しいピアノになりました。エルスネルの真珠さながらのミルキーな輝きを纏った音色から、マギンでの無機質かつ透明な音色、パデレフスキでは憂いや熱情を帯びた分厚い響きまで、それぞれの曲の色味を最大限に表現できたチョイスになったと思います。それに合わせ、ヴァイオリンも音色・音のバランスなどについて、細かくマイクの位置などを調整していただきましたが、その仕上がりのミックスなどは正にアッパレで、職人の仕事というのを間近で見させていただいた録音でした。

今回の収録曲は、ポーランド作曲家の作品のみ。ポーランド音楽国際コンクールで演奏した思い出の作品を詰め込んだわけですが、何を隠そう、このコンクールは全3ラウンド全て(時間にして1時間半!)をポーランドの作曲家のみでレパートリーを構成するという、大変ユニークなものでした。もちろん私たちも最初はそこまでポーランドの作品に知識がなかったわけですが、大変親切なこのコンクール公式サイトには何ページにも渡ってポーランドの作曲家及び作品リストが紹介してありました。私たちは掲載されるデュオ編成の全ての作品を聴き、そして楽譜を見、どの曲を演奏するかラウンド毎にしっかりイメージしながら決定しました。
タンスマンとマギンは木口さんのお気に入り。タンスマンはパリで長く過ごした作曲家で、ミヨーやオネゲルなどとも親交があった人でした。今回私たちが収録したソナタ第2番は彼の若い頃の作品で、起承転結の「転」ばかりを繰り返すような複雑な和音の移ろい、それによって繰り出されるドラマティックな展開が魅力のエネルギッシュな作品です。マギンはショパン国際コンクールやロン=ティボー国際コンクールなどで入賞し、ピアニストとして活躍していました。YouTubeでは彼のショパンの演奏を聴くこともできますが、その演奏活動の傍ら、ピアノ曲や他の楽器のために数十曲も作品を遺した作曲家でもありました。このCDは3つもソナタを収録しており、純古典派のエルスネル、フレンチ風×ロマンティシズムのタンスマン、そして情熱のパデレフスキが並ぶなか、マギンは全く違うオアシス感を出し、CD自体の風通しをよくする役割を果たしてくれていると思います。曲が始まった瞬間に空気をフッと変えてくれる、私たちのポーランド作品のレパートリーの中でも何度も演奏しているお気に入りの作品です。コンクール本選で演奏した際にはファイナルでのこの作品の演奏に対して、作曲者の娘さんであるマルゴット・マギンさんから「ミウォシュ・マギン賞」をいただいたこと、そしてそのマルゴットさんと直接お会いできお話できたことは、私たちにとって光栄で本当に幸せなことでした。

このCDのトリを飾る、そしてコンクールでは決勝のラストの曲でもあったパデレフスキの30分に及ぶ大作ヴァイオリン・ソナタは、私のチョイスです。私たちのレパートリーで勝負曲と呼べるもののなかに、R.シュトラウスのヴァイオリン・ソナタがあります。これが30分程のロマン派の大作で、情熱的でダイナミックな部分や、愛に満ちた甘く優しい所まで様々な色が出せるお気に入りの作品です。それに取って代わる、コンクールのファイナルや演奏会の最後を彩る作品があれば、と探して見つけたのがこのソナタでした。民族的な響きや踊りのリズム、そしてピリッとした芯の強さといいましょうか、太い精神性を感じるのは、パデレフスキのポーランド魂を感じる部分です。憂いを帯びつつも内に秘めた強い情熱や、アメリカで活躍した彼ならではの地平線の果てまで見えるような広大な大地を彷彿とさせるスケールの大きさを感じていただけたらと思います。
最後になりましたが、素晴らしい機会をくださったNIMiT – ポーランド国際音楽舞踊研究所 – の皆様とポーランドのレーベルCD Accordのクルーの皆さま、そしていつも私たちを支えてくださる恩師のシュテファン・メンドゥル教授、ペーター・シューマイヤー教授に心より感謝申し上げます。私たちのこのCDが、みなさまにとってお気に入りのポーランド作品やポーランドの作曲家を見つけるきっかけとなりましたら、これほど嬉しいことはありません。
松岡井菜(ヴァイオリニスト)

ヴァイオリニスト松岡井菜とピアニスト木口雄人が2018年に結成。2022年から2023年にかけて3つの国際コンクールで優勝したのを皮切りに欧州・アメリカで活躍の場を広げ、2024年夏には「ショパンと彼のヨーロッパ」音楽祭デビュー、2025年春にはウィーン楽友協会でのリサイタルなど活躍の場を広げている。日本でも2024年度第34回青山音楽賞バロックザール賞を受賞し、今後の活動も大いに期待されている。

ポーランドの音楽
〔ユゼフ・エルスネル:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ニ長調 Op. 10 No. 2(1798頃),アルトゥール・マラフスキ:ブルレスケ(1940),アレクサンデル・タンスマン:ソナタ 第2番 ニ長調(1919),ミウォシュ・マギン:アンダンテ(1963),イグナツィ・ヤン・パデレフスキ:ソナタ イ短調 Op. 13(1885)〕
【演奏】
Aka Duo(アカデュオ)
松岡 井菜(ヴァイオリン)&木口 雄人(ピアノ)
[ACD-340(輸入盤・日本語解説付)]
試聴・購入はこちら