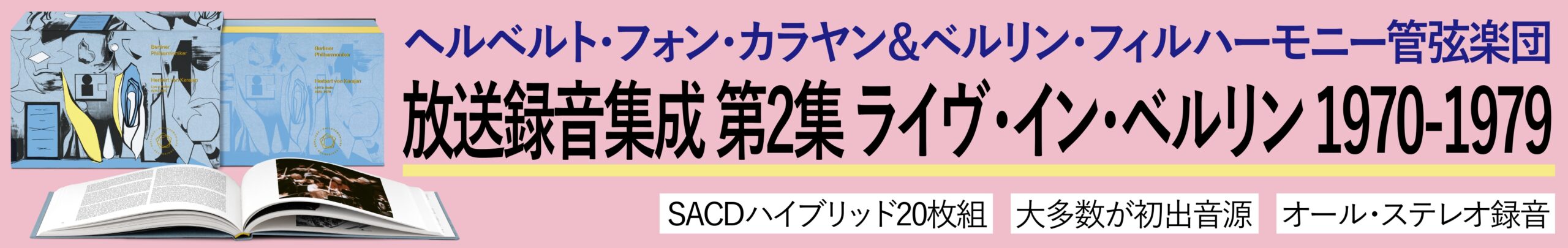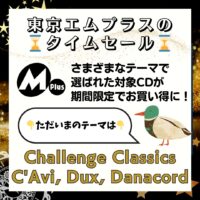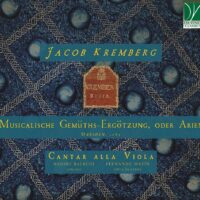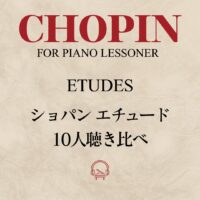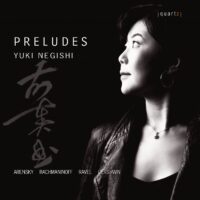ザンクト・フローリアンの夏の音楽祭ブルックナー週間(Bruckner-Tage)の常任指揮者として交響曲全集を完成させたレミ・バロー。2023年にリヒャルト・シュトラウス音楽祭(Richard Strauss-Tage)に招かれると大成功を収め、翌2024年には常任指揮者に任命された。ウィーンの老舗レコード店でもある「Gramola」レーベルは、ブルックナーに続き、リヒャルト・シュトラウスの作品集の録音を開始、今年その第1弾が登場する。リヒャルト・シュトラウスゆかりの地ガルミッシュ=パルテンキルヒェンで行われているこの音楽祭の歴史的背景と最新盤について、日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長の広瀬大介氏に寄稿して頂いた。
(同内容の文章がCD「レミ・バロー/リヒャルト・シュトラウス:英雄の生涯、ドン・ファン」国内仕様盤解説にも掲載されています)

リヒャルト・シュトラウス:交響詩《ドン・ファン》,同《英雄の生涯》
レミ・バロー指揮ピルセン・フィルハーモニー管弦楽団
〈録音:2024年6月6日 プルゼニ(チェコ)でのライヴ録音〉Měšťanská Beseda
[Gramola(D)GRAM99346](輸入盤)
[Gramola(D)NYCX-10518](国内仕様盤・日本語解説付き)
偉大な音楽家の名前を冠した音楽祭は数あれど、すべてがバイロイト音楽祭のように盛大な規模をもって開催されているとは限らない。リヒャルト・シュトラウスの場合は、歴史こそ四半世紀を越えるものの、そのみちのりは紆余曲折に満ちていた、と云わねばならないだろう。

そもそも、シュトラウスにゆかりの深いドイツの都市はどこなのか、という問題が立ちはだかる。生誕地のミュンヘンなのか、有名オペラ作品が数多く初演されたドレスデンなのか、はたまた歌劇場の音楽監督を長く務めたベルリンやウィーンなのか。いずれの都市で音楽祭が主宰されたとしてもまったくおかしくない。

だが、名乗りを挙げたのは、そのような大都市ではなかった。《サロメ》の成功によって望外の資産を得ることになったシュトラウスが、ドイツの南端、アルプスの麓の避暑地とも云うべきガルミッシュ=パルテンキルヒェンに別荘を建てたのが1908年のこと。初めはまさに夏の別荘という扱いだったのだが、やがて家族はここに定住するようになり、楽旅を繰り返すシュトラウスもここに戻ってきて作曲活動に勤しむようになった。以来、1949年に亡くなるまで、第二次世界大戦終結後の数年間はスイスへの避難を余儀なくされたが、シュトラウス一家は街はずれに位置するこの別荘を愛し続けた。

1989年、作曲家の没後40周年を記念して、ガルミッシュ=パルテンキルヒェン市は、その生まれ月である6月に、シュトラウス・フェスティヴァル週間の開催を決定する。旗振り役となったのは、当時バイエルン州立歌劇場の総監督を務めていたアウグスト・エファーディンク。このフェスティヴァルの開催によって、市民の側にも、シュトラウスの街である、という意識が芽生えるようになったのはごく自然な流れだっただろう。1997年には、学術的な研究を続けるミュンヘンのシュトラウス研究所が、ミュンヘン市の財政的援助が得られなくなったことによって閉鎖を余儀なくされた際、その後継者として名乗りを挙げたのもガルミッシュ=パルテンキルヒェン市であった。以来、研究所は同市で現在に至るまで積極的な研究活動を継続している。

音楽祭はその後も毎年開催されるが、市の財政規模が小さいことと、オーケストラやオペラの演奏に適した演奏会場が市に存在しないことも相まって、基本的には室内楽や歌曲の演奏を中心とした活動を続けている。夏の避暑地、冬のウィンタースポーツの中心地であり、ドイツ有数のリゾート地としてほぼ1年中、観光客の絶えない街ではあるものの、2023年現在で同市の人口が27,509人であることを考えれば、財政的に脆弱なのは致し方のない面もあるだろう。大規模なオーケストラ、あるいは演奏会形式によるオペラの演奏は、中央駅からほど近いアイススケート用のリンクを用いるのが常だった。ガルミッシュ中心地にあるコングレスハウスも1,000人程度を収容できるホールがあり、ここでも多くの演奏会が開かれた。
2009年から2017年までは、歌手・演出家として活躍を続けるブリギッテ・ファスベンダーがフェスティヴァルの芸術監督を務めた。歌手としての前歴を活かし、有名歌手を数多く招いてリーダーアーベントやマスタークラスを数多く開催し、若手歌手にとっての登竜門的存在となった。運営のかたちが変わった現在においても、ファスベンダーがのこしたこの伝統はかたちを変えつつ受け継がれている。

2009年からはリヒャルト・シュトラウス研究所が運営面を担当。2018~19年は、指揮者のアレクサンダー・リーブライヒが音楽祭の芸術監督を務め、ガルミッシュ=パルテンキルヒェンだけでなく、その周辺地域でも演奏会を実施するかたちへと拡大した。ドイツ最高峰のツークシュピッツェ山頂駅で開催したコンサートがその典型とも言えるだろう。だが、その後のコロナ禍で市財政も悪化し、リープライヒも退任。2020年以降は、シュトラウス研究所の所長であるドミニク・シェディヴィが代表を務めている。

2023年にこのフェスティヴァルに招聘されたのがレミ・バロー。ブルックナー・ファンにとっては、ザンクト・フローリアン大聖堂において、毎年1曲ずつ収録する交響曲全集を完成させた指揮者としてご存じの方も多いだろう。ここで成功を収めたことで、翌2024年には同フェスティヴァルの常任指揮者となった。バローはウィーン国立歌劇場のヴァイオリン奏者としても活躍し、その後で指揮の道を志している。いわば、シュトラウス作品における旋律、そしてそれらが組み合わさる対位法の感覚を、奏者としても体得していると言えるだろう。
2024年に演奏した《ドン・ファン》と《英雄の生涯》も大きな成功を収めた。このCDは、音楽祭の直前にオーケストラの本拠地で行われた演奏会のライヴ収録音源である。ブルックナー・シリーズに続いて、Gramolaレーベルが、リヒャルト・シュトラウス作品集の録音を手がけている。ピルゼン・フィルハーモニー管弦楽団は、チェコ西部の都市ピルゼン(ドイツ語、チェコ語ではプルゼニ)に居を構え、同市にかつて存在した放送オーケストラをその前身としている。2021年シーズンから岩崎宙平が首席指揮者に就任。バイエルン州のレーゲンスブルクにも近く、ドイツとの歴史的関係も深い。ピルスナー・ビールの発祥地として有名だろう。

現代的な機能性重視の一流オーケストラがグイグイと音楽を牽引するシュトラウス演奏を耳にする機会は多いが、その街の聴衆とともに歩み、暖かなサウンドを信条とするピルゼン・フィルの音楽は、どこか懐かしさを感じさせる。もちろんこのオーケストラとてグローバル化の中で多くの国籍を有する奏者から成り立っているが、こういう演奏によって、チェコの、そしてドイツの音楽文化が豊かに担われていること、その懐の深さをあらためて感じることができる機会を大切にしたい。今後も年1回のペースで続いてゆくであろう、新たな録音に耳を傾ける機会が楽しみである。
広瀬大介(音楽学)
写真提供:Dr. Dominik Sedivy/ Richard-Strauss-Institut

リヒャルト・シュトラウス:交響詩《ドン・ファン》,同《英雄の生涯》
レミ・バロー指揮ピルセン・フィルハーモニー管弦楽団
〈録音:2024年6月6日 プルゼニ(チェコ)でのライヴ録音〉Měšťanská Beseda
[Gramola(D)GRAM99346](輸入盤)
[Gramola(D)NYCX-10518](国内仕様盤・日本語解説付き)
企画・制作:ナクソス・ジャパン