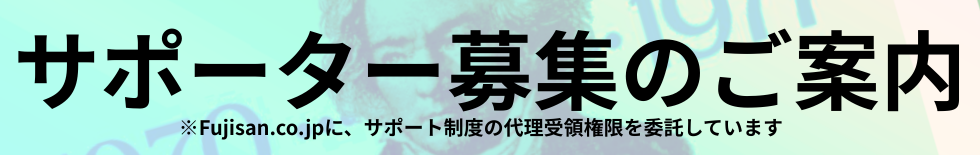「レコ芸アーカイブ 編集部セレクション」がスタートします。
このコーナーでは編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとに集めて、ご紹介していきます。
第1弾は「批評についての批評」。クラシック音楽メディアの「批評の場」として機能してきたレコ芸ですが、そのペンは時として、自らの行為にも向けられました。
12月は、1975年9月号(創刊300号記念特別号)に掲載された、秋山邦晴「音楽批評の音楽批評が音楽批評であることについて考える」を2回に分けて、連日お届けします。
※文中の表記・事実関係などはオリジナルのまま再録しています。
※今回の再録に際し、オリジナルにはない見出しを編集部で追加しています。
【構成】
・批評への批評の試み
・批評家が怖れるもの
・まずは方法論をもつことから
・小林秀雄と吉田秀和、その亜流について
・批評と論争の自由のために(ここまで①※無料公開)
・概念は流転する
・芸術のなかの「批評」の発見
・レコード批評について
・批評は最終回答ではない(ここまで②※有料公開)
※各見出しは、再掲にあたりレコード芸術ONLINE編集部が追加したものです
批評への批評のこころみ
こんなタイトルをつけたからといって、語呂合わせを愉しんでいるわけではない。これこそが今日の音楽批評の問題点であると、ぼくは考えているからにほかならない。
いいかえれば、編集部から与えられた「わが国の音楽批評の問題点は一体何なのか」という、いささか大上段にふりかぶったテーマにぼくが答えるためには、この問題をめぐってささやかな思考をめぐらし、また、いまだにこの根本問題の不在を意識さえしないために起こっているわが国の音楽批評の矛盾や弊害を指摘しなければならないだろう。
それでは「音楽批評の音楽批評」とは何か。
それは現状の音楽批評への批評といったことだけではない。
むろん批評への批評や論争といったことがほとんど皆無といった状態の日本の現状では、音楽批評への批評が大いにこころみられるべきであろう。結論をいそがずに、まず現状への検討をすることで、問題のありかを明確にしていくことにしよう。
それではなぜ、批評や論争が皆無なのか。
批評家が怖れるもの
まず批評家は権威の失墜を怖れるからである。他人の批評や批判によって、みずからの無能力ぶりを暴露れることが恐いのだ。ひとりひとりの批評家がそうした及び腰でいるわけだから、したがって相互間に、なるべく事を荒らだてて傷つけ合わないことという紳士協定が暗黙のうちに結ばれているようである。またこの協定は、それこそがわが国の「音楽批評家」すべての権威が失われない道であり、また「音楽批評」そのものの権威を失墜させないためであるといった、一種のすりかえのうえに成り立っているようにみえる。
それでは、ほんのたまに、何年に一度という僅少さで起こる論争はなぜか。しかし、それはほとんど論争といったものであったためしがない。結局はこの協定が破られて、あわてふためいて相互のあいだで繰り返される感情的なやりとりであることが、ほとんどのようである。それさえも、最後には、これ以上は「水掛け論」になるから……といったことで、焚火の最後よりもみじめったらしくおわる。
しかし、もともと批評の方法論がない批評家相互のやり合いなのだから、こうした結末になるのは、はじめからわかりきっている。つまり、それらは、演奏についてのそれぞれの印象批評のちがいが争点なのだから、100人いれば100人ともすれちがうわけなのだ。それにもかかわらず、第三者がXという演奏家に対するAとBとの批評がこれほど正反対な評価であるのはけしからん、などと発くものだから、AとBとは前述の危機を感じて、ときならぬやりとりをやらねばならぬ破目になる。印象批評であれば、AとBとが異なった結論をもつことが前提なのであって、そこに論点などありようもないし、はじめから水掛け論にすぎないのである。
問題は印象批評がいまだに成り立っているという現実かもしれないが、それよりも、そういった印象批評に権威づけをさせている批評家自身であり、楽壇の風土である。
批評家がすべての問題をとりしきる権力をもった権威であるかのような時代は、もうとっくの昔に過ぎ去った。そうしたすでに失っている権威などというものの失墜にいまだに怯えるところに喜劇的な様相が生じるのだ。演奏家、作曲家の側から批評家に向ってしばしば投げられる不満や無用論なども、こうしたもう失われてしまっている架空の権威に対してであることが多い。また印象批評がそのように権威づけられることに対してでもある。
まずは方法論をもつことから
それでは、どうしたら論争が活潑化するのか。
まず、こういった印象批評に権威づけをするかのようなあり方をつきくずすことが先決だ。そして、批評家ひとりひとりが批評の方法論をもたなくては論争など成立する可能性はない。ひとりひとりの立場が明確でないということは争点がないということだ。そこになんで論争などが、起こりうるだろうか。
つまり、「音楽批評の音楽批評」は批評の方法論をもつことからはじまるのだ。
戦後のわが国の音楽批評は、やっと近代を確立し、方法論をすこしずつもちはじめたというようなことがいわれる。はたしてそうだろうか。
たしかに、音楽批評の近代を確立しなければならないといった意識は、戦後の批評家たちのあいだから生まれた。そしてその場合、あるひとたちは文学の批評を手本にすることでそれをこころみようとした。そして直接的には小林秀雄をモデルとし、かれの『モーツァルト』がその美学の規範となった。
ぼくはそのこと自体をどうこう批判するつもりはない。ひとりひとりの批評家がなにから影響を受けようとも、それは個人的な問題にすぎないからだ。しかし、そうした方向こそが、まるで音楽批評の唯一の道ででもあるかのような風潮と化したとき、ぼくはその傾向をにがにがしく思った。
いま手元にその雑誌がないので、はっきりと思いだすことができないのだが、あれはいまから20年くらいまえのことだったと思う。ある綜合雑誌で批評の特集をやった。たしか文学の批評については江藤淳、美術は針生一郎といった各ジャンルの批評家たちが、それぞれの問題点を書いていた。音楽批評については、ぼくが書くことになったのだが、ぼくはたしか、新聞から演奏評を追放しなくてはならないなどと、かなり紅衛兵的に極論した。しかし、これはじつは前おきで、せいぜい400字1、2枚程度のスペースで、寸鉄人を刺すような一見技術批評的な印象批評では弊害こそあれ、音楽批評の役割を果すことにはならないことをいいたかったのだ。
小林秀雄と吉田秀和、その亜流について
そして、ぼくがそこで論じたのは、小林秀雄の亜流がはびこりだしてきたことへの批判であり、美文調の文体へのあこがれが、いかに音楽批評を空疎なものに追いやっているかということであった。
20年といえば、ふた昔。詳しい内容などいまではすっかり忘れてしまったが、要するにぼくは戦後の小林秀雄への音楽批評の傾斜を正面から批判したかったことだけは事実であった。
問題をあきらかにするために、あえて名前をだすことをお許しいただきたい。ぼくがこういえば、おそらく誰もが吉田秀和氏を想像するかもしれない。しかし、ぼくはほんとうは小林秀雄といわずに、吉田秀和の亜流と書いてもよかったのだ。吉田氏が実際に小林秀雄にどのように傾倒したかは、ぼくはしらない。そんなことより、吉田氏にはっきりとした吉田氏の文体があり、吉田氏の思考方法というものがつねにある。たとえば、エッセイ集『ソロモンの歌』(河出書房新社)の詩人中原中也について書いた一文を読めば、それは一目瞭然であろう。この特異な詩人の生前の追憶を語りながら、そこにこの詩人の特質とかれの詩の世界がもっているものに対して、じつに深い洞察を語りつづっているのである。その文章はよくいわれるような筆力のたしかな上手い文章であることはむろんだが、ぼくはそういう言い方よりも、明晰で、しかも感性のゆたかな詩的な文章だと思う。
そういえば、同じ本のなかに、氏が小林秀雄にふれた「三人」という一文がある。その出だしで、「小林秀雄の『モーツァルト』が〈創元〉という雑誌に発表され、それを読んだ時のショックは一生忘れられないだろう」と書いている。そしてこのなかで、ある有名な音楽学者の口から、「文章がうまいというのは得なもんだね」という『モーツァルト』への感想をきくに及んで、氏は「カッと逆上して、もう少しで食ってかかりそうになった」とも書いている。
これでもわかるように、吉田氏は小林秀雄の『モーツァルト』に美としてのショックをうけたのではない。むしろそこに「自分のできることすべてをその中に投げ入れる方法の啓示であり、一方では、どうやって、すべてを書きつくさないで、たくさんのものを与えるかという問題への答え」(吉田秀和)をみたのだった。
ところが大部分の小林秀雄亜流は、そうした方法論やものの見方を引きつぐのではなく、文学にあこがれ、美文調を音楽批評のなかにもちこもうとする滑稽なアナクロニズムに落ち込んだのだった。
こうした傾向には、もうひとつの悪い影響があった。小林秀雄とともに、もうひとり河上徹太郎の音楽批評の影響がついて廻ったということである。小林、河上両氏が悪いわけではない。音楽批評家のスノビズムだけが批判されるべきなのである。
このふたりの文芸批評家は、ともに昭和初期の最初の音楽グループ「スルヤ」のメンバーだった。そして音楽にすくなからず関わり、論じた。つまり、あまりにも遅くれてやってきた音楽批評への影響であった。この点については、『音楽芸術』誌に連載中の「日本の作曲界の半世紀」⑱(1975年6月号)でちょっと触れた。
ところで「自分のできることすべてをその中に投げいれる方法」としての音楽批評とは、ひらたくいえば、自分の生と音楽との一回かぎりの出会いを、自分に可能なあらゆる思考や体験の記録として追求する書き方といいかえられるにちがいない。「すべてを書きつくさないで、たくさんのものを与える」文体とは、いわばシンボリズムの文字の方向といえなくもない。こうした方法をとりながら、吉田氏は自分の音楽批評の世界をかたちづくっていったのである。
このことに気づかない多くの亜流は、ひたすら吉田氏から文章のうまさを学ぼうとし、文学への無力な羨望にますますみずからのコンプレックスを複雑化していった。半技術批評的美文調まがいなど、いずれにしろ、気持のいいしろものではない。当時、ぼくがにがにがしく思ったことも無理はなかったろう。さらにまずいことには、こうした自分と音楽との出会いを明晰に思考し、体験できない連中は、結局はその場しのぎの印象批評に落ち込んでいかざるをえないということである。
ただし、吉田氏自身にも、この方法をとるかぎり矛盾もでてくる。つまり、「自分のできることすべて……」の方法は、自分の生=思考・行動のフル回転をつねにもとめられる。たとえば、ぼくがつねに吉田氏の現代音楽への批評について批判的であり、そういった文章をたびたび書いてきたのも、その矛盾についてであった。いいかえれば、吉田氏のこういった姿勢は、ひとたび現代の音楽に出会うと及び腰となり、視点の明確さは薄れ、過去の文脈のなかに無理やりに引きこむことで、あるひとつの答えをだしたそうな誘惑にさえ落ち込んだりする。たとえば、近刊の『現代音楽を考える』(新潮社)のなかで、音色旋律などの音色構造の問題を、過去の「色彩論」をひきだすことでつじつまを合わせようとしていたりする文章に出喰わすと、ぼくはまたかという思いになる。
これは現代の音楽だけについてではない。ちかごろは現代の〈演奏〉についても、そうした矛盾が露呈されたりすることがある。いかにも残念なことだ。
批評と論争の自由のために
ぼくがいちばん初めに書いた批評は、たしか1950年、ある新人作曲家のデビュー作品について書かれた批評への批評だった。楽壇の大批評家がなんと「音楽以前である」というたった一語で片づけていたことに対しての批判をこめて、新人への批評とはどうあるべきかを書いたものだった。ほとんど無名の若輩がずいぶん大それたことを書くねと、当時楽壇通のひとが、ぼくにその無謀さをいさめるように微笑したのを、いまでも昨日のことのように思いだす。しかし、楽壇のなかに巣くうこうした感情的な状況がどのように根強いものであるかは、その後ぼくにもよくわかった。だが、感情的な状況や楽壇政治は、音楽批評を確立するためには障害にこそなれ、益するものはなにひとつない。それはいうまでもない。だから、先輩批評家に対しても、いいたいことははっきりといってきたつもりである。下世話に及んだが、ぼくの体験からいって、この状態はいまだに巣くっていると思う。このような批評や論争が自由におこなわれるような討論の場の不在が、わが国の「音楽批評の音楽批評」をはばんでいるともいえる。
*
次回(有料公開)に続く。
1929年生。51年音楽雑誌『レコード音楽』編集長を務め、芸術グループ「実験工房」に参加。52年早稲田大学仏文科中退。同時期に評論活動を活発化。対象はクラシック音楽のみならず、前衛音楽、映画音楽、詩の世界にまで及ぶ。71年から75年にかけて『レコード芸術』に「日本の作曲家たち」を連載。78年には書籍化された。96年没。